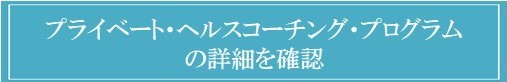バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。
心と体をつなぐホリスティックな食事法について、
ニュースレター登録者限定のキャンペーン情報等も配信しています。
ご登録は、こちらから
もれなく統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます
目次
大豆イソフラボンは植物性エストロゲン
大豆にイソフラボンが含まれていることが発見されて以来、大豆と乳がんとの関係については曖昧な状態が長く続いていました。
イソフラボンは、ヒトが副腎で造る副腎皮質ホルモン(ステロイドホルモン)に似た化学構造をもっています。例えば、男性ホルモンのテストステロンや女性ホルモンのエストロゲンです。
そのため、イソフラボンは、植物性エストロゲンとか、エストロゲン様物質などと呼ばれます。
婦人科系のがんや疾患は、多くがエストロゲンが多過ぎることで起きます。
そのため、大豆や大豆製品がホルモンに影響を起こすのではないか、特に、婦人科系のがんリスクを上昇させてしまうのではなかと、いった懸念を生みました。
そして、イソフラボンと乳がんとの関係は、多くの研究の対象となってきました。
(裏付けとなる研究報告は、最後に参考文献として一覧にしています。)
イソフラボンは乳がんの原因物質か?

これまでは、乳がんを患っている女性に対して、多くのがん専門医が、確信は持てないものの、万が一を考慮して大豆を食べないようにと、指導してきました。
また、もし今現在、あなたが乳がんと戦っているとしたら、大豆を食べることに不安を感じているかもしれません。
健康志向の高い女性達の中には、乳製品よりも大豆製品を怖がる人達も多くいます。
しかし、牛乳の方がエストロゲン(しかも動物性のエストロゲン)を多く含んでいるので、乳製品こそ避けた方が良いものなのですが・・。
大豆は乳がんを予防するのか?

アジア人に予防効果が認められた
日常的に大豆と大豆製品を食べているアジア人とアジア系アメリカ人を対象とした、2008年に行われたメタ分析では、大豆製品は、がんの発症を高めるのではなく、予防していることを示していました。
大豆(豆乳や豆腐などの大豆製品を含む)を食べない女性と比較し、大豆と大豆製品を多く食べている女性は、乳がん発症率が約29%低かったことを報告しています。
また、2014年のメタ分析では、大豆を多く食べてる女性は、乳がん発症リスクが41%も低いことが示されました。
しかしながら、この違いには遺伝的要因や生活様式の違いなどの多くの要因が関与しているため、大豆の摂取と乳がんに関する他の疫学的研究では、矛盾する結果も報告されています。
予防もしないがリスクでもない
多くの観察研究は、成人において大豆イソフラボンの高用量の摂取が乳がんを予防するという見解を残念ながら支持していません。
予防効果については賛否両論あるものの、乳がんリスクを高めるという報告もありません。
思春期に大豆を食べていることが重要?
アジア人にだけ、大豆の乳がん予防効果が確認された理由のひとつとして、大豆製品を食べている期間の長さが関係しているのではないかと考えられています。
特に、アジア人は、豆腐やテンペや味噌や枝豆など、あまり加工されていない大豆製品を子供の時から日常的に食べていることが、世界のどの人種よりも乳がん発症率が低い原因なのではないかと研究者は述べています。
特に、乳腺が発達する思春期にたくさんの大豆を日常的に食べていることが重要なのではないかとの推察もなされています。
限られた他の研究でも、若い頃に大豆食品をより多く摂取することが、成人期における乳がんの危険性を減少させる可能性が示唆されています。
大豆は乳がんの再発を抑制する

『米国臨床栄養学ジャーナル(the American Journal of Clinical Nutrition)』は、 2012年に、過去に乳がんを患ったことのある女性(乳がんサバイバー)を対象に「豆腐や豆乳等その他の大豆製品は乳がんの再発に影響を与えるか」という仮説を検証した研究結果を発表しました。
合計9,514人の乳がんサバイバーのうち、少なくとも毎日枝豆を半カップ以上食べていた、大豆を多く食べていた女性の乳がん再発率は、約30%低かったと報告しています。
つまり、大豆は、人種に関係なく、乳がんの再発を抑制する効果を持っていることになります。
大豆は病因に関係なく死亡率を低下させる

米国国立がん研究所(National Cancer Institute)の、1995年以降の患者の臨床データやアンケート回答が記録されている、「乳がん戸籍簿(the Breast Cancer Family Registry)」に登録のある6,235名の米国人とカナダ人の乳がん患者を調べた最新の研究では、次のことが示されました。
イソフラボンを豊富に含む食品を食べることは
病因に関係なく死亡率の低下と関係している
女性で顕著な差
この傾向は、特に女性において顕著に表れていました。
最も多く大豆製品を食べていたグループと、最も少なく食べていたグループの間には、約21%もの死亡率の差が存在していました。
悪性乳がんに効果大
更にこの死亡率の差は、次に該当する乳がんの女性で最も顕著でした。
- ホルモン受容体陰性乳がん(悪性タイプ)
- ホルモン療法を受けてない乳がん
言い換えれば、悪性乳がんを発症している、あるいは、ホルモン療法を受けていない乳がんの女性が、大豆や大豆製品を多く食べることで生存可能性を高めることが期待できるということです。
今まであまり大豆を食べてこなかった人は、今からでも大豆を食べ始めませんか?
悪性ではない乳がんにももちろん効果あり
大豆はエストロゲン受容体陽性乳がん患者の生存にとっても重要であることが報告されています。
そして、ホルモン療法を受けている人にも改善効果が期待できます。
大豆製品の選び方

大豆製品を食べる時に注意しなければいけないことがあります。大豆や大豆製品なら何でも良いわけではありません。
大豆
大豆そのもの、あるいは、原材料として使用されている大豆は次のようなものであることが重要です。
- 遺伝子組換えでない
- 残留農薬がない/少ない
自然栽培(無農薬・無肥料)、無農薬栽培、有機栽培などの大豆を探してくださいね。
大豆加工食品
豆腐や味噌、豆乳、テンペなどの大豆の加工製品は、次の様なものを選ぶことが大切です。
- 加工度合いが最小に留められているもの
- 不要な添加物が使用されていないもの
加工の度合いが大きい大豆製品には、予防効果は期待できないと研究者は述べています。
最近、様々なフレーバーが添加された豆乳が出まわっていますが、香料などで味がつけられているものは避けましょう。
東洋医学の視点を加えると
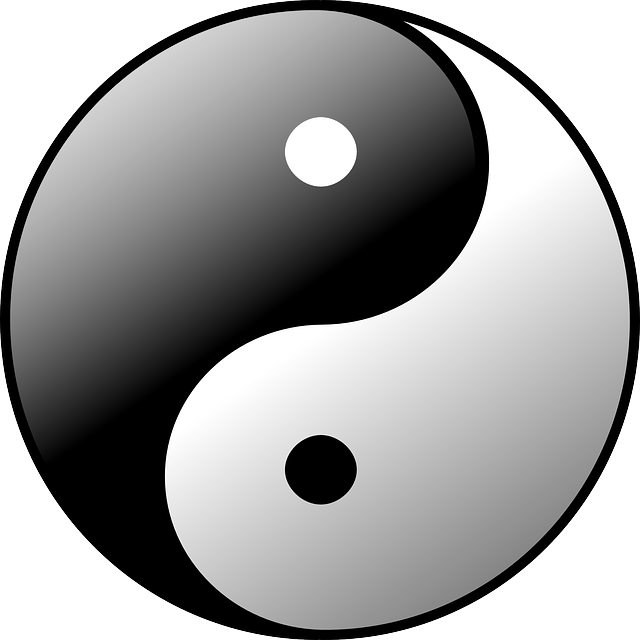
この研究では、大豆の加工の種類別の効果についての分析は行われていません。
例えば、大豆を豆腐や豆乳など、ほぼそのままの状態で摂る方がいいのか、納豆や味噌など発酵してから摂った方が良いのかなどの区別は行われていません。
そのため、東洋医学にその回答を探してみました。
陰陽道
東洋医学の陰陽道の考え方では、大豆にはそれぞれ、状態によってもっているエネルギーの質が異なります。
- 大豆と豆腐は「陰」
- お味噌と納豆は「中庸」
- お醤油は「陽」
と、区別されます。
東洋医学では、体を「中庸」に保つことが健康にとって重要だと考えますから、「中庸」の食べ物を多く食べることを一般的には勧めます。
つまり、どの年齢の人であっても、大豆を食べるなら基本は、お味噌や納豆などの様に発酵させてから食べることが好ましいと言えます。
「陰」が不足がちの人/「陽」が強すぎる人
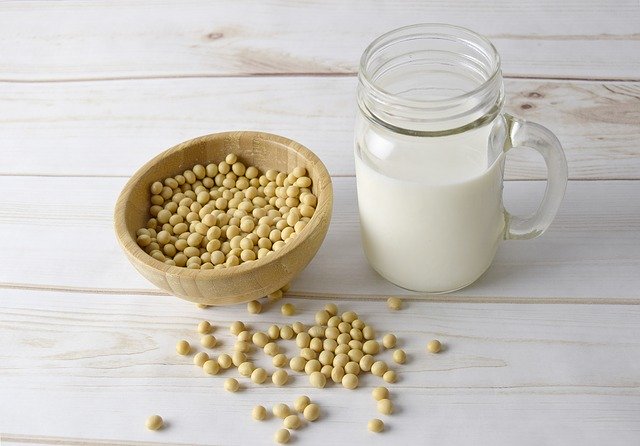
例えば、生理不順がある、暑がり、行動が粗暴などの傾向がある人は、「陰」のエネルギーを補充することでエネルギーのバランスをとることが大切です。
そのため、大豆そのものや豆腐や豆乳がお勧めです。
「陰」が強すぎる人/「陽」が不足しがちの人

例えば、ネガティブ思考、行動が消極的、うつ状態、冷え症、更年期症状があるなどの傾向がある人は、「陽」のエネルギーを補充して体内エネルギーのバランスをとることが大切です。
そのためには、大豆は発酵させてから、あるいは、お醤油なども加えると良いと言えます。
更年期の女性
更年期の女性は、『女性が若々しくいる秘訣を東洋医学から得る』、『更年期症状の予防と改善のための統合食養学的アプローチ』も併せてご確認ください。
甲状腺機能低下症の人
甲状腺機能に問題のある人の大豆との付き合い方については『甲状腺機能低下症の予防と改善(2)- 食事』をご確認ください。
ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス
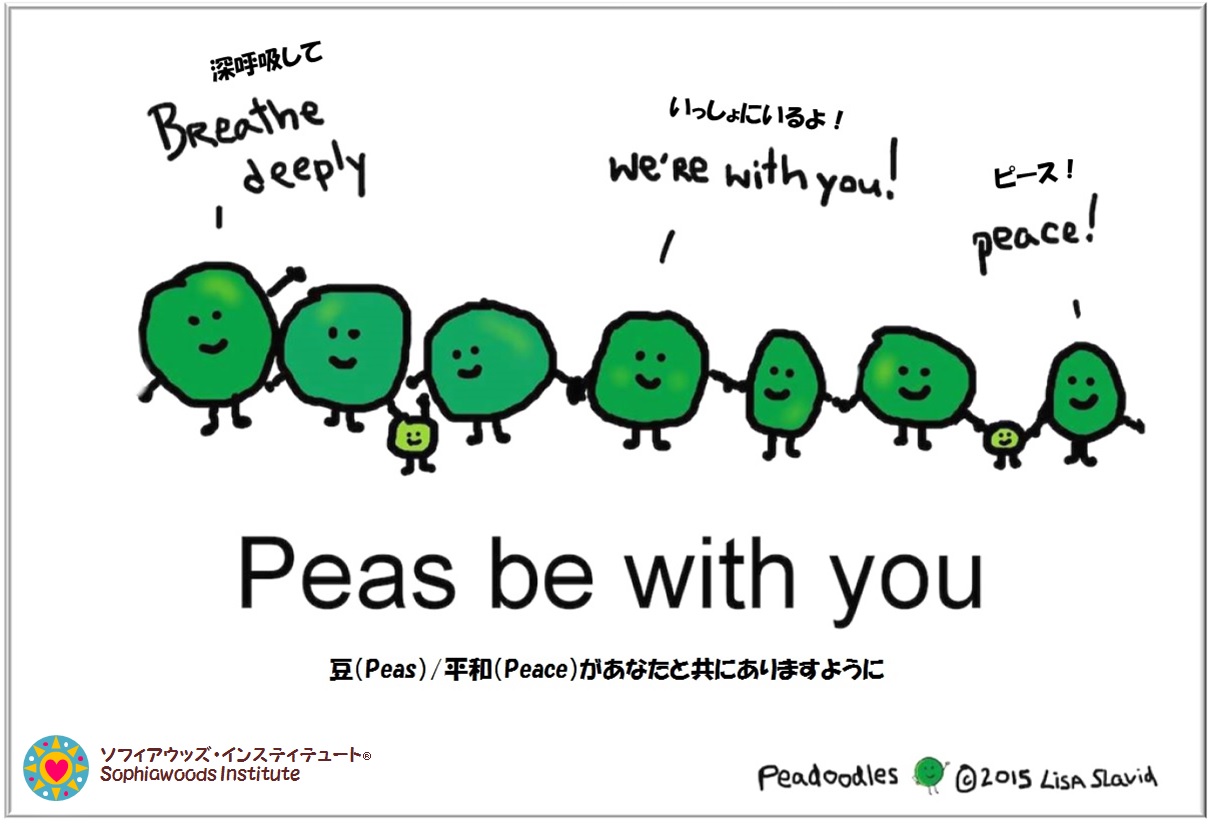
乳がんを予防したい、乳がんの再発を予防したい人は、『乳がんを予防する食とライフスタイル10の戦略』も併せてご確認ください。
でももし、ひとりで取り組むことに不安や難しさを感じているのなら、ヘルスコーチと、一度、話をしてみませんか?
公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。
プライベート・ヘルスコーチング・プログラムについて
お気軽にご相談ください。
初回相談を無料でお受けしています。
あるいは、ソフィアウッズ・インスティテュートのマインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースで学びませんか?セルフドクターコースでは、あなたが食を通してご自身の主治医(セルフドクター)になるために、必要な知識とスキルを教えています。
新学期は、毎年3月と9月です。講座でお会いしましょう。

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる
ニュースレターのご登録は、こちらから
統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます
参考文献:
- “Jazz Tofu”, Dr. Neal Barnard, September 8, 2015
- “Epidemiology of soy exposures and breast cancer risk”, Wu AH, Yu MC, Tseng CC, Pike MC, Br J Cancer. 2008 Jan 15;98(1):9-14. doi: 10.1038/sj.bjc.6604145. Epub 2008 Jan 8.
- “Association between Soy Isoflavone Intake and Breast Cancer Risk for Pre- and Post-Menopausal Women: A Meta-Analysis of Epidemiological Studies”, Meinan Chen , Yanhua Rao , Yi Zheng, Shiqing Wei, Ye Li, Tong Guo, Ping Yin, February 20, 2014https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089288
- “Soy food intake after diagnosis of breast cancer and survival: an in-depth analysis of combined evidence from cohort studies of US and Chinese women”, Nechuta SJ, Caan BJ, Chen WY, Lu W, Chen Z, Kwan ML, Flatt SW, Zheng Y, Zheng W, Pierce JP, Shu XO, Am J Clin Nutr. 2012 Jul;96(1):123-32. doi: 10.3945/ajcn.112.035972. Epub 2012 May 30.
- “Dietary isoflavone intake and all-cause mortality in breast cancer survivors: The Breast Cancer Family Registry”, Zhang FF, Haslam DE, Terry MB, Knight JA, Andrulis IL, Daly MB, Buys SS, John EM7, Cancer. 2017 Jun 1;123(11):2070-2079. doi: 10.1002/cncr.30615. Epub 2017 Mar 6.
- “Soy Food Intake and Breast Cancer Survival”, Xiao Ou Shu, MD, PhD; Ying Zheng, MD, MSc; Hui Cai, MD, PhD; et al Kai Gu, MD; Zhi Chen, MD, PhD; Wei Zheng, MD, PhD; Wei Lu, MD, PhD, December 9, 2009, JAMA. 2009;302(22):2437-2443. doi:10.1001/jama.2009.1783
ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング