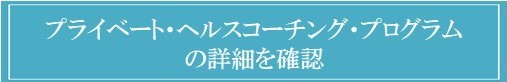гғҗгӮӨгӮӘеҖӢжҖ§гҒ§йЈҹгҒ№гҒҰгҖҒеҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҺгҖҒеҒҘеә·гҒЁе№ёгҒӣгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒӘйЈҹдәӢжі•гӮ’гӮігғјгғҒгғігӮ°гҒҷгӮӢгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲд»ЈиЎЁгҖҖе…¬иӘҚзөұеҗҲйЈҹйӨҠгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒпјҲCINHCпјүгҖҒе…¬иӘҚеӣҪйҡӣгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒпјҲCIHCпјүгҒ®жЈ®гҒЎгҒӣгҒ§гҒҷгҖӮ
еҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒӘйЈҹдәӢжі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒ
гғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјзҷ»йҢІиҖ…йҷҗе®ҡгҒ®гӮӯгғЈгғігғҡгғјгғіжғ…е ұзӯүгӮӮй…ҚдҝЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ”зҷ»йҢІгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮү
гӮӮгӮҢгҒӘгҒҸзөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰпјҲгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜж „йӨҠеӯҰпјүеҶҠеӯҗгҒҢз„Ўж–ҷгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ
зӣ®ж¬Ў
гҒ“гҒ®дәәгӮ’дҝЎй јгҒ—гҒҰд»Ій–“гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгӮҲгҒ„гҒ®гҒӢгҖҒгҒқгӮҢгҒЁгӮӮгҖҒгҒқгҒ®дҝЎй јгӮ’иЈҸеҲҮгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘдәәгҒӘгҒ®гҒӢгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«дјҡгҒЈгҒҹдәәгҒ§гӮӮгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢзӣҙгҒҗгҒ«гҒҜеҲӨж–ӯгҒҢгҒӨгҒӢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒҫгҒ—гҒҰгӮ„гҖҒгғҚгғғгғҲдёҠгҒ§зҹҘгӮҠеҗҲгҒЈгҒҹдәәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҲӨж–ӯгҒҢжӣҙгҒ«йӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮ“гҒӘгҒЁгҒҚгҖҒдҪ•гӮ’еҹәжә–гҒ«дҝЎй јгҒҷгӮӢгғ»гҒ—гҒӘгҒ„гӮ’жұәгӮҒгӮӢгҒЁй–“йҒ•гӮҸгҒӘгҒ„зўәзҺҮгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ®гғҡгғігӮ·гғ«гғҷгғӢгӮўеӨ§еӯҰгҒҢгҖҺгғҚгӮӨгғҒгғЈгғјгҖҸиӘҢгҒ«гҖҢи©•еҲӨгҒЁеҚ”иӘҝжҖ§гҖҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢи«–ж–ҮгӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®з ”究иҖ…гҒҹгҒЎгҒЁгҒ®гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјгҒ®еҶ…е®№гҒҢгғҡгғігӮ·гғ«гғҷгғӢгӮўеӨ§еӯҰгҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒеҲҶгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸиҲҲе‘іж·ұгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒе’ҢиЁіиҰҒзҙ„гҒ—гҒҰгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒиЈҸд»ҳгҒ‘гҒЁгҒӘгӮӢз ”з©¶и«–ж–ҮгҒҜгҖҒжңҖеҫҢгҒ«еҸӮиҖғж–ҮзҢ®гҒЁгҒ—гҒҰдёҖиҰ§гҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
й–“жҺҘдә’жҒөжҖ§

гҖҢжғ…гҒ‘гҒҜдәәгҒ®гҒҹгӮҒгҒӘгӮүгҒҡгҖҚ
гҒЁгҖҒгҒ„гҒҶи«әгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иӘ°гҒӢгҒ«е„ӘгҒ—гҒҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒқгҒ®иӘ°гҒӢгҒ®гҒҹгӮҒгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиҮӘеҲҶиҮӘиә«гҒ®гҒҹгӮҒпјҲеҲ©зӣҠпјүгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒӢгӮүгҖҒгҖҢй–“жҺҘдә’жҒөзҗҶи«–гҖҚгҒҜгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иӘ¬гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
д»–дәәгӮ’еҠ©гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иүҜгҒ„и©•еҲӨгӮ’еҫ—гҒҹдәәгҒҜ
第дёүиҖ…гҒӢгӮүе ұгӮҸгӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢ
гҒ§гӮӮгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒҹгҒЎгҒӢгӮүдҝЎй јгӮ’еҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҒӢгҒҜгҖҒгҒқгҒ®и©•еҲӨгҒ«гҒ©гӮҢгҒ гҒ‘еӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒҢеҗҢж„ҸгҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгҒ«дҫқгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғҡгғігӮ·гғ«гғҷгғӢгӮўеӨ§еӯҰз”ҹзү©еӯҰж•ҷжҺҲгӮёгғ§гӮ·гғҘгӮўгғ»Bгғ»гғ—гғӯгғҲгӮӯгғіеҚҡеЈ«гҒ®з ”究е®ӨгҒ«жүҖеұһгҒҷгӮӢгғқгӮ№гғҲеҚҡеЈ«иӘІзЁӢз ”з©¶е“ЎгҒ®гғҶгӮӨгғ©гғјгғ»Aгғ»гӮұгӮ·гғігӮёгғЈгғјеҚҡеЈ«гҒҜгҖҢй–“жҺҘдә’жҒөжҖ§гҖҚгӮ’ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иӘ¬жҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҢгҖҺгғһгғӘгҒҢгӮҸгҒҹгҒ—гҒ«е„ӘгҒ—гҒҸгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҒӢгӮүгҖҒгӮҸгҒҹгҒ—гӮӮгғһгғӘгҒ«е„ӘгҒ—гҒҸгҒҷгӮӢгҖӮгҖҸ
гҒЁгҖҒгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒ
гҖҺгӮҸгҒҹгҒ—гҒҢеҘҪгҒҫгҒ—гҒ„еҚ°иұЎгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮёгғЈгӮ·гғҘгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгғһгғӘгҒҜе„ӘгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҒ гҒӢгӮүгҖҒгӮҸгҒҹгҒ—гҒҜгғһгғӘгҒ«е„ӘгҒ—гҒҸгҒҷгӮӢгҖӮгҖҸгҒЁгҖҒгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҖҚ
11жңҲгҒ«гҒ”зөҗе©ҡгӮ’е ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҹй«ҳз•‘е……еёҢгҒ•гӮ“гҒЁеІЎз”°е°Ҷз”ҹгҒ•гӮ“гҒҢгҖҒгғҶгғ¬гғ“гҒ®гғҜгӮӨгғүгӮ·гғ§гғјгҒ®гӮӨгғігӮҝгғ“гғҘгғјгҒ§гҖҒгҖҢеӨҡгҒҸгҒ®е…ұйҖҡгҒ®еҸӢдәәгҒҢй«ҳз•‘гҒ•гӮ“гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒЁгҒҰгӮӮиүҜгҒҸиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒй«ҳз•‘гҒ•гӮ“гҒ«гҒҜдјҡгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ‘гӮҢгҒ©гӮӮгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮиүҜгҒ„еҚ°иұЎгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖҚгҒЁеІЎз”°гҒ•гӮ“гҒҢгҒҠгҒЈгҒ—гӮғгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒӯгҖӮй–“жҺҘдә’жҒөжҖ§гҒ§гҒҷгҒӯпјҲ笑пјү
гҒҠдә’гҒ„гҒ®иЎҢзӮәгӮ’гҒ©гҒҶи©•дҫЎгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢ

гҖҢеҚ”иӘҝжҖ§гҖҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзҗҶи«–зҡ„з ”з©¶гҒ®еҚ”еғҚгғҒгғјгғ гӮ’зҺҮгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгғҡгғігӮ·гғ«гғҷгғӢгӮўеӨ§еӯҰз”ҹзү©еӯҰж•ҷжҺҲгӮёгғ§гӮ·гғҘгӮўгғ»Bгғ»гғ—гғӯгғҲгӮӯгғіеҚҡеЈ«гҒ®з ”究е®ӨгҒ«жүҖеұһгҒҷгӮӢгғқгӮ№гғҲеҚҡеЈ«иӘІзЁӢз ”з©¶е“ЎгҒ®е·қеӢқзңҹзҗҶеҚҡеЈ«гҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иӘ¬жҳҺгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®е…ёеһӢзҡ„гҒӘзҗҶи«–гғўгғҮгғ«гҒ§гҒҜгҖҒ
пј‘гҒӨгҒ®иЎҢеӢ•гҒҢгҒқгҒ®дәәгҒ®и©•еҲӨгӮ’жұәе®ҡгҒҷгӮӢгҒЁжғіе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢиӘ°гҒӢгҒ®и©•еҲӨгӮ’жұәгӮҒгӮӢйҒҺзЁӢгҒ«гҒҜгҖҒ
гӮӮгҒЈгҒЁеҫ®еҰҷгҒӘгғӢгғҘгӮўгғігӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒеӨ§жҠөгҖҒгҒӮгӮӢдәәгҒҢгҒЁгҒЈгҒҹгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®иЎҢеӢ•гӮ’иҰӢгҒҰгҖҒ
гҒқгӮҢгҒҢдё»гҒ«иүҜгҒ„иЎҢеӢ•гҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒӢжӮӘгҒ„иЎҢеӢ•гҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгӮ’иҖғгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮгҖҚ
гғ—гғӯгғҲгӮӯгғіеҚҡеЈ«гҒЁе…ұгҒ«гҖҢеҚ”иӘҝжҖ§гҖҚгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзҗҶи«–зҡ„з ”з©¶гҒ®еҚ”еғҚгғҒгғјгғ гӮ’зҺҮгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгғ—гғӘгғігӮ№гғҲгғіеӨ§еӯҰгҒ®гӮігғӘгғјгғҠгғ»гӮҝгғ«гғӢгӮҝеҚҡеЈ«гҒ®з ”究е®ӨгҒ«жүҖеұһгҒҷгӮӢеҚҡеЈ«иӘІзЁӢгҒ®еӯҰз”ҹгӮ»гғҗгӮ№гғҒгғЈгғігғ»гғҹгӮ·гӮ§гғ«пјқгғһгӮҝж°ҸгҒҜгҖҒгҖҢи©•еҲӨгҒҜгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘиЎҢеӢ•гҒ®йӣҶзҙ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҚҳзҙ”гҒӘиҖғгҒҲгҒ«гӮӮз–‘е•ҸгӮ’жҠұгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
д»Ҡж—ҘгҒ®дё–з•ҢгҖҒзү№гҒ«гӮҪгғјгӮ·гғЈгғ«гғЎгғҮгӮЈгӮўгӮ’з”ЁгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒгҒӮгӮӢдәәгҒ®иЎҢзӮәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒІгҒЁгҒӨгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸеӨҡгҒҸгҒ®жғ…е ұгҒҢе…ҘжүӢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ“гҒ§гҖҒгғҹгӮ·гӮ§гғ«пјқгғһгӮҝж°ҸгҒҜгҖҒжғ…е ұиұҠеҜҢгҒӘз’°еўғдёӢгҒ§гҖҒдәәгҒҜгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«д»–дәәгӮ’и©•дҫЎгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгӮ’жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҖқгҒ„гҒӨгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮІгғјгғ зҗҶи«–гғўгғҮгғ«гӮ’з”ЁгҒ„гҒҹз ”з©¶
д»ҠеӣһгҒ®з ”究гҒ§з”ЁгҒ„гҒҹгӮІгғјгғ зҗҶи«–гғўгғҮгғ«гҒҜгҖҒгҖҢеӣҡдәәгҒ®гӮёгғ¬гғігғһгҖҚгҒ®з°Ўжҳ“зүҲгҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгӮӢгҖҢгғҜгғігӮ·гғ§гғғгғҲеҜ„д»ҳгӮІгғјгғ пјҲone-shot donation gameпјүгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ
еӣҡдәәгҒ®гӮёгғ¬гғігғһ
гҒЎгҒӘгҒҝгҒ«еӣҡдәәгҒ®гӮёгғ¬гғігғһгҒЁгҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҠ¶жіҒгҒ§жұәж–ӯгҒҷгӮӢгӮІгғјгғ гҒ§гҒҷгҖӮ
пј’дәәгҒ®еӣҡдәәпјҲAгҒЁBпјүгҒҢйҖ®жҚ•гҒ•гӮҢгҖҒеҲҘгҖ…гҒ®йғЁеұӢгҒ§е°Ӣе•ҸгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮйҡ”йӣўгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒҠдә’гҒ„гҒ®еӢ•еҗ‘гҒҜеҲҶгҒӢгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒқгҒ®жҷӮгҖҒиҮӘзҷҪгҒҷгӮӢгҒӢй»ҷз§ҳгҒҷгӮӢгҒӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҲ‘гҒҢжұәгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

- дәҢдәәгҒЁгӮӮй»ҷз§ҳгҒҷгӮӢгҒЁжҮІеҪ№пј‘е№ҙ
- дәҢдәәгҒЁгӮӮиҮӘзҷҪгҒҷгӮӢгҒЁжҮІеҪ№пј’е№ҙ
- гҒІгҒЁгӮҠгҒ гҒ‘иҮӘзҷҪпјҸй»ҷз§ҳгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒиҮӘзҷҪгҒ—гҒҹж–№гҒҜйҮҲж”ҫгҖҒй»ҷз§ҳгҒ—гҒҹж–№гҒҜжҮІеҪ№пј“е№ҙ
гҒ•гҒҰгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҜиҮӘзҷҪгҒ—гҒҹж–№гҒҢеҫ—гҒӢй»ҷз§ҳгҒ—гҒҹж–№гҒҢеҫ—гҒӢгғ»гғ»гғ»
гҒ“гҒ®е ҙеҗҲгҖҒдәҢдәәгҒЁгӮӮй»ҷз§ҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжңҖйҒ©и§ЈгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ§гӮӮгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢй»ҷз§ҳгҒ—гҒҰгӮӮзӣёжүӢгҒҢиҮӘзҷҪгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒ гҒ‘гҒҢжҮІеҪ№пј“е№ҙгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзӣёжүӢгҒ®еӢ•еҗ‘гҒҢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„дёӯгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҜзӣёжүӢгӮ’дҝЎй јгҒ—гҒҰй»ҷз§ҳгӮ’з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖҒгҒқгӮҢгҒЁгӮӮе…ҲгҒ«иЈҸеҲҮгҒЈгҒҰиҮӘеҲҶгҒ гҒ‘йҮҲж”ҫгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӢҷгҒ„гҒҫгҒҷгҒӢпјҹ
гҒ“гӮҢгҒҢеӣҡдәәгҒ®гӮёгғ¬гғігғһгҒ§гҒҷгҖӮ
гғҜгғігӮ·гғ§гғғгғҲеҜ„д»ҳгӮІгғјгғ

гғҜгғігӮ·гғ§гғғгғҲеҜ„д»ҳгӮІгғјгғ гҒ§гҒҜгҖҒеҗ„гғ—гғ¬гӮӨгғӨгғјгҒҜгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®гғ‘гғјгғҲгғҠгғјгӮ’еҠ©гҒ‘гӮӢгҒӢиЈҸеҲҮгӮӢгҒӢгӮ’йҒёгҒігҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®жҷӮгҖҒгғ‘гғјгғҲгғҠгғјгҒҢд»–гҒ®гғ—гғ¬гӮӨгғӨгғјгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиЎҢеӢ•гӮ’гҒЁгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒд»–гҒ®гғ—гғ¬гӮӨгғӨгғјгӮ’еҠ©гҒ‘гҒҹгҒӢиЈҸеҲҮгҒЈгҒҹгҒӢгӮ’гҒӮгҒӘгҒҹгҒҜиҰіеҜҹгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒгғ‘гғјгғҲгғҠгғјгӮ’еҠ©гҒ‘гӮӢгҒӢеҠ©гҒ‘гҒӘгҒ„гҒӢгҒ®еҲӨж–ӯгҒ«еҸҚжҳ гҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®гғ‘гғјгғҲгғҠгғјгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮеҗҢгҒҳгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢд»–гҒ®гғ—гғ¬гғјгғӨгғјгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиЎҢеӢ•гӮ’гҒЁгҒЈгҒҹгҒӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгӮ’еҠ©гҒ‘гӮӢгҒӢиЈҸеҲҮгӮӢгҒӢгӮ’жұәгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ©гҒ®жҲҰз•ҘгӮҲгӮҠгӮӮжңүеҠ№гҒӘжҲҰз•Ҙ
гғҜгғігӮ·гғ§гғғгғҲеҜ„д»ҳгӮІгғјгғ гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҖҒгғ’гғҲгҒҢгҖҒгҒӮгӮӢдәәгҒ®иЎҢзӮәгӮ’гҒ„гҒҸгҒӨиҰӢгҒҰгҖҒгҒқгҒ®гҒҶгҒЎгҒ®гҒ„гҒҸгҒӨгҒ®жӮӘгҒ„иЎҢзӮәгӮ’иЁұгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒгҒқгҒ®дәәгҒЁгҒ®еҚ”иӘҝй–ўдҝӮгӮ’з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢдёҠгҒ§жңҖйҒ©гҒӢгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжңүзӣҠгҒӢгӮ’гҖҒз ”з©¶гғҒгғјгғ гҒҜж•°еӯҰзҡ„гғўгғҮгғӘгғігӮ°гӮ’йҖҡгҒ—гҒҰзӨәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®зөҗжһңгҒ®жңҖйҒ©и§ЈпјҲгҒӮгҒӘгҒҹгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮгғ‘гғјгғҲгғҠгғјгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгӮӮжңүзӣҠгҒӘйҒёжҠһпјүгҒҜгҖҒ
д»–гҒ®гғ—гғ¬гӮӨгғӨгғјгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгғ‘гғјгғҲгғҠгғјгҒ®иЎҢеӢ•гӮ’пј’еӣһиҰіеҜҹгҒ—гҖҒ
гҒқгҒ®гҒҶгҒЎгҒ®е°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮпј‘еӣһгҒҢиүҜгҒ„гҒЁжҖқгҒҲгӮӢиЎҢеӢ•гҒ гҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒ
гғ‘гғјгғҲгғҠгғјгӮ’еҠ©гҒ‘гҖҒгҒқгҒҶгҒ§гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜеҠ©гҒ‘гҒӘгҒ„
гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®ж–№жі•гӮ’еҪјгӮүгҒҜгҖҢпј’еӣһиҰӢгҒҰпј‘еӣһиЁұгҒҷпјҲlook twice, forgive onceпјүгҖҚж–№жі•гҒЁе‘јгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е·қеӢқеҚҡеЈ«гҒҜгҖҒгҖҢ2еӣһиҰӢгҒҰ1еӣһиЁұгҒҷгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҲҰз•ҘгҒҢгҖҒд»–гҒ®жҲҰз•ҘгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгҖҢеёёгҒ«еҚ”еҠӣгҒҷгӮӢгҖҚгҒЁгҒӢгҖҢеёёгҒ«иЈҸеҲҮгӮӢгҖҚгҒЁгҒӢгҖҒгҖҢгӮ„гӮҠеҸ–гӮҠгӮ’2еӣһд»ҘдёҠиҰӢгӮӢгҖҚгҒЁгҒӢгҖҒгҖҢжӮӘгҒ„иЎҢеӢ•гӮ’иЁұгҒҷеүІеҗҲгӮ’еӨүгҒҲгӮӢгҖҚгӮҲгӮҠгӮӮеёёгҒ«еҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«е…ұи‘—иҖ…е…Ёе“ЎгҒҢй©ҡгҒ„гҒҹгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ—гғӯгғҲгӮӯгғіеҚҡеЈ«гҒҜгҖҒд»ҠеӣһгҒ®ж–°гҒ—гҒ„з ”з©¶зөҗжһңгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢзӨҫдјҡгҒ®гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘдәәгҖ…гҒҢз•°гҒӘгӮӢеҲӨж–ӯеҹәжә–гҒ«еҫ“гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒ
гҖҺпј’еӣһгҒҝгҒҰпј‘еӣһиЁұгҒҷгҖҸгҒЁгҒ„гҒҶж–№жі•гҒҜгҖҒ
еҚ”иӘҝжҖ§гӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒҷгҒ®гҒ«еҚҒеҲҶгҒӘеҗҢж„ҸгӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖҚ
еҷӮи©ұгӮҲгӮҠгӮӮзӨҫдјҡиҰҸзҜ„гӮҲгӮҠгӮӮжңүеҠ№

гғ—гғӯгғҲгӮӯгғіеҚҡеЈ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гҖҢ2еӣһиҰӢгҒҰ1еӣһиЁұгҒҷгҖҚж–№жі•гӮ’з”ЁгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҷӮи©ұгӮ„гҖҒгғ«гғјгғ«йҒөе®ҲгӮ’еј·еҲ¶гҒҷгӮӢе…¬зҡ„ж©ҹй–ўгҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮеҚ”иӘҝжҖ§гҒҜз¶ӯжҢҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁд»ҳгҒ‘еҠ гҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒжұҡиҒ·гӮ„дёҚжӯЈиЎҢзӮәгҒҢйҮҺж”ҫгҒ—гҒ«гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзӨҫдјҡгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҖҢпј’еӣһгҒҝгҒҰпј‘еӣһиЁұгҒҷгҖҚгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒҠдә’гҒ„гҒ«еҲ©зӣҠгҒ®гҒӮгӮӢдҝЎй јгҒ—еҗҲгҒҲгӮӢй–ўдҝӮгӮ’зҜүгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жғ…е ұйҮҸгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„

гғ—гғӯгғҲгӮӯгғіеҚҡеЈ«гҒҜгҖҒгғқгӮ№гғҲеҚҡеЈ«иӘІзЁӢз ”з©¶е“ЎгҒ®гғҶгӮӨгғ©гғјгғ»Aгғ»гӮұгӮ·гғігӮёгғЈгғјеҚҡеЈ«гҒЁе·қеӢқеҚҡеЈ«гҒЁе…ұеҗҢгҒ—гҖҒеҚ”иӘҝжҖ§гӮ’еҚҒеҲҶгҒ«з¶ӯжҢҒгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгҒ©гӮҢгҒ гҒ‘гҒ®еҷӮи©ұгҒҢеҝ…иҰҒгҒӢгӮ’иЁҲз®—гҒ—гҒҹи«–ж–ҮгӮ’д»ҘеүҚзҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮҝгғ«гғӢгӮҝеҚҡеЈ«гҒҜгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮӮиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгӮ„гӮҠеҸ–гӮҠгӮ’2еӣһд»ҘдёҠиҰӢгҒҰгӮӮеҲӨж–ӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжңүж„ҸгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒ
гҒҠгҒқгӮүгҒҸжңҖгӮӮй©ҡгҒҸгҒ№гҒҚгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖҚгҖҢжғ…е ұгҒҜи«ёеҲғгҒ®еүЈгҒ§гҒҷгҖӮ
жғ…е ұгҒ«иҮӘз”ұгҒ«гӮўгӮҜгӮ»гӮ№гҒ§гҒҚгӮӢе ҙеҗҲгҒ§гӮӮгҖҒ
гғ’гғҲгҒҜгҒқгҒ®гҒҷгҒ№гҒҰгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒҜйҖІеҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгҖҚ
гҒ“гҒ®зҷәиҰӢгҒ®гҖҒгӮ·гғігғ—гғ«гҒ•гҒЁе …зүўжҖ§гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®иЎҢеӢ•жҲҰз•ҘгҒҢдәәй–“зӨҫдјҡгҒ«еҸӨгҒҸгҒӢгӮүгҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҖҒгғҹгӮ·гӮ§гғ«=гғһгӮҝж°ҸгҒҜжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒӢгӮүгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№

иҒһгҒ„гҒҹи©ұгӮҲгӮҠгӮӮиҰӢгҒҹдәӢе®ҹ
гҖҢзҷҫиҒһгҒҜдёҖиҰӢгҒ«гҒ—гҒӢгҒҡгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶи«әгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӯгҖӮ
йҒҺеҺ»гҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹеӨҡгҒҸгҒ®зӨҫдјҡеҝғзҗҶеӯҰгҒ®з ”究гҒҢгҒқгӮҢгӮ’иЁјжҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒд»ҠеӣһгҒ®з ”究гӮӮгҖҒгҒ©гҒ“гҒӢгӮүгҒӢиҖігҒ«гҒҷгӮӢи©•еҲӨгӮ„еҷӮи©ұгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«зӣ®гҒ«гҒ—гҒҹиЎҢзӮәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгғ’гғҲгҒҜгҒҠдә’гҒ„гҒ®й–ўдҝӮгӮ’и©•дҫЎгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЈҸд»ҳгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ»гӮ«гғігғүгғҒгғЈгғігӮ№гҒҢйҮҚиҰҒ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒиӘ°гҒӢгҒ®иЎҢгҒ„гҒҜгҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮпј’гҒӨиҰӢгҒҰгҒӢгӮүеҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҖӮ
дҫӢгҒҲгҖҒиӘ°гҒӢгҒ®жӮӘгҒ„иЎҢгҒ„гӮ’1еӣһгҖҒзӣ®гҒ«гҒ—гҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒзӣҙгҒҗгҒ«гҒқгҒ®дәәгҒҢжӮӘгҒ„дәәгҒ гҒЁеҲҮгӮҠжҚЁгҒҰгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮӮгҒ—ж¬ЎгҒ®иЎҢгҒ„гҒҢе–„гҒ„иЎҢгҒ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгҒқгҒ®дәәгҒЁгҒ®еҸӢжғ…гӮ„дәәй–“й–ўдҝӮгҒӘгҒ©гҒҜз¶ҷз¶ҡгҒ•гҒӣгҒҰгҒҠгҒ„гҒҹж–№гҒҢгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжңүзӣҠгҒ гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’гҒ“гҒ®з ”究гҒҜзӨәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ»гӮ«гғігғүгғҒгғЈгғігӮ№гӮ’зӣёжүӢгҒ«дёҺгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒзҝ»гҒЈгҒҰгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹиҮӘиә«гҒ«гӮӮгӮ»гӮ«гғігғүгғҒгғЈгғігӮ№гҒҢдёҺгҒҲгӮүгӮҢгӮӢж©ҹдјҡгҒҢеў—гҒҲгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
еҚҠеҲҶиЁұгҒҷеҜӣе®№гҒ•
гҒқгӮҢгҒ«гҖҒпј’еӣһгҒ«пј‘еӣһгҒ®йҒҺгҒЎгӮ’иЁұгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶеҜӣе®№гҒ•гӮ’гӮӮгҒӨгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гӮӮжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®зҘһеӯҰиҖ…гҒ®гғҲгғјгғһгӮ№гғ»гғ•гғ©гғјгҒҜгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иЁҖгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
Keep thy eyes wide open before Marriage;
Thomas Fuller
and half shut afterward.
зөҗе©ҡгҒҷгӮӢеүҚгҒ«гҒҜзӣ®гӮ’еӨ§гҒҚгҒҸиҰӢй–ӢгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ•гҒ„гҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰзөҗе©ҡеҫҢгҒҜеҚҠеҲҶй–үгҒҳгҒҰгҒ„гҒӘгҒ•гҒ„
еӨ«е©Ұй–ўдҝӮгҒ«йҷҗгӮүгҒҡгҖҒгҒҠдә’гҒ„гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжңүзӣҠгҒӘй–ўдҝӮгӮ’еҶҶжәҖгҒ«дҝқгҒӨгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒпј’еӣһгҒ«пј‘еӣһиЁұгҒҷгҖҒеҚҠеҲҶзӣ®гӮ’гҒӨгӮҖгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§дәӢгҒӘгӮ“гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӯгҒҮгҖӮ
пј’еӣһйҖЈз¶ҡгҒӘгӮүеҲҮгӮӢ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҘҪгҒҫгҒ—гҒҸгҒӘгҒ„иЎҢзӮәгҒҢпј’еӣһйҖЈз¶ҡгҒ—гҒҰзӣ®ж’ғгҒ•гӮҢгҒҹгҒӘгӮүгҖҒиәҠиәҮгҒӘгҒҸгҒқгҒ®й–ўдҝӮгӮ’ж–ӯгҒЈгҒҰгӮӮиүҜгҒ„гҖҒж–ӯгҒӨж–№гҒҢгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®еҲ©зӣҠгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ“гҒ®з ”究гҒҜзӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зӣёжүӢгҒ®иЎҢзӮәгӮ’иЁұгҒ—з¶ҡгҒ‘гҒҰгӮӮгҖҒпј’еӣһиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁд»ҘдёҠгҒ®еҠ№жһңгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒDVгӮ„еҜ„з”ҹгҒ•гӮҢгӮӢй–ўдҝӮгҒ«йҷҘгӮүгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒй–ўдҝӮгӮ’еҲҮгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӮгҒӘгҒҹгӮ’еӮ·гҒӨгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘиЎҢзӮәгҒҢйҖЈз¶ҡгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘй–ўдҝӮгҒЁгҒҜж—©гҖ…гҒ«з·ҡгӮ’еј•гҒҸгҖҒдәәй–“й–ўдҝӮгҒ®гғҗгӮҰгғігғҖгғӘгғјгӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
е…¬иӘҚгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒҜгҖҒйЈҹдәӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгӮ’еҸ–гӮҠе·»гҒҸж§ҳгҖ…гҒӘгҒ“гҒЁпјҲз’°еўғгҖҒд»•дәӢгҖҒ家ж—ҸгҖҒдәәй–“й–ўдҝӮгҒӘгҒ©пјүгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰгҖҒгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«еҸҚжҳ гҒ•гҒӣгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢгҖҒгҒӘгӮҠгҒҹгҒ„гҒӮгҒӘгҒҹгҒ«гҒӘгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгӮігғјгғҒгғігӮ°гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒ—гҒҠгҒІгҒЁгӮҠгҒ§еҸ–гӮҠзө„гӮҖгҒ“гҒЁгҒ«дёҚе®үгӮ„йӣЈгҒ—гҒ•гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгӮүгҖҒгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒЁгҖҒдёҖеәҰгҖҒи©ұгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹ
гғ—гғ©гӮӨгғҷгғјгғҲгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°гғ»гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
гҒҠж°—и»ҪгҒ«гҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
еҲқеӣһзӣёи«ҮгӮ’з„Ўж–ҷгҒ§гҒҠеҸ—гҒ‘гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒ®гғһгӮӨгғігғүгғ»гғңгғҮгӮЈгғ»гғЎгғҮгӮЈгӮ·гғіи¬ӣеә§гӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§еӯҰгҒігҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹгӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢйЈҹгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҒ”иҮӘиә«гҒ®дё»жІ»еҢ»пјҲгӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјпјүгҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҝ…иҰҒгҒӘзҹҘиӯҳгҒЁгӮ№гӮӯгғ«гӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж–°еӯҰжңҹгҒҜгҖҒжҜҺе№ҙ3жңҲгҒЁ9жңҲгҒ§гҒҷгҖӮи¬ӣеә§гҒ§гҒҠдјҡгҒ„гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§еҒҘеә·гҒЁе№ёгҒӣгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢ
гғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјгҒ®гҒ”зҷ»йҢІгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮү
зөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰпјҲгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜж „йӨҠеӯҰпјүеҶҠеӯҗгҒҢз„Ўж–ҷгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ
еҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡ
- вҖңThe evolution of private reputations in information-abundant landscapes.вҖқ, Michel-Mata, S., Kawakatsu, M., Sartini, J. et al. Nature 634, 883вҖ“889 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07977-x
- вҖңA method of вҖҳlook twice, forgive onceвҖҷ can sustain social cooperationвҖқ, Erica Moser, September 25, 2024, University of Pennsylvania
гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲ – гғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°