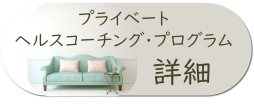バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。
心と体をつなぐホリスティックな食事法について、
ニュースレター登録者限定のキャンペーン情報等も配信しています。
ご登録は、こちらから
もれなく統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます
目次
マタニティブルーは世界共通
多くの人にとって赤ちゃんの誕生は人生の幸せの1ページとなる出来事です。
でも、出産したら諸々が終わるわけではなく、出産はさらなる諸々の始まりです。そして、その結果、世界の女性に共通して出産後うつが起こっています。
ハーバード大学病院のステファニー・コリヤー医師によれば、妊婦の5人にひとりは、妊娠中あるいは出産後に不安障害になっているとのことです。
日本では、コロナウイルス感染症の流行以来、約29%の母親が産後うつを経験していると報告されています。4人に一人以上です。
今回は、いわゆる「マタニティブルー」と呼ばれる、出産に関係して起こる不安症やうつ症状を出産の「前」と「後」の2回に分けて、それぞれの予防法と起きてしまった時の対処法についてお伝えします。
2回目の今回は、出産の「後」、出産後のマタニティブルーを予防する方法、そして、万が一、産後に大きな気分の落ち込みに気づいた時、適切に対処する方法をお伝えします。
少しでも気分の落ち込みが現れたら、すぐに対応することが薬に頼らずに過ごすためにとても重要です。
なお、裏付けとなる研究論文は最後に参考文献として一覧にしています。
産後うつが起こりやすい時期

産後うつ病は、出産後に女性に起こるうつ病の一種です。(最近では男性にも産後うつがあることを報告している研究もありますが・・)出産後1年以内であればいつでも発症する可能性があります。
最も多い時期は、産後3週間~6週間以内です。
1997年~1999年におけるイギリスの妊産婦の死亡原因について調査した研究は、妊産婦の死亡の約28%は自殺であり、特に、産後42日間に自殺するリスクが最も高いことを報告しています。
もちろん、出産後にうつを経験しない女性もいます。でも、大抵のお母さんは、出産後の数週間の怒涛の日々で疲れ切ってしまいます。
この時期に母親がうつになると、生まれたばかりの赤ちゃんの世話を適切にすることが難しくなり、深刻な事態に陥ることもあります。
産後うつの症状
産後うつ病の症状には次のようなものがあります。
- 悲しみ
- 絶望感
- 自分には価値がないと感じる
- 何をやっても十分ではないと感じる
- 活動への興味の喪失
- 涙もろさ
- 不安定な気分
- 睡眠障害
- 食欲不振または食習慣の変化
- 集中力の低下
- 自傷行為や自殺願望
- など
京都大学と大阪大学の 0~4歳児の母親で、身体疾患や精神疾患のない 339 名(平均年齢34.7歳)を対象に、育児ストレスインデックス(PSI)を用いて育児ストレスを評価した研究では、睡眠の質、消化器の機能障害、身体的抑うつ、女性ホルモンの分泌機能低下などが育児ストレスと関連していることが示めされています。
産後うつ病が起こる原因

なぜ産後にうつ病が起こるのかの正確な原因は不明です。
ただ、身体的、精神的、社会的な要因の複雑な組み合わせによって発症すると考えられています。
1. 引き金となる要因
引き金には、次のような要因が関係していると考えられています。
- 妊娠中や出産時に起こるホルモンの変化
- 新生児との生活への適応ストレス
- 社会的支援の欠如
- 精神疾患の病歴
- など
2. 自ら支援を遠ざけてしまう
2024年7月に開催された第21回日本うつ病学会にて、筑波大学精神医学の根本清貴准教授は、産後うつ発症の背景にある要因を次のように解説しています。
「ホルモンバランスの変化に加え、
世間からのプレッシャー、パートナーとの関係の変化で
孤独を感じ、自ら支援を遠ざけてしまうことで
さらに孤立を深めてしまうことがある」
3. 腸内細菌の顔ぶれ変化
また、腸内細菌の顔ぶれと産後うつの症状と回復力に関連があることが京都大学と大阪大学による研究によって発見され報告されています。
腸内細菌には、サイコバイオティクスと呼ばれる、あなたの精神状態や性格にまで影響する共生細菌がいます。腸内細菌の顔ぶれの変化は、確実にあなたの心の状態に影響しています。
サイコバイオティクスの詳しい働きについては『サイコバイオティクス』をご確認ください。
女性ホルモンと産後うつ病との関係

ホルモンの変化についていえば、妊娠中は女性ホルモンのエストロゲンとプロゲステロンの濃度が非常に高い状態が続きます。
プロゲステロンは一般的に母になるための女性ホルモンです。子宮内膜を厚くして赤ちゃんのゆりかごを子宮内に作ることはよく知られています。
出産と共に、プロゲステロンとエストロゲンの濃度は急激に減少します。
1. プロゲステロンの低下
プロゲステロンには、抗うつ作用があります。気分の安定にもかかわっています。
出産後にプロゲステロンの濃度が低下することで、気分が落ち込み、産後うつ病が発症するのではないかと考えられています。
また、プロゲステロンは、睡眠と覚醒のサイクルにも関与しています。
出産後のプロゲステロンの減少や、授乳による睡眠パターンの乱れなど、いくつかの要因が重なることで、寝不足になり、疲労感やイライラなどが起こると考えられています。
2. エストロゲンの低下
エストロゲンは、抗うつ作用のある神経伝達物質セロトニンの働きを助けています。
エストロゲンが減少すると、セロトニントランスポーターと呼ばれる、セロトニンの脳内への再取り込みを阻害するタンパク質が増加します。
つまり、エストロゲンの減少によってセロトニン不足が起こることで、うつ症状が起こりやすくなると考えられています。
3. ホルモンの減少だけが原因ではない
このように、妊娠前の状態に戻ろうとするホルモンの変化に心と体は翻弄されます。
しかし、出産後にすべての女性のエストロゲンとプロゲステロン濃度は減少しますが、すべての女性に産後うつが現われるわけではありません。
つまり、プロゲステロンとエストロゲンの減少だけが産後うつ病の原因ではないのです。
産後うつ病は、前述したとおり、身体的、精神的、社会的な要因の複雑な組み合わせによって起こります。
腸内細菌と産後うつの症状

京都大学と大阪大学によって実施された2つの調査から次のことが判明しました。
1. 育児ストレスで腸内細菌の多様性が低下
0~4歳児の母親で、身体疾患や精神疾患のない 339 名(平均年齢34.7歳)を対象に、育児ストレスインデックス(PSI)を用いて育児ストレス(親に対するストレスと赤ちゃんに対するストレスの両方)を評価した研究では、低リスク群に比べて高リスク群の腸内細菌の顔ぶれの多様性が低いことが示されました。
育児ストレスによって腸内細菌の多様性が低下するのか、腸内細菌の多様性が低いから育児ストレスを強く感じてしまうのか、どちらが先かはこの研究からは分かりません。
しかし、次の2つめの研究が因果関係があることを明らかにしています。
2. エクオールで心の回復力が低下
産後3~6カ月未満の初産の母親27名(平均年齢33.6歳)を対象に調査が行われ、次の関係性が発見されました。
- 腸内細菌の多様性が大きいと、心の回復力(心的レジリエンス)が高くなる
- 短鎖脂肪酸の産生や抗炎症作用をもつ菌は、身体運動機能、心的レジリエンス、オキシトシンの量と関係している
- エストロゲン様作用を持つエクオールを産生する菌が多いほど、心的レジリエンスが低くなる
- うつ病患者では、エクオール産生菌が増加している
エストロゲン自体はうつ予防と関係しているのに、エストロゲンと類似した働きをすると考えられてきたエクオールを造る菌が腸内で増えると、心の回復力が低下するという発見は、興味深いですね。
エクオールのサプリメントを美容のために飲んでいる女性は要注意です。
まとめると、次の状態を腸内に作ることで、産後うつを予防できる可能性があると考えられます。
- 腸内細菌の顔ぶれを多様に保つこと
- 短鎖脂肪酸を作る菌を増やすこと
- エクオール過剰の状態を避けること
これら3つの状態を腸内に造る方法を、後半でお伝えします。
どんな病気もそうですが、産後うつ病も早く対処すればするほど、早く回復します。
社会的なプレッシャーと夫婦間の関係の変化

1. 社会との孤立
仕事をもって働いている女性は、産休を取ることで、社会的なつながりの喪失感や孤立感を覚えることがあります。
取り残されている感じ、疎外感なども含まれます。
また、新たな環境での周囲の人々との関係にストレスを感じることもあります。
2. 良い母の呪い
更に、周囲の考える「良い母親像」や「母親に求める期待」、あなた自身がもつ「良い母親は~でなければならない」という思いに囚われ追い詰められてしまうこともあります。
3. 夫婦間の認識のズレ
また、夫婦の間で、子育てへの役割の認識にズレが生じていることも多々あります。
例えば、母親は、もっと家事を助けて欲しいと考えているのに、父親は家族のためにと仕事をがんばろうと帰宅が遅くなるなど・・。
「こんなこと言わなくても分かっているだろう/分かって当然」、「大切に思ってくれているのなら、察せられるはず」はあなたの幻想・妄想です。
あなたが初めて母親になったのと同じように、パートナーも初めて親になったのです。子供のいる生活もお互い初めてのこと。ひとつひとつ言葉にして伝えていくことが大切です。
言わなくても分かるはずのことを言う努力です。
4. 母性の呪い
「母親なら自分の子供を自然に愛せるもの」などといった母性に関する社会からの悪意なく発せられた無配慮な言葉が、母親を追い詰めてしまうことがあります。
特に、産婦人科の先生や助産師さんや保健所のスタッフなど、本来、あなたのよき理解者であるはずの人たちから、そうした言葉が発せられることによって、支援を受けることを拒否するきっかけになることもあります。
産後うつ病の治療

産後うつ病の治療に用いられる薬には、次のようないくつかの種類があります。ひとりひとりの症状や病歴などに沿って適切な薬が選択されます。
統合食養学のヘルスコーチとしては、薬に直ぐに頼ることはお勧めできませんが、情報としてお伝えしておきます。
なお、授乳中の女性は、これらの薬の赤ちゃんへの安全性について主治医に必ず確認してくださいね。
1. 選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)
SSRIは、産後うつ病に最も一般的に処方される抗うつ剤です。
産後うつ病に使用されるSSRIには、フルオキセチン(プロザック)、セルトラリン(ゾロフト)、パロキセチン(パキシル)などがあります。
2. セロトニン-ノルエピネフリン再取り込み阻害薬(SNRI)
産後うつ病の治療に用いられるもうひとつの抗うつ剤です。
ベンラファキシン(エフェクサー)やデスベンラファキシン(プリスティク)などがあります。
3. 非定型抗うつ薬
ブプロピオン(ウェルブトリン)やラモトリギン(ラミクタール)などの気分安定剤も産後うつ病の治療に使用されることがあります。
出産後に無気力になりそうになったらやること
投薬には一定の効果があると考えられています。
しかし、こうした心のお薬には好ましくない副作用が伴ない、また離脱することが難しいことから、投薬のみが唯一の治療法ではないことも知っておいてほしいです。
1. 「助けてほしい」と言う

家族や友人に助けを求めることを恐れないでください。
最近は高齢女性の中には仕事をもっていたり、ご自身の趣味の活動に熱心な人も多いですが、忙しくしている義母だって祖母だって、孫のためなら時間を割いて協力してくれるかもしれません。お料理やお掃除・洗濯、赤ちゃんの世話や買い物だって、お願いしたっていいんですよ。
ダメならそう言うはずです。大丈夫だから引き受けてくれるんですから、お願いする前から諦めず「ダメもと」で言ってみる価値はあります。
それで何か小言を言われたとしても「右から左へスルー」する鈍感さもあなたと赤ちゃんを守るために重要です。
また、「産後ドゥーラ」と呼ばれる産後をアシストしてくれる人もいます。赤ちゃんが生まれた後のあらゆる面のサポートをしてくれる人です。地元の自治体に相談したり、ネットで検索してみてはいかがでしょうか。
2. サポートグループに参加する

新生児との新しい生活に困惑しているのはあなた一人ではありません。世界中の多くの女性があなたと同じような経験をしています。
あなたはひとりではありません。
他のママたちとつながることも検討してください。似た状況にいるママたちや先輩ママたちからサポートやアドバイスを得られるだけでなく、お互いに励ましあえる友だちを見つけるきっかけになるかもしれません。
オンライン・コミュニティや地元のコミュニティにグループを見つけることができると思いますよ。
3. 一日ずつ進む

特に産後の数週間は、さまざまな変化に圧倒されることの連続です。だから、一日ずつ進んでください。
やりたいことや、あなたがやらなくてはいけないと思っていることのすべてを一日の中でやり遂げられない日があるかもしれません。
でも、それは大した問題ではありません。
あなたが精いっぱいがんばっているということ、それがすべてです。
一流のアスリートだって、優勝するまでに何試合も勝ち抜いていなかければならないような時、一つの試合が終わった後のインタビューで目標を訊かれ、「一試合一試合勝っていくだけです。目の前の試合に全力で挑みます」という言葉を耳にしたことはありませんか?
アスリートにとっての一試合一試合と同じように、今のあなたは一日一日を乗り越えることだけを考えればいいんです。一日ずつでいいんです。
4. あなた自身と赤ちゃんに寛容になる

赤ちゃんは初めてこの世界に来たのです。この世界のド素人、人間としても未熟でド素人です。だから、たくさん「あり得ない」ことをするでしょうし、あなたのお世話なくしては生きてもいけません。何もできないド素人なんですから、大目にみて寛容に接してあげてください。
あなたも同じです。特に、初めてお母さんになったのなら、あなたはお母さんのド素人です。知らないことできないこと戸惑うことがあって当然です。だから、そのことでイラついたり自己嫌悪になったり、赤ちゃんに八つ当たりする必要はないんです。
お互いド素人同士、この時期をお互いの絆を強くする時間、深く知り合う特別な時間にしてください。赤ちゃんを抱きしめたり、話しかけたり、見つめ合って過ごしてください。
そして、全てをあなたひとりでやらなくてはならないと考えないでください。
ちなみに、生まれたばかりの赤ちゃんには、昼夜を認識できる善玉菌がいないことが発見されています。体内時計が定まっていないのです。だから、生後数カ月の間は睡眠も覚醒もせいぜい2~3時間しか続かないだけでなく、睡眠時間帯も毎日ばらばらで決まった時間にまとまって眠ることはありません。
赤ちゃんが夜中に泣いても仕方がないのです。夜と昼の区別ができないのですから。
生後半年くらい経ってやっとでまとまった時間を眠るようになり、夜と昼の区別がなんとなくできてきます。
5. カウンセリングを受けてみる
もし精神的にも肉体的にもものすごく辛く、周囲に助けを求められる環境ではなければ、専門のカウンセリングを受診してみることも選択肢に入れておいてくださいね。
ヘルスコーチは心理カウンセラーではありませんが、ヘルスコーチも話を聴くエキスパートです。いろいろ相談してみてくださいね。
6. 自分時間を確保する

誰にだって、一人時間は必要です。
家族や友人やコミュニティなどからサポートを受けているのに、「自分時間が欲しいだなんてわがままだ」なんて思う必要はありません。
ほんの30分間でも、誰か信頼できる人に赤ちゃんをみてもらって、ゆっくりお風呂に浸かる、散歩する、本を読む、好きなドラマを見る、美容院に行く、なんでもいいんです。
あなたが気分転換できることなら何でも構いません。
あなたの心が健康でなければ、あなたは赤ちゃんと一緒に過ごすことが難しくなります。だから、赤ちゃんのためにも、あなたが母親でいる以外の時間をもつことは、とても大切なことです。
7. 日記をつける
日記は、心に溜まった諸々を吐き出すのにとても便利なツールです。書くことで感情を処理することが容易になります。
日が経った頃、読み返してみることで、抱えている問題を冷静に見ることができ、問題解決の糸口がみつかるかもしれません。
また、あなたの心の成長を客観的に確認することもできます。
8. 魚を食べる

ビタミンDの血液中の濃度が高いほど周産期のうつ病の発症リスクが低いこと、ビタミンD不足の状態がうつ病のリスクを高めることが明らかにされています。また同様に、血液中のDHAやEPA(オメガ3不飽和脂肪酸)の濃度が低いとうつ病を発症するリスクが高くなることも明らかにされています。
嬉しいことに、魚には、DHA/EPAとビタミンDの両方が豊富に含まれています。
妊娠中は魚を食べる量や頻度が制限されますが、産後は授乳中であっても魚を食べる量を制限する必要はありません。それどころか、魚を食べる頻度と量が多いお母さんは、産後うつ病になりにくいことが示されています。
産後うつ病の治療に魚油のサプリメントが既に用いられている他、ビタミンDが産後うつ病の改善に効果があることに期待されています。ただし、これは医療用水準で造られたサプリメントの話です。そうではないサプリメントの危険性については『DHE/EPAのサプリメント』をご確認ください。
当然、ヘルスコーチとしては、サプリメントではなく、魚を食べて欲しいです。
9. 豆類・根菜類・ベリー類・ネギ類を食べる

これらの食品には、腸内の善玉菌が大好きな食物繊維とオリゴ糖が豊富です。これらの食品を多く食べることで、腸内で短鎖脂肪酸を作る善玉菌を増やすことができます。
これら以外では、バナナやオートミールなどにも食物繊維とオリゴ糖が豊富に含まれています。
10. 多様な発酵食品を食べる

さまざまな発酵食品には、それぞれ異なるさまざまな乳酸菌やビフィズス菌がいます。
腸内の善玉菌の顔ぶれを多様にするためには、ヨーグルトだけに頼るのではなく、多様な発酵食品を食べることが有効だと考えられます。
出産後だけでなく出産前からも積極的に発酵食品を食べる習慣をもっておくと安心です。
11. エストロゲン過剰の状態を改善する
エストロゲン過剰で発症する疾患予防に効果を示している食事法については、『炎症性不妊』のページで「子宮内膜症」と「多嚢胞性卵巣症候群」をご参照ください。
ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス

もちろん、産後うつ病は、身体的、精神的、社会的な要因が複雑に絡み合って発症するものですから、食事だけで改善するとは言えません。
でも、あなたは1日3食は食べるのです。その食事があなたの不安や鬱々とした気分を予防したり改善する効果が期待できるものである方が良いに決まっています。
あなたは食べるものでできています
なお、マタニティブルーに限らず、一般的なうつの症状の予防や改善、不安症の予防や改善に良いとされる食事やライフスタイル、逆にうつや不安症になりやすい心を作ってしまう食品などについて、過去に執筆した記事は『うつ』のページをご確認ください。
また、不妊症の改善のための食事については『不妊症』をご参照ください。
今回の記事が、出産を間近に控えて、あるいは、出産したばかりで、不安や心配でいっぱいになっているあなたの心の少しの安心になっていたら嬉しいです。
今回ご紹介したことすべてをいっぺんにやらなくても大丈夫です。何かひとつからでも、今、できることから試してみてくださいね。
そして、もし、おひとりで取り組むことに不安や難しさを感じるのでしたら、ヘルスコーチと、一度、話をしてみませんか?
公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。
プライベート・ヘルスコーチング・プログラムについて
お気軽にご相談ください。
初回相談を無料でお受けしています。
あるいは、ソフィアウッズ・インスティテュートのマインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースで学びませんか?セルフドクターコースでは、あなたが食を通してご自身の主治医(セルフドクター)になるために、必要な知識とスキルを教えています。
女性ホルモンの手なずけ方、エストロゲン過剰の状態の改善方法などについても2時間のレクチャーがありますよ。
新学期は、毎年3月と9月です。講座でお会いしましょう。

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる
ニュースレターのご登録は、こちらから
統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます
参考文献:
- “How can you manage anxiety during pregnancy?”, Stephanie Collier, MD, MPH, June 25, 2021, Harvard Health Publishing, Harvard Medical School
- “Perinatal psychiatric disorders: a leading cause of maternal morbidity and mortality”, Margaret Oates, Br Med Bull, 2003:67:219-29. doi: 10.1093/bmb/ldg011, PMID: 14711766
- 「産後うつを招く孤独・孤立の背景に何が?自殺企図がある緊急性高いケースも」、平吉里奈、2024年8月16日、メディカルトリビューン
- “8 Excellent Tips For Postpartum Depression And Recovery”, Suzy Cohen
- “Intestinal microbiome and maternal mental health: preventing parental stress and enhancing resilience in mothers”, Matsunaga M, Takeuchi M, Watanabe S, Takeda AK, Kikusui T, Mogi K, Nagasawa M, Hagihara K, Myowa M., Commun Biol. 2024 Feb 29;7(1):235. doi: 10.1038/s42003-024-05884-5. PMID: 38424440; PMCID: PMC10904874.
- “Postpartum depression and vitamin D: A systematic review”, Shirin Amini, Sima Jafarirad, Reza Amani, Crit Rev Food Sci Nutr, 2019;59(9):1514-1520. doi: 10.1080/10408398.2017.1423276, Epub 2018 Feb 2, PMID: 29393662
- “Postpartum depression: aetiology, pathogenesis and the role of nutrients and dietary supplements in prevention and management”, Gnana Prasoona Rupanagunta, Mukesh Nandave, Divya Rawat, Jyoti Upadhyay, Summya Rashid, Mohd Nazam Ansari, Saudi Pharm J, 2023 Jul;31(7):1274-1293. doi: 10.1016/j.jsps.2023.05.008, Epub 2023 May 15, PMID: 37304359, PMCID: PMC10250836
ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング