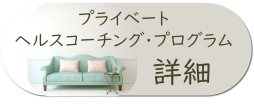уГРуВдуВкхАЛцАзуБзщгЯуБ╣уБжуАБх┐ГуБиф╜УуВТуБдуБкуБОуАБхБех║╖уБих╣╕уБЫуВТцЙЛуБлхЕеуВМуВЛуГЫуГкуВ╣уГЖуВгуГГуВпуБкщгЯф║Лц│ХуВТуВ│уГ╝уГБуГ│уВ░уБЩуВЛуАБуВ╜уГХуВгуВвуВжуГГуВ║уГ╗уВдуГ│уВ╣уГЖуВгуГЖуГеуГ╝уГИф╗гшбиуААхЕмшкНч╡▒хРИщгЯщдКуГШуГлуВ╣уВ│уГ╝уГБя╝ИCINHCя╝ЙуАБхЕмшкНхЫ╜щЪЫуГШуГлуВ╣уВ│уГ╝уГБя╝ИCIHCя╝ЙуБоцгоуБбуБЫуБзуБЩуАВ
х┐ГуБиф╜УуВТуБдуБкуБРуГЫуГкуВ╣уГЖуВгуГГуВпуБкщгЯф║Лц│ХуБлуБдуБДуБжуАБ
уГЛуГеуГ╝уВ╣уГмуВ┐уГ╝чЩ╗щМ▓шАЕщЩРхоЪуБоуВнуГгуГ│уГЪуГ╝уГ│цГЕха▒чнЙуВВщЕНф┐буБЧуБжуБДуБ╛уБЩуАВ
уБФчЩ╗щМ▓уБпуАБуБУуБбуВЙуБЛуВЙ
уВВуВМуБкуБПч╡▒хРИщгЯщдКхнжя╝ИуГЫуГкуВ╣уГЖуВгуГГуВпцаДщдКхнжя╝ЙхЖКхнРуБМчДбцЦЩуГАуВжуГ│уГнуГ╝уГЙуБзуБНуБ╛уБЩ
чЫоцмб
уБКшВЙуБМуГСуГпуГ╝уБоц║РуБауБиуБДуБЖшкНшнШуВТуВВуБгуБжуБДуВЛф║║уБпхдЪуБДуБицАЭуБДуБ╛уБЩуБМуАБуБКшВЙуБочиощбЮуБлуВИуБгуБжуБпуАБф║ИщШ▓уБЧуБжуБПуВМуВЛчЧЕц░ЧуБМщБХуБЖуБгуБжчЯеуБгуБжуБДуБ╛уБЧуБЯуБЛя╝Я
уБ╛уБЯуАБуБКшВЙуБпуБйуВМуВВщгЯуБ╣щБОуБОуБЯуВЙхРМуБШуВИуБЖуБкчЧЕц░ЧуБохОЯхЫауБлуБкуВЛуБицАЭуБгуБжуБДуВЛф║║уБпхдЪуБДуБицАЭуБДуБ╛уБЩуБМуАБуБКшВЙуБочиощбЮуБлуВИуБгуБжш╡╖уБУуВКуВДуБЩуБДчЧЕц░ЧуБочиощбЮуБМщБХуБЖуБгуБжчЯеуБгуБжуБДуБ╛уБЧуБЯуБЛя╝Я
ф╗КхЫЮуБпуАБуБЭуВУуБкуБКшВЙуБичЧЕц░ЧуБиуБощЦвф┐ВуБлуБдуБДуБжуБКф╝ЭуБИуБЧуБ╛уБЩуАВ
чЙЫшВЙуБпуБМуВУуБищЦвф┐ВуБЧуБжуБДуВЛ

2015х╣┤уБлWHOуБМш╡дшВЙуБиуБЭуБохКах╖ещгЯхУБя╝ИуГПуГауГ╗уВ╜уГ╝уВ╗уГ╝уВ╕уБкуБйя╝ЙуВТчЩ║уБМуВУцАзчЙйш│куБлхИЖщбЮуБЧуБжф╗ецЭеуАБшВЙщгЯуБМуБМуВУуГкуВ╣уВпуВТщлШуВБуВЛуБУуБиуБпх║ГуБПчЯеуВЙуВМуВЛуВИуБЖуБлуБкуВКуБ╛уБЧуБЯуАВ
ш╡дшВЙуБиуБпуАБхЫЫуБдш╢│хЛХчЙйя╝ИчЙЫуГ╗ш▒ЪуГ╗ч╛КуГ╗щжмуБкуБйя╝ЙуБошВЙуВТцМЗуБЩшиАшСЙуБзуБЩуАВшДВшВкуБох░СуБкуБДш╡дш║лшВЙуБоуБУуБиуБзуБпуБВуВКуБ╛уБЫуВУуАВ
шй│уБЧуБПуБпуАОуБКшВЙуБиуБМуВУуАПуВТуБФчв║шкНуБПуБауБХуБДуАВ
уБЧуБЛуБЧуАБуБМуВУф╗ехдЦуБочЧЕц░ЧуБиуБощЦвф┐ВуБлуБдуБДуБжуБпуАБуБВуБ╛уВКуВИуБПхИЖуБЛуБгуБжуБДуБ╛уБЫуВУуБзуБЧуБЯуАВ
уБЭуБоуБЯуВБуАБшЛ▒хЫ╜уВкуГГуВпуВ╣уГХуВйуГ╝уГЙхдзхнжуБпуАБшЛ▒хЫ╜уГРуВдуВкуГРуГ│уВпуБо47ф╕З4,985ф║║уБоцИРф║║уГЗуГ╝уВ┐уВТчФиуБДуБжуАБшВЙуВТщгЯуБ╣уВЛщЗПуБичЧЕц░ЧуБочЩ║чЧЗуГкуВ╣уВпуБлуБдуБДуБжхИЖцЮРуВТшбМуБгуБЯч╡РцЮЬуВТ2021х╣┤уБлчЩ║шбиуБЧуБжуБДуБ╛уБЩуАВ
ф╗КхЫЮуБпуАБуБЭуБоха▒хСКуВТшжБч┤ДуБЧуБжуБКф╝ЭуБИуБЧуБ╛уБЩуАВ
ш╡дшВЙя╝ИчЙЫшВЙуГ╗ш▒ЪшВЙя╝ЙуБиуБЭуБохКах╖ехУБуБзуГкуВ╣уВпуБМф╕КцШЗуБЩуВЛчЦ╛цВг

ш╡дшВЙя╝ИчЙЫшВЙуГ╗ш▒ЪшВЙя╝ЙуБиуБЭуБохКах╖ещгЯхУБуВТуБЭуВМуБ╗уБйщгЯуБ╣уБкуБДф║║уБицпФш╝ГуБЧуБжуАБхоЪцЬЯчЪДуБлщА▒я╝УхЫЮф╗еф╕КщгЯуБ╣уВЛф║║уБпуАБя╝СцЧеуБлщгЯуБ╣уВЛщЗПуБМ70gхвЧуБИуВЛуБФуБиуБлцмбуБочЦ╛цВгуБочЩ║чЧЗуГкуВ╣уВпуБМф╕КцШЗуБЩуВЛуБУуБиуБМчд║уБХуВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВ
- шВ║чВОуГ╗уГ╗уГ╗1.31хАН
- ч│Цх░┐чЧЕуГ╗уГ╗уГ╗1.30хАН
- цЖйходчЦ╛цВгуГ╗уГ╗уГ╗1.19хАН
- шЩЪшбАцАзх┐ГчЦ╛цВгуГ╗уГ╗уГ╗1.15хАН
- хдзшЕ╕уГЭуГкуГ╝уГЧуГ╗уГ╗уГ╗1.10хАН
уБбуБкуБ┐уБлуАБцЖйходчЦ╛цВгуБиуБпуАБц╢ИхМЦчобуБохгБуБоф╕АщГиуБМхдЦхБ┤уБлшвЛчК╢уБлчкБхЗ║уБЧуБжуБЧуБ╛уБЖчЧЕц░ЧуБзуБЩуАВ
я╝Бш╡дшВЙуБзуГкуВ╣уВпуБМф╜Оф╕ЛуБЩуВЛчЦ╛цВг
щЙДцмаф╣ПцАзш▓зшбАуГ╗уГ╗уГ╗хКах╖еуБХуВМуБжуБДуБкуБДш╡дшВЙуВТщгЯуБ╣уВЛщЗПуБМя╝СцЧеуБл50gхвЧуБИуВЛуБФуБиуБлуАБщЙДцмаф╣ПцАзш▓зшбАуБочЩ║чЧЗуГкуВ╣уВпуБМ20%уВВф╜Оф╕ЛуБЩуВЛуБУуБиуБМчд║уБХуВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВ
чв║уБЛуБлуАБш╡дшВЙуБлуБпщЙДхИЖуБМш▒КхпМуБлхРлуБ╛уВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

шГЖчобуБМуВУуГ╗уГ╗уГ╗хдзшжПцибуВ│уГЫуГ╝уГИчаФчй╢JPHC StudyуБлчЩ╗щМ▓уБЧуБжуБДуВЛ9ф╕Зф║║ш╢ЕуВТш┐╜ш╖бшк┐цЯ╗уБЧуБЯч╡РцЮЬуВТхЫ╜члЛуБМуВУчаФчй╢уВ╗уГ│уВ┐уГ╝уБМ2019х╣┤уБлчЩ║шбиуБЧуБжуБДуБ╛уБЩуАВш╡дшВЙуВТщгЯуБ╣уВЛщЗПуБМхдЪуБДчФ╖цАзуБзуБпуАБшГЖчобуБМуВУуГкуВ╣уВпуБМ0.66хАНя╝И34%ц╕Ыя╝ЙуБлф╜Оф╕ЛуБЩуВЛуБУуБиуБМчд║уБХуВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВуБкуБКуАБхе│цАзуБзуБпщЦвщАгцАзуБМшжЛуВЙуВМуБ╛уБЫуВУуБзуБЧуБЯуАВ
чаФчй╢шАЕуБпуАМуБкуБЬуБУуБоуВИуБЖуБкч╡РцЮЬуБМх╛ЧуВЙуВМуБЯуБЛуАБуБЭуБоуГбуВлуГЛуВ║уГауБлуБдуБДуБжуБпуБпуБгуБНуВКхИЖуБЛуВЙуБкуБДуАНуБиш┐░уБ╣уБжуБДуБ╛уБЩуАВ
чЩ╜шВЙя╝Ищ╢ПшВЙя╝ЙуБзуГкуВ╣уВпуБМф╕КцШЗуБЩуВЛчЦ╛цВг

чЩ╜шВЙуБиуБпуАБщ╢ПшВЙуВДщнЪуВТцМЗуБЩшиАшСЙуБзуБЩуАВф╗КхЫЮуБочаФчй╢уБзуБпуАБщ╢ПшВЙуВТщгЯуБ╣уВЛща╗х║жуВДщЗПуБМшк┐цЯ╗уБХуВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВ
щ╢ПшВЙуВТя╝СцЧеуБлщгЯуБ╣уВЛщЗПуБМ30gхвЧуБИуВЛуБФуБиуБлцмбуБочЦ╛цВгуБочЩ║чЧЗуГкуВ╣уВпуБМф╕КцШЗуБЩуВЛуБУуБиуБМчд║уБХуВМуБ╛уБЧуБЯуАВ
- шГГщгЯщБУщАЖц╡БчЧЗуГ╗уГ╗уГ╗1.17хАН
- ч│Цх░┐чЧЕуГ╗уГ╗уГ╗1.14хАН
- шГГчВОуБКуВИуБ│хНБф║МцМЗшЕ╕чВОуГ╗уГ╗уГ╗1.12хАН
- шГЖуБоуБЖчЦ╛цВгуГ╗уГ╗уГ╗1.11хАН
- шГЖуБоуБЖцЖйходчЦ╛цВгуГ╗уГ╗уГ╗1.10хАН
я╝БчЩ╜шВЙуБзуГкуВ╣уВпуБМф╜Оф╕ЛуБЩуВЛчЦ╛цВг
щЙДцмаф╣ПцАзш▓зшбАуГ╗уГ╗уГ╗ш╡дшВЙуБихРМцзШуБлуАБщ╢ПшВЙуВВщгЯуБ╣уВЛщЗПуБМя╝СцЧеуБл30gхвЧуБИуВЛуБФуБиуБлуАБщЙДцмаф╣ПцАзш▓зшбАуБоуГкуВ╣уВпуВТ17%уВВц╕Ых░СуБХуБЫуБ╛уБЧуБЯуАВ
ф╕КуБлцО▓ш╝ЙуБЧуБЯуАМщЙДхИЖуБохдЪуБДшВЙщбЮуАНуБоуГкуВ╣уГИуБлуБпхРлуБ╛уВМуБжуБДуБ╛уБЫуВУуБМуАБщ╢ПшВЙуБоуВВуВВшВЙуБицЙЛч╛╜уБлуБпуАБчв║уБЛуБля╝СцЧеуБлх┐ЕшжБуБиуБЩуВЛщЙДхИЖуБо10%ф╗еф╕КуБМхРлуБ╛уВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВя╝Ия╝СцЧеуБох┐ЕшжБщЗПуБо10%ф╗еф╕КуВТхРлуВАха┤хРИуБпуАМш▒КхпМуАНуБишбичП╛уБзуБНуБ╛уБЩя╝Й
шВЙщбЮуБпш╡дуБзуВВчЩ╜уБзуВВуГкуВ╣уВпя╝Я

чЙЫшВЙуВДш▒ЪшВЙуБкуБйуБищ╢ПшВЙуБзуБЛуБЛуВКуВДуБЩуБДчЧЕц░ЧуБлщБХуБДуБМуБВуВЛуБиуБДуБЖуБоуБпщЭвчЩ╜уБДуБзуБЩуБнуАВ
щЙДцмаф╣ПцАзш▓зшбАуВТщЩдуБДуБжуАБшВЙщбЮуБпш╡дуБзуБВуВНуБЖуБичЩ╜уБзуБВуВНуБЖуБиуАБф╜ХуБЛуБЧуВЙуБочЧЕц░ЧуБищЦвф┐ВуБЧуБжуБДуВЛуБиуБДуБЖха▒хСКуБпшбЭцТГчЪДуБзуБЩуАВ
хЛХчЙйцАзуВ┐уГ│уГСуВпш│куБиуБДуБЖшжЦчВ╣уБзшжЛуВЛуБиуАБщнЪуБпуАБWHOуБпуАМх░СуБкуБПуБиуВВщА▒уБля╝ТщгЯф╗еф╕КщгЯуБ╣уВЛуБУуБиуАНуВТцОихеиуБЧуБжуБДуБ╛уБЩуБоуБзуАБхЛХчЙйцАзуВ┐уГ│уГСуВпш│куБпуАБщнЪуБЧуБЛхоЙх┐ГуБЧуБжщгЯуБ╣уВЛуБУуБиуБМуБзуБНуБкуБДуБиуАБуБДуБЖуБУуБиуБзуБЧуВЗуБЖуБЛя╝Я

уВ╜уГХуВгуВвуВжуГГуВ║уГ╗уВдуГ│уВ╣уГЖуВгуГЖуГеуГ╝уГИуБЛуВЙуБоуВвуГЙуГРуВдуВ╣

уБзуВВуАБщнЪуБлуБпц░┤щКАуВДуГЮуВдуВпуГнуГЧуГйуВ╣уГБуГГуВпц▒ЪцЯУуБохХПщбМуБМуБВуВКуБ╛уБЩуАВцдНчЙйцАзуБоуВ┐уГ│уГСуВпш│куБауБгуБжуАБф╛ЛуБИуБ░уАБхдзш▒ЖуВДуГКуГГуГДщбЮуБауБгуБжуВлуГЙуГЯуВжуГац▒ЪцЯУуБохХПщбМуБМуБВуВКуБ╛уБЩуАВ
цЬмх╜УуБлхоЙх┐ГуБЧуБжщгЯуБ╣уВЙуВМуВЛщгЯхУБуБпуАБуВВуБпуВДхнШхЬиуБЧуБкуБД
уБиуБДуБЖуБоуБМф╗КуБоф╕ЦуБоф╕нуБочП╛хоЯуБзуБпуБкуБДуБзуБЧуВЗуБЖуБЛуАВ
уБиуБпуБДуБИуАБуВ┐уГ│уГСуВпш│куВТщгЯуБ╣уБкуБДуБиуБДуБЖщБ╕цКЮшВвуБпуБВуВКуБ╛уБЫуВУуАВщгЯуБ╣уБкуБСуВМуБ░чФЯуБНуБжуБпуБДуБСуБ╛уБЫуВУуАВ
шжЦщЗОуВТх║ГуБПуБЧуБжшжЛуВЛх┐ЕшжБуБМуБВуВКуБЭуБЖуБзуБЩуАВ
ф╛ЛуБИуБ░уАБф╗КхЫЮуБочаФчй╢уБзуБпуАБшВЙуБиф╕Ач╖ТуБлщгЯуБ╣уВЛщЗОшПЬуБощЗПуБлуБдуБДуБжуБошк┐цЯ╗уБпуБкуБХуВМуБжуБДуБ╛уБЫуВУуАВ
щЗОшПЬуБпуАБуБХуБ╛уБЦуБ╛уБкчЦ╛цВгф║ИщШ▓хК╣цЮЬуВТуВВуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ
щгЯуБ╣уВЛшВЙуБощЗПуБлхп╛уБЩуВЛщЗОшПЬуБоуГРуГйуГ│уВ╣уБлуВИуБгуБжчЦ╛цВгуГкуВ╣уВпуБпчХ░уБкуВКуБ╛уБЩуАВ
уВПуБЯуБЧуБоф╗КуБ╛уБзуБоуВпуГйуВдуВвуГ│уГИуБХуВУуБЯуБбуБоуГЧуГнуВ░уГйуГащЦЛхзЛх╜УхИЭуБоуБКшВЙуБищЗОшПЬуБоуГРуГйуГ│уВ╣уБЛуВЙуБпуАБхдзцК╡уБоф║║уБпуАБшЗкхИЖуБзцАЭуБгуБжуБДуВЛуБ╗уБйшВЙуБощЗПуБлцпФуБ╣уБжхНБхИЖуБкщЗОшПЬуВТщгЯуБ╣уБжуБДуБкуБДуБишиАуБИуБ╛уБЩуАВ
уАОхБех║╖чЪДуБкшАБхМЦуАПуБзуБКф╝ЭуБИуБЧуБЯщАЪуВКуАБчзСхнжчЪДуБкшгПф╗ШуБСуВТуВВуБдя╝ШуБдуБощгЯф║Лц│ХуБоф╕нуБзцЬАуВВхБех║╖чЪДуБкшАБхМЦуБищЦвщАгуБМщлШуБЛуБгуБЯуБоуБпч╡▒хРИщгЯщдКхнжуВТхРлуВАуГПуГ╝уГРуГ╝уГЙхдзхнжуБМшАГцбИуБЧуБЯуВВуБоуБзуБЧуБЯуАВ
ф╗КхЫЮуБКф╝ЭуБИуБЧуБЯч╡▒шиИуБпч╡▒шиИуБиуБЧуБжуАБщгЯхУБуБош│куВТхдЙуБИуАБщгЯф║ЛуБоуГРуГйуГ│уВ╣уВТхдЙуБИуВЛуБУуБиуБзуАБш║лф╜УцйЯшГ╜уВВч▓╛чеЮцйЯшГ╜уВВшкНчЯецйЯшГ╜уВВхБех║╖чЪДуБлцн│уВТуБиуВЛуБУуБиуБпхПпшГ╜уБкуВУуБзуБЩуАВ
хЕмшкНуГЫуГкуВ╣уГЖуВгуГГуВпуГ╗уГШуГлуВ╣уВ│уГ╝уГБуБпуАБщгЯф║ЛуБауБСуБзуБкуБПуАБуБВуБкуБЯуВТхПЦуВКх╖╗уБПцзШуАЕуБкуБУуБия╝ИчТ░хвГуАБф╗Хф║ЛуАБхо╢цЧПуАБф║║щЦУщЦвф┐ВуБкуБйя╝ЙуВТшАГцЕоуБЧуБжуАБуГЧуГнуВ░уГйуГауБлхПНцШауБХуБЫуАБуБВуБкуБЯуБМуАБуБкуВКуБЯуБДуБВуБкуБЯуБлуБкуВМуВЛуВИуБЖуВ│уГ╝уГБуГ│уВ░уВТцПРф╛ЫуБЧуБ╛уБЩуАВ
уВВуБЧуБКуБ▓уБиуВКуБзхПЦуВКч╡ДуВАуБУуБиуБлф╕НхоЙуВДщЫгуБЧуБХуВТцДЯуБШуВЛуБоуБзуБЧуБЯуВЙуАБуГШуГлуВ╣уВ│уГ╝уГБуБиуАБф╕Ах║жуАБшй▒уВТуБЧуБжуБ┐уБ╛уБЫуВУуБЛя╝Я
уГЧуГйуВдуГЩуГ╝уГИуГ╗уГШуГлуВ╣уВ│уГ╝уГБуГ│уВ░уГ╗уГЧуГнуВ░уГйуГауБлуБдуБДуБж
уБКц░Чш╗╜уБлуБФчЫ╕шлЗуБПуБауБХуБДуАВ
хИЭхЫЮчЫ╕шлЗуВТчДбцЦЩуБзуБКхПЧуБСуБЧуБжуБДуБ╛уБЩуАВ
уБВуВЛуБДуБпуАБуВ╜уГХуВгуВвуВжуГГуВ║уГ╗уВдуГ│уВ╣уГЖуВгуГЖуГеуГ╝уГИуБоуГЮуВдуГ│уГЙуГ╗уГЬуГЗуВгуГ╗уГбуГЗуВгуВ╖уГ│шмЫх║зуВ╗уГлуГХуГЙуВпуВ┐уГ╝уВ│уГ╝уВ╣уБзхнжуБ│уБ╛уБЫуВУуБЛя╝ЯуВ╗уГлуГХуГЙуВпуВ┐уГ╝уВ│уГ╝уВ╣уБзуБпуАБуБВуБкуБЯуБМщгЯуВТщАЪуБЧуБжуБФшЗкш║луБоф╕╗ц▓╗хМ╗я╝ИуВ╗уГлуГХуГЙуВпуВ┐уГ╝я╝ЙуБлуБкуВЛуБЯуВБуБлуАБх┐ЕшжБуБкчЯешнШуБиуВ╣уВнуГлуВТцХЩуБИуБжуБДуБ╛уБЩуАВ
цЦ░хнжцЬЯуБпуАБцпОх╣┤3цЬИуБи9цЬИуБзуБЩуАВшмЫх║зуБзуБКф╝ЪуБДуБЧуБ╛уБЧуВЗуБЖуАВ

х┐ГуБиф╜УуВТуБдуБкуБДуБзхБех║╖уБих╣╕уБЫуВТцЙЛуБлхЕеуВМуВЛ
уГЛуГеуГ╝уВ╣уГмуВ┐уГ╝уБоуБФчЩ╗щМ▓уБпуАБуБУуБбуВЙуБЛуВЙ
ч╡▒хРИщгЯщдКхнжя╝ИуГЫуГкуВ╣уГЖуВгуГГуВпцаДщдКхнжя╝ЙхЖКхнРуБМчДбцЦЩуГАуВжуГ│уГнуГ╝уГЙуБзуБНуБ╛уБЩ
хПВшАГцЦЗчМо
- тАЬMeat consumption and risk of 25 common conditions: outcome-wide analyses in 475,000 men and women in the UK Biobank study.тАЭ, Papier K, Fensom GK, Knuppel A, Appleby PN, Tong TYN, Schmidt JA, Travis RC, Key TJ, Perez-Cornago A, BMC Med. 2021 Mar 2;19(1):53. doi: 10.1186/s12916-021-01922-9. PMID: 33648505; PMCID: PMC7923515
уВ╜уГХуВгуВвуВжуГГуВ║уГ╗уВдуГ│уВ╣уГЖуВгуГЖуГеуГ╝уГИ – уГЫуГкуВ╣уГЖуВгуГГуВпуГШуГлуВ╣уВ│уГ╝уГБуГ│уВ░