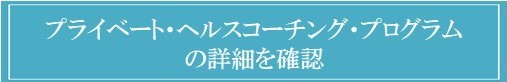バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。
心と体をつなぐホリスティックな食事法について、
ニュースレター登録者限定のキャンペーン情報等も配信しています。
ご登録は、こちらから
もれなく統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます
目次
あなたを引き止める慣性の法則
何か新しいことを始めるのは、不安です。
やったことがないことに挑戦するのには、恐怖心が伴います。
これからどうなるか分からない不確かなことを避けて、既に結果が分かっていることだけをしていれば、あなたは失敗して恥ずかしい思いをしたり、批判される不安を覚えることはありません。
物理の法則「慣性の法則」が心にもあります。
変化を避けて、今の習慣をずっと続けていたいという本能です。
でも、どうなるか分からないけれど、勇気を出してやってみた最も居心地の悪い状況の中で、大抵、人生のサプライズは見つかります。人生の学びや成長は、大抵、「もしかしたら失敗するかもしれない」という居心地の悪い場所にあります。
なお、裏付けとなる研究論文を最後に参考文献として一覧にしています。
回避行動の危険性

良く知らない領域に踏み込んで挑戦するよりも、馴染みのあるところに留まることを選んでしまう理由のひとつは、何が起こるか分からない状況や失敗する可能性に対する恐怖です。
確信のもてない状況を避ければ、短期的には不安や恐怖は取り除かれます。
でも、長期的には、もっと大きなストレス源を作ってしまうことがあると、2011年の『the Journal of Consulting and Clinical Psychology(カウンセリングと臨床心理学ジャーナル)』に発表された研究が示しています。
壮年期にいる被験者1,211名の回避行動と、その影響について10年に渡り、定期的に3度、調査しています。その結果、回避行動は、次のリスクと関係性があることが判明しました。
- 重度の慢性ストレス
- うつの発症
つまり、不確かなことを避ける傾向にある人ほど、重度の慢性ストレスを抱える傾向が強く、また、うつを発症することが多いと言えます。
また、2013年にthe Mayo Clinicで行われた調査は、恐怖に感じる状況を避ける子供は、不安症に悩まされる傾向が強いと報告しています。
800人以上の子供の回避行動を調査したところ、調査が行われた時点で回避行動が見られた子供は、その1年後に高い不安感(ストレス反応)を示したとのことです。
ストレス源(不確かな状況)を避ければ避けるほど、安心が得られるわけではなく、逆に、重度の慢性ストレスに悩まされたり、うつになる可能性が高まるとは、皮肉なものです。
恐怖心は消せない

『the Journal of Anxiety Disorders(不安障害ジャーナル)』に2016年発表された研究は、私たちの最も根底にある根源的恐怖心について検証しています。
研究者は、私たちが感じる未知のものごとへの恐怖心は、様々な恐怖心の根底にある最も根源的な恐怖心ではないかと述べています。根源的な恐怖心は、単に不安感を引き起こすだけでなく、精神疾患の原因になることもあります。
そんな恐怖心なら、取り除きたいものですが、簡単な話ではありません。
なぜなら、根源的恐怖心は、取り除こうとして取り除けるものではないからです。
恐怖心はあなたの味方
恐怖心は、向き合うことでのみ克服できるものだからです。つまり、恐怖心を克服するためには、恐怖を感じなければならないのです。
また、あなたは恐怖心を敵のように思っているかもしれませんが、実は、恐怖心は、あなたの味方なんです。あなたを守ろうとして起こるのです。
日常的な、あなたの感情や判断を助ける役割をもっています。
恐怖心がなければ、あなたは命の危険がある状況にあなたを追い込んでしまう可能性があります。
原始の脳の中にある偏桃体が起こすストレス反応(恐怖心)は、あなたを守るためにあるのです。
顔見知りの悪魔の方が見知らぬ悪魔よりも良い

面白いことに、2016年に『ネイチャー・コミュニケーションズ』で報告された研究は、望まない結果であっても、結果を知っている方が、知らないよりもストレスが低いことを明らかにしています。
50%の確率で電気ショックを受ける(2回に1回の確率で電気ショックを受けない)と伝えられた被験者は、確実に電気ショックを受けると伝えられた被験者よりも、ストレスレベルが高かったことが示されています。
どんなに悪い結果でも、確実な結果の方が、どっちになるのか分からない結果よりもマシということですね。
高ストレスは直感力を高める?
話は逸れますが、最も高いストレス反応を示した被験者グループは、次に電気ショックが与えられるか与えられないかを高い確率で予測することができるようになったと報告されています。
私たちの判断能力が、高ストレスによって向上する可能性を示唆していると、研究者は述べていますが、ランダムに行われる電気ショックの有無を当てられるなんて、なんだか、超能力の開花のようですね。
ヒトには、まだまだ、追い詰められたら思わぬ能力を開花させる可能性をもっているのかもしれません。「火事場の馬鹿力」でしょうか(笑)
現実の受け止め方次第

居心地のよい場所から出られないのは、恐怖心のせいだと思っているかもしれませんが、恐怖心が起こるも起こらないも、あなたの感じ方/考え方次第です。
この先の結果が分からない、状況が不確実だということは事実だとしても、あなたがその状況には問題がないと認識すれば、恐怖心は抑制されます。
現実的にあなたを脅かすものが何もなかったとしても、あなたが危険だと思えば、恐怖心は起こります。
今回は、コンフォートゾーン(居心地の良い場所)から一歩だけ出る簡単なテクニックについてお伝えします。
コンフォートゾーンの外に一歩出る方法

新しいことに挑戦することに躊躇してしまっている人、生活習慣を変えたいのに、いつも中途半端のまま元に戻ってしまう人、自分の殻をやぶりたいと思っているのに勇気が出せない人のお役に立てたら嬉しいです。
1. ただ行ってみる

どんな結果になるのか分からないことを避けようとしている時は、大抵、現実的でない高い期待を自分にして、その期待を満たせなかった時を想像して、恐怖しています。
その状況を避けさえすれば、自分に失望したり恥ずかしい思いをせずに済むので、避けようとするのです。
だったら、自分に大きな期待をせずに、ただやったらいいのです。
例えば、「ただ行くだけ」というのはどうでしょうか。
行ってからのことは、その時の風にまかせることにして(笑)何が起こるかなんて、期待せず、予測もせず、ただ行く、出席する、参加すると、いうことだけを目標にするのです。
私は、これがなかなか苦手です。行くからには何等かの成果を期待しまうからでしょうか。だから「ただ行くだけ」というフラットな気持ちでいることを、何かのお誘いをいただいた時には、常に、自分にリマインドするようにしています。
2. 小さく始める

完全でなければゼロと、いう思考は、あなたの成長にとって大きな障害となります。
一気に大きく考えすぎると、大抵、圧倒されて思考も動きもフリーズしてしまいます。そして、あなたの殻に閉じこもっている方が安全で心地よく思えてきます。
完璧でなければ、敗北だという考え方は、あなたの成長を妨げます。1番でなければ、全て負けという思考です。
大きく考えすぎるあまりに一歩が踏み出せないのなら、大きな目標を小さな目標に分解するのはどうでしょうか。小さな目標を積み重ねることによって、大きな目標を達成する可能性が高まります。
例えば、2mの高さのフェンスを一気に飛び越えるのは、失敗するリスクが伴います。でも、30cmづつブロックを積み重ねて少しずつ上っていけば、確実に乗り越えることができます。
3. ひとつだけ変える
何かを変えたいと思っている人は、大抵、あれもこれもと多くのことを一度に変えなければならないと考えてしまいがちです。そしてそれがあまりに多すぎて、どうせ全てやるのは無理だと感じ、諦めてしまうのです。
いつもの思考パターンに陥るのは簡単です。
現状でいつづけることが、いかにあなたを憂鬱な気分にさせようとも、失敗する恐怖よりはマシだと思えてくるのです。
でも、すべてを一度に変える必要なんてないんです。何かひとつを変える勇気をもつことができれば、例えそれが小さくてあまり重要でないことのように思えても、いずれ大きな成果につながります。
何かをひとつ、いつもとは異なることを始めたら、脳はあなたが変化を望んでいることを察知します。そうしてひとつずつ、脳に変化を怖がらなくても良いのだと教えていくことができます。
例えば、こんな小さなことでも良いのです。
- 仕事場までのルートを変えてみる
- コーヒーショップの店員さんと雑談してみる
- 新しいレシピに挑戦してみる
などなど・・脳は、あなたが新しいことを求めていることを理解します。
小さかろうと大きかろうと、あなたが新しい経験を与えてあげればあげるほど、脳はそれを楽しむようになります。
4. 内なる批判者に疑問をもつ
あなたの心の内にいる、あなたを批判する声は、あなたの評価者としてはベストな人選ではありません。
大概の場合、その声の言うことは、真実ではありません。
ただ問題は、その声には、説得力があるということです。あなたが既に不安や恐怖を感じている時は特に。
心の内から、あなたを批判する声に敏感になってください。
まずはその声に気づくことが重要です。そして、その声に気づいたら直ぐに、その声を黙らせるか、反論しなくてはいけません。言っていることは本当に現実的なのか正しいのか、それともあなたの恐怖心が言わせているだけの被害妄想なのか。
疑問をもってください。
内なるあなたを批判する声に反論することで、あなたは、自信がもてるようになります。
5. セルフケアを実践する

結果が分からない不確かなこと向き合うには、心にも体にもエネルギーが必要です。
あなたの心と体はつながっています。心が弱くなりそうなとき、体が強ければ、心の支えとなります。その逆も真です。
- 運動する
- 健康的に食べる
- リラックスする
- 愛する人達と接する
- 好きなことをやる
そうすることで、あなたの体と心は元気になります。あなたが不安に感じることと向き合わなければならなくなった時、あなたをサポートしてくれるはずです。
コンフォートゾーンの外で待ち受ける未知なる出来事が恐怖ではなく楽しみに感じられるようになるでしょう。
ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス

言っても、人生は1回限りです。
不安や恐怖心から、望む人生を歩むことを諦めたら、その後長期に渡って不安と不満を抱えて生きることなるかもしれません。
小さく始めて自分に優しく、不安な状況に立ち向かったご自分にご褒美することを忘れずに努力をお祝いしましょう。
もしおひとりで取り組むことに不安や難しさを感じるのでしたら、ヘルスコーチと、一度、話をしてみませんか?
公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。
プライベート・ヘルスコーチング・プログラムについて
お気軽にご相談ください。
初回相談を無料でお受けしています。
あるいは、ソフィアウッズ・インスティテュートのマインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースで学びませんか?
マインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースの中では、ストレスと仲良くなる脳とホルモンの仕組み、そして、簡単にできる具体的な方法についてお伝えしています。
セルフドクターコースでは、あなたが食を通してご自身の主治医(セルフドクター)になるために、必要な知識とスキルを教えています。
新学期は、毎年3月と9月です。講座でお会いしましょう。

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる
ニュースレターのご登録は、こちらから
統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます
参考文献:
- “Stress Generation, Avoidance Coping, and Depressive Symptoms: A 10-Year Model”, Holahan, C. J., Moos, R. H., Holahan, C. K., Brennan, P. L., & Schutte, K. K. (2005), Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(4), 658-666, http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.73.4.658
- “Computations of uncertainty mediate acute stress responses in humans”, Archy O. de Berker, Robb B. Rutledge, Christoph Mathys, Louise Marshall, Gemma F. Cross, Raymond J. Dolan & Sven Bestmann, Nature Communications, volume 7, Article number: 10996 (2016)
- “Fear of the unknown: One fear to rule them all?”, R. Nicholas Carleton, Journal of Anxiety Disorders, Volume 41, June 2016, Pages 5-21, https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.03.011
- “The default response to uncertainty and the importance of perceived safety in anxiety and stress: An evolution-theoretical perspective”, Brosschot JF, Verkuil B, Thayer JF, J Anxiety Disord. 2016 Jun;41:22-34. doi: 10.1016/j.janxdis.2016.04.012. Epub 2016 May 7
- “Children who avoid scary situations likelier to have anxiety”, Mayo Clinic, March 11, 2013, Science News
ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング