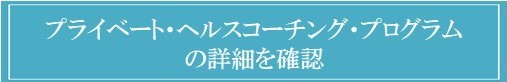сЃљсѓцсѓфтђІТђДсЂДжБЪсЂ╣сЂдсђЂт┐ЃсЂеСйЊсѓњсЂцсЂфсЂјсђЂтЂЦт║исЂет╣ИсЂЏсѓњТЅІсЂФтЁЦсѓїсѓІсЃЏсЃфсѓ╣сЃєсѓБсЃЃсѓ»сЂфжБЪС║ІТ│Ћсѓњсѓ│сЃ╝сЃЂсЃ│сѓ░сЂЎсѓІсђЂсѓйсЃЋсѓБсѓбсѓдсЃЃсѓ║сЃ╗сѓцсЃ│сѓ╣сЃєсѓБсЃєсЃЦсЃ╝сЃѕС╗БУАесђђтЁгУфЇух▒тљѕжБЪжцісЃўсЃФсѓ╣сѓ│сЃ╝сЃЂ№╝ѕCINHC№╝ЅсђЂтЁгУфЇтЏйжџЏсЃўсЃФсѓ╣сѓ│сЃ╝сЃЂ№╝ѕCIHC№╝ЅсЂ«ТБ«сЂАсЂЏсЂДсЂЎсђѓ
т┐ЃсЂеСйЊсѓњсЂцсЂфсЂљсЃЏсЃфсѓ╣сЃєсѓБсЃЃсѓ»сЂфжБЪС║ІТ│ЋсЂФсЂцсЂёсЂдсђЂ
сЃІсЃЦсЃ╝сѓ╣сЃгсѓ┐сЃ╝уЎ╗жї▓УђЁжЎљт«џсЂ«сѓГсЃБсЃ│сЃџсЃ╝сЃ│ТЃЁта▒уГЅсѓѓжЁЇС┐АсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сЂћуЎ╗жї▓сЂ»сђЂсЂЊсЂАсѓЅсЂІсѓЅ
сѓѓсѓїсЂфсЂЈух▒тљѕжБЪжцітГд№╝ѕсЃЏсЃфсѓ╣сЃєсѓБсЃЃсѓ»ТаёжцітГд№╝ЅтєітГљсЂїуёАТќЎсЃђсѓдсЃ│сЃГсЃ╝сЃЅсЂДсЂЇсЂЙсЂЎ
уЏ«ТгА
- ADHDТ▓╗уЎѓУќгсЂ«Сйюуће
- сѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сЂ«Сйюуће
- жЄЇУдЂсЂфсЂ«сЂ»сѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│тЈЌт«╣СйЊ
- сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂеADHDТ▓╗уЎѓУќг
- сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂїADHDсЂФті╣сЂЈсЂеУђЃсЂѕсѓЅсѓїсѓІуљєућ▒
- 1. сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ»сЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│сЂесЃјсЃФсѓбсЃЅсЃгсЃісЃфсЃ│сѓњтбЌсѓёсЂЎ
- 2. сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ»тЅЇжаГуџ«У│фсЂ«сЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│СйютІЋТђДТЕЪУЃйсѓњТГБтИИтїќсЂЎсѓІ
- 3. сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ»У╗йт║дсЂ«ADHDсѓњТћ╣тќёсЂЎсѓІ
- 4. сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ»т╝иУ┐ФТђДжџют«│Т▓╗уЎѓсЂФТюЅті╣
- 5. сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ»сѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│тЈЌт«╣СйЊсЂ«СйюућесѓњТЅЊсЂАТХѕсЂЎ
- 6. сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ»ADHDТ▓╗уЎѓУќгсЂеСйЊтєЁТЕЪт║ЈсЂїжАъС╝╝
- сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ«СйюућесЂ«уеІт║дсЂ»сЃњсЃѕсЂФсѓѕсЂБсЂдуЋ░сЂфсѓІ
- тГдТаАсЂ«ТѕљуИЙсѓѓтцДтѕЄсЂДсЂЎсЂїТюгС║║сЂ«УЄфти▒Уѓ»т«џТёЪсЂ»сѓѓсЂБсЂетцДтѕЄ
- сѓйсЃЋсѓБсѓбсѓдсЃЃсѓ║сЃ╗сѓцсЃ│сѓ╣сЃєсѓБсЃєсЃЦсЃ╝сЃѕсЂІсѓЅсЂ«сЂћТЈљТАѕ
ADHDТ▓╗уЎѓУќгсЂ«Сйюуће
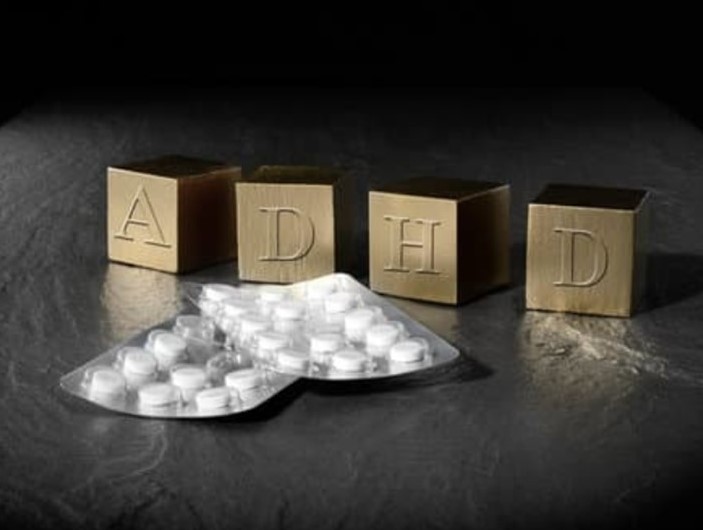
ADHDсЂ«Т▓╗уЎѓУќгсђЂСЙІсЂѕсЂ░сђЂсѓ│сЃ│сѓхсЃ╝сѓ┐сђЂсѓбсЃЄсЃЕсЃФсђЂсЃфсѓ┐сЃфсЃ│сђЂсЃЄсѓГсѓ╗сЃЅсЃфсЃ│сЂфсЂЕсЂ»сђЂтЁесЂдсѓбсЃ│сЃЋсѓДсѓ┐сЃЪсЃ│у│╗№╝ѕтљЉу▓ЙуЦъТђДж║╗Уќгу│╗№╝Ѕ сЂ«УќгсЂДсђЂ сЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│сѓёсЃјсЃФсѓбсЃЅсЃгсЃісЃфсЃ│сЂфсЂЕсЂ«уЦъухїС╝ЮжЂћуЅЕУ│фсѓњтбЌсѓёсЂЎсЂЊсЂесЂДсђЂADHDсЂ«уЌЄуіХсѓњТћ╣тќёсЂЎсѓІсѓѕсЂєсЂФтЃЇсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
сЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│сЂ»уДЂжЂћсЂ«тќюсЂ│сЂ«ТёЪТЃЁсЂесђЂсЃјсЃФсѓбсЃЅсЃгсЃісЃфсЃ│сЂ»тЅЇтљЉсЂЇсЂфсѓёсѓІТ░ЌсЂежќбС┐ѓсЂЌсЂдсЂёсѓІсЃЏсЃФсЃбсЃ│сЂДсЂЎсђѓ
сѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сЂ«Сйюуће
сѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сЂФсѓѕсЂБсЂдсЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│сѓёсЃјсЃФсѓбсЃЅсЃгсЃісЃфсЃ│сЂїтбЌтіасЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїуб║УфЇсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сѓѓсЂЌсѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сЂїADHDТ▓╗уЎѓУќгсЂ«С╗БсѓЈсѓісЂФсЂфсѓІсЂ«сЂфсѓЅсђЂсѓбсЃ│сЃЋсѓДсѓ┐сЃЪсЃ│у│╗№╝ѕтљЉу▓ЙуЦъТђДж║╗Уќгу│╗№╝ЅсЂ«УќгсѓњтГљСЙЏсЂФжБ▓сЂ┐уХџсЂЉсЂЋсЂЏсЂфсЂЈсЂдсѓѓУЅ»сЂЈсЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
тЅ»СйюућесЂ«сЂѓсѓІУќгсѓњжБ▓сЂЏсѓІсЂЊсЂесѓњУђЃсЂѕсЂЪсѓЅсђЂсЂџсЂБсЂет«ЅтЁесЂДт«Ѕт┐ЃсЂДсЂ»сЂфсЂёсЂ«сЂДсЂЌсѓЄсЂєсЂІсђѓ
жЄЇУдЂсЂфсЂ«сЂ»сѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│тЈЌт«╣СйЊ

сѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│сЂ»сђЂТДўсђЁсЂфС╗БУгЮсђЂУфЇуЪЦТЕЪУЃйсђЂтєижЮЎсЂЋсѓёжЏєСИГтіЏсЂФжќбС┐ѓсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сЂ«СйюућесѓњуљєУДБсЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂФсЂ»сђЂсѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│сЂеухљсЂ│сЂцсЂЈсѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│тЈЌт«╣СйЊсЂФсЂцсЂёсЂдуЪЦсѓІт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│тЈЌт«╣СйЊсЂ»сђЂсѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│сЂесЂёсЂєуЅЕУ│фсѓњтЈЌсЂЉтЈќсѓІсѓ░сЃГсЃ╝сЃќсЂ«сѓѕсЂєсЂфсѓѓсЂ«№╝ѕтЈЌт«╣СйЊ№╝ЅсЂДсЂЎсђѓ
- сѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│тЈЌт«╣СйЊсЂїсѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│сѓњтЈЌсЂЉтЈќсѓІсЂесђЂуЅ╣т«џсЂ«СйюућесЂїУхисЂЊсЂБсЂЪсѓіуЅ╣т«џсЂ«СйюућесЂїТГбсѓЊсЂасѓісЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
- тЈЌт«╣СйЊсѓњсЃќсЃГсЃЃсѓ»сЂЌсЂдсѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│сѓњтЈЌсЂЉтЈќсѓїсЂфсЂЈсЂЎсѓІсЂесђЂуЅ╣т«џсЂ«СйюућесЂїУхисЂЊсѓІсЂЊсЂесѓњжў▓сЂёсЂасѓісђЂсЂѓсѓІСйюућесѓњуХЎуХџсЂЋсЂЏуХџсЂЉсѓІсЂЊсЂесЂїтЈ»УЃйсЂФсЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сЂЪсЂасЂЌсђЂсѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│тЈЌт«╣СйЊсЂФсЂ»сђЂсѓхсЃќсѓ┐сѓцсЃЌсЂїУцЄТЋ░тГўтюесЂЌсЂдсЂёсЂдсђЂсЂЮсѓїсЂъсѓїуЋ░сЂфсѓІтй╣тЅ▓сѓњТїЂсЂБсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂеADHDТ▓╗уЎѓУќг
сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂеADHDТ▓╗уЎѓУќгсЂ«ТѕљтѕєсЂ«ТДІжђасЂ»сђЂсѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│сЂежЮътИИсЂФС╝╝сЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂЮсЂ«сЂЪсѓЂсђЂсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂеADHDТ▓╗уЎѓУќгсЂ«СИАТќ╣сЂесѓѓсђЂсѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│тЈЌт«╣СйЊсЂеухљтљѕсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂЙсЂЪсЂ»ADHDТ▓╗уЎѓУќгсЂ«ТѕљтѕєсЂїсѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│тЈЌт«╣СйЊсЂеухљсЂ│сЂцсЂёсЂдсЂЌсЂЙсЂєсЂесђЂт«ЪжџЏсЂ«сѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│сЂ»тЈЌт«╣СйЊсЂеухљсЂ│сЂцсЂЈсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂфсЂЈсЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сЂцсЂЙсѓісђЂADHDТ▓╗уЎѓУќгсЂ»сђЂсѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│сЂїтЈЌт«╣СйЊсЂеухљсЂ│сЂцсЂЈсЂЊсЂесѓњжў╗ТГбсЂЌсђЂсѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│сЂ«СйюућесѓњТЅЊсЂАТХѕсЂЎсЂ«сЂДсЂЎсђѓсЂЮсЂ«сЂЊсЂесЂДсђЂADHDсЂ«ТїЎтІЋсЂїт«Ѕт«џсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
ADHDТ▓╗уЎѓУќг№╝ЈтљЉу▓ЙуЦъТђДУќгсЂ«Сйюуће
ADHDсЂ«С║║сЂїсђЂADHDТ▓╗уЎѓУќгсѓњжБ▓сѓђсЂесђЂУАїтІЋсЂет┐ЃсЂФУљйсЂАуЮђсЂЇсЂїТѕ╗сѓісђЂжЏєСИГсЂДсЂЇсѓІсѓѕсЂєсЂФсЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓсЂЌсЂІсЂЌADHDсѓњсѓѓсЂБсЂдсЂёсЂфсЂёС║║сЂїжБ▓сѓђсЂесђЂADHDсЂ«сѓѕсЂєсЂфуЌЄуіХсЂїуЈЙсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
ADHDТ▓╗уЎѓУќгсЂасЂЉсЂДсЂфсЂЈсђЂтљЉу▓ЙуЦъСйюућесЂ«сЂѓсѓІУќгсЂ»сђЂADHDсЂ«уЌЄуіХсѓњТћ╣тќёсЂЎсѓІСйюућесѓњУхисЂЊсЂЌсЂЙсЂЎсЂїсђЂADHDсЂДсЂ»сЂфсЂёС║║сЂїжБ▓сѓђсЂесђЂуЋ░тИИсЂфУ║ЂуіХТЁІ№╝ѕУдџсЂЏсЂётЅцсЂ«сѓѕсЂєсЂфСйюуће№╝Ѕсѓњт╝ЋсЂЇУхисЂЊсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ«Сйюуће
тЂЦт║исЂфС║║сЂ«СйЊтєЁсЂДсђЂсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂїсѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│тЈЌт«╣СйЊсЂеухљсЂ│сЂцсЂЈсЂесђЂуДЂжЂћсѓњТ┤╗тІЋуџёсЂФсЂЎсѓІуЦъухїС╝ЮжЂћуЅЕУ│фсЂ«сЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│сѓёсЃјсЃФсѓбсЃЅсЃгсЃісЃфсЃ│сЂ«тѕєТ│їсѓњтбЌтіасЂЋсЂЏсђЂуДЂжЂћсЂ«Уё│сѓёСйЊсЂ»Т┤╗уЎ║сЂФсЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│сЂесЃјсЃФсѓбсЃЅсЃгсЃісЃфсЃ│сЂ«СйюућесЂФсѓѕсЂБсЂдсђЂсѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сѓњжБ▓сѓђсЂетцюуюасѓїсЂфсЂЈсЂфсѓІС║║сЂїсЂёсѓІСИђТќ╣сЂДсђЂсѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сѓњжБ▓сѓђсЂесђЂсЂ╗сЂБсЂет┐ЃсЂїУљйсЂАуЮђсЂЈС║║сѓѓсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сЂ»жБЪтЊЂсЂДсЂЎсЂІсѓЅсђЂADHDУќгсЂеТ»ћУ╝ЃсЂЌсЂЪсѓЅсЂџсЂБсЂеуЕЈсѓёсЂІсЂФуДЂжЂћсЂ«у▓ЙуЦъуіХТЁІсЂФСйюућесЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
сЂфсЂісђЂсЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│сЂ»тцџсЂЉсѓїсЂ░тцџсЂёТќ╣сЂїУЅ»сЂёсѓЈсЂЉсЂДсЂ»сЂфсЂЈсђЂтѕєТ│їсЂЋсѓїжЂјсЂјсѓІсЂесђЂТ░ЌтѕєсѓњТѓфсЂЈсЂЋсЂЏсЂЪсѓісђЂУљйсЂАуЮђсЂЇсЂїтц▒сѓЈсѓїсђЂУёѕТІЇсЂїТЌЕсЂЈсЂфсѓісђЂсЃЉсЃІсЃЃсѓ»уЌЄуіХсѓњУхисЂЊсЂЎсЂЊсЂесЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂїADHDсЂФті╣сЂЈсЂеУђЃсЂѕсѓЅсѓїсѓІуљєућ▒

№╝ѕУБЈС╗ўсЂЉсЂесЂфсЂБсЂдсЂёсѓІуаћуЕХУФќТќЄсЂ»сђЂТюђтЙїсЂФтЈѓУђЃТќЄуї«сЂесЂЌсЂдСИђУдДсЂФсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎ№╝Ѕ
1. сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ»сЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│сЂесЃјсЃФсѓбсЃЅсЃгсЃісЃфсЃ│сѓњтбЌсѓёсЂЎ
ADHAсЂ«Т▓╗уЎѓсЂФућесЂёсѓЅсѓїсѓІтї╗УќгтЊЂсЂ«сЂ╗сЂесѓЊсЂЕсЂЎсЂ╣сЂдсЂїсЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│сЂесЃјсЃФсѓбсЃЅсЃгсЃісЃфсЃ│тђцсѓњтбЌсѓёсЂЎСйюућесЂ«сЂѓсѓІтљЉу▓ЙуЦъТђДсЂ«уЅЕУ│фсЂДсЂЎсђѓ
сЂЮсЂЌсЂдсђЂсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ»сђЂсЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│сЂесЃјсЃФсѓбсЃЅсЃгсЃісЃфсЃ│сЂ«СИАТќ╣сѓњтбЌсѓёсЂЎсђЂСИќуЋїсЂДТюђсѓѓТЎ«тЈісЂЌсЂдсЂёсѓІтљЉу▓ЙуЦъТђДуЅЕУ│фсЂ«№╝ЉсЂцсЂДсЂЎсђѓсЂЮсЂ«жЂјуеІсЂДсђЂсѓбсѓ╗сЃЂсЃФсѓ│сЃфсЃ│сЂесѓ╗сЃГсЃѕсЃІсЃ│сѓѓтбЌсѓёсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
т«ЪжџЏсђЂADHDТ▓╗уЎѓУќгсЂ«сЃфсѓ┐сЃфсЃ│сЂФсЂ»сђЂтцџсЂЈсЂ«сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂїтљФсЂЙсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
2. сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ»тЅЇжаГуџ«У│фсЂ«сЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│СйютІЋТђДТЕЪУЃйсѓњТГБтИИтїќсЂЎсѓІ
сђјТгДтиъуЦъухїу▓ЙуЦъУќгуљєтГд№╝ѕEuropean Neuropsychopharmacology№╝ЅсђЈсЂФуЎ║УАесЂЋсѓїсЂЪуаћуЕХсЂФсѓѕсЂБсЂдсђЂсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂїтЅЇжаГуџ«У│фсЂ«сЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│СйютІЋТђДТЕЪУЃйсѓњТГБтИИтїќсЂЌсђЂADHDсЂ«уЅ╣тЙ┤сЂДсЂѓсѓІТ│еТёЈТгажЎЦсЂеУфЇуЪЦтцЅтїќсѓњТћ╣тќёсЂЎсѓІтЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓІсЂЊсЂесЂїуц║сЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЊсЂ«уаћуЕХсЂДсЂ»сђЂсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂїтї╗УќгтЊЂсЂетљїТДўсЂФсЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│тђцсѓњТГБтИИтїќсЂЋсЂЏсЂЪсЂЊсЂесЂїта▒тЉісЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
3. сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ»У╗йт║дсЂ«ADHDсѓњТћ╣тќёсЂЎсѓІ
сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сѓњтљФТюЅсЂЎсѓІсЂіУїХ№╝ѕу┤ЁУїХсѓёуиЉУїХ№╝ЅсЂїсђЂУ╗йт║дсЂ«ADHDсѓњсѓѓсЂБсЂдсЂёсѓІС║║сѓњт»ЙУ▒АсЂФсЂЌсЂЪуаћуЕХсЂДсђЂуќ▓ті┤ТёЪсЂ«У╗йТИЏсђЂУЄфС┐АсђЂсѓёсѓІТ░ЌсђЂТ│еТёЈтіЏсђЂУГдТѕњт┐ЃсђЂті╣ујЄсђЂжЏєСИГтіЏсђЂУфЇуЪЦтіЏсѓњжФўсѓЂсЂЪсЂесђЂта▒тЉісЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЊсЂ«уаћуЕХУђЁсЂ»сђЂсЂіУїХсЂ«ТЉѓтЈќсЂїТѕљС║║сЂ«ADHDсЂ«ТюЅті╣сЂфуЕЇТЦхуџёТ▓╗уЎѓТ│ЋсЂДсЂѓсѓІтЈ»УЃйТђДсѓњуц║тћєсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
4. сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ»т╝иУ┐ФТђДжџют«│Т▓╗уЎѓсЂФТюЅті╣
т╝иУ┐ФТђДжџют«│№╝ѕOCD№╝ЅсЂ«Т▓╗уЎѓсЂФсЂесЂБсЂдсђЂADHDТ▓╗уЎѓУќгсЂ«сЃЄсѓГсѓ╣сЃѕсЃГсѓбсЃ│сЃЋсѓДсѓ┐сЃЪсЃ│№╝ѕсЃЄсѓГсѓ╗сЃЅсЃфсЃ│№╝ЅсЂесѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ«сЂЕсЂАсѓЅсЂїТюЅті╣сЂІсѓњТцюУе╝сЂЎсѓІсЂЪсѓЂсЂ«уаћуЕХсЂїсѓ╣сѓ┐сЃ│сЃЋсѓЕсЃ╝сЃЅтцДтГдсЂФсѓѕсЂБсЂдт«ЪТќйсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЮсѓѓсЂЮсѓѓтї╗УќгтЊЂсЂесѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ«сЂЕсЂАсѓЅсЂФті╣ТъюсЂїсЂѓсѓІсЂ«сЂІуаћуЕХсЂЋсѓїсѓІсЂЈсѓЅсЂёсђЂТ»ћУ╝Ѓт»ЙУ▒АсЂесЂЌсЂдТцюУејсЂЎсѓІСЙАтђцсЂїсЂѓсѓІсЂЈсѓЅсЂёті╣ТъюсЂФТюЪтЙЁсЂДсЂЇсѓІсЂесЂёсЂєсЂЊсЂесЂасЂеТђЮсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
5. сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ»сѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│тЈЌт«╣СйЊсЂ«СйюућесѓњТЅЊсЂАТХѕсЂЎ
сђїсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂїсѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│тЈЌт«╣СйЊсЂ«СйюућесѓњТЅЊсЂАТХѕсЂЎсѓѕсЂєсЂФ
уДЂжЂћсЂ«Уё│сЂДСйюуће№╝ѕсѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│тЈЌт«╣СйЊТІ«ТіЌСйюуће№╝ЅсЂЎсѓІсЂесЂёсЂєС║Іт«ЪсЂїсђЂ
ADHDсЂ«УЄет║іУе║уЎѓсЂДсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сѓњСй┐ућесЂЎсѓІТйютюеуџёсЂфтѕЕуѓ╣сЂасђЇ
сЂесђЂсЂЎсѓІУФќТќЄсЂїсђЂ2014т╣┤сЂ«сђју▓ЙуЦъУќгуљєтГдсѓИсЃБсЃ╝сЃісЃФ№╝ѕJournal of Psychopharmacology№╝ЅсђЈсЂФТј▓У╝ЅсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
6. сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ»ADHDТ▓╗уЎѓУќгсЂеСйЊтєЁТЕЪт║ЈсЂїжАъС╝╝
ADHDТ▓╗уЎѓУќгсЂ«сЃАсЃЂсЃФсЃЋсѓДсЃІсЃЄсЃ╝сЃѕсЂесѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ»сђЂСИАТќ╣сЂесѓѓ№╝ЉТЎѓжќЊС╗ЦтєЁсЂФСйюућесЂїУхисЂЊсѓісђЂ4ТЎѓжќЊС╗ЦтєЁсЂФСйюућесЂїТХѕТ╗ЁсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЊсЂ«СИАУђЁсЂ»сђЂжЮътИИсЂФжАъС╝╝сЂЌсЂЪтљИтЈјсЂеС╗БУгЮсЂ«сЃЌсЃГсѓ╗сѓ╣сђЂСйЊтєЁТЕЪт║ЈсђЂтЅ»тЈЇт┐юсѓњсѓѓсЂБсЂдсЂёсѓІсЂЊсЂесЂїта▒тЉісЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ«СйюућесЂ«уеІт║дсЂ»сЃњсЃѕсЂФсѓѕсЂБсЂдуЋ░сЂфсѓІ

1.ADHDсЂ«тјЪтЏасЂ»сЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│СИЇУХ│сЂасЂЉсЂ»сЂфсЂё
ADHAсЂїУхисЂЊсѓІтјЪтЏасЂ»сЂ▓сЂесЂцсЂДсЂ»сЂѓсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓ
- СИ╗сЂФУАесѓїсЂдсЂёсѓІADHDсЂ«уЌЄуіХ
- жЂ║С╝ЮтГљсЂ«тй▒жЪ┐
- СйЊтєЁсЂ«сЃЅсЃ╝сЃЉсЃЪсЃ│сѓёсЃјсЃФсѓбсЃЅсЃгсЃісЃфсЃ│сЂ«жЄЈсѓётѕєТ│їсЂ«уіХТЁІ
сЂФсѓѕсЂБсЂджЂЕсЂЎсѓІУќгсѓёТ▓╗уЎѓТќ╣Т│ЋсЂїуЋ░сЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сЂЮсЂ«сЂЪсѓЂсђЂсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ«ті╣ТъюсЂФти«сЂїућЪсЂўсѓІсЂЊсЂесЂїТЃ│т«џсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
2.сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂеСйЊУ│фсЂ«уЏИТђД
ТгАсЂ«УдЂтЏасЂФсѓѕсЂБсЂдсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂФт»ЙсЂЎсѓІтЈЇт┐юсЂ»уЋ░сЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓсЂЮсЂ«сЂЪсѓЂсђЂтЁесЂдсЂ«ADHDсЂ«С║║сЂФсѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сЂїті╣ТъюсЂїсЂѓсѓІсЂесЂ»у┤ёТЮЪсЂДсЂЇсЂЙсЂЏсѓЊсђѓ
- сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сѓњтѕєУДБсЂДсЂЇсѓІУЃйтіЏ
- сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂїсЂЕсЂ«сѓбсЃЄсЃјсѓисЃ│тЈЌт«╣СйЊсЂеухљсЂ│сЂцсЂЈсЂІ
- сЂЕсѓїсЂасЂЉтцџсЂЈсЂ«тЈЌт«╣СйЊсЂеухљсЂ│сЂцсЂЈсЂІ
3.жБЪтЊЂСИГсЂ«сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│жЄЈ
сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ«тљФТюЅжЄЈсЂ»сђЂсЂЮсѓїсЂъсѓїсЂ«жБЪтЊЂсѓёжБ▓сЂ┐уЅЕсЂФсѓѕсЂБсЂдуЋ░сЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓсЂЮсЂ«сЂЪсѓЂсђЂтї╗УќгтЊЂсЂеуЋ░сЂфсѓітИИсЂФСИђт«џжЄЈсѓњсѓ│сЃ│сѓ╣сѓ┐сЃ│сЃѕсЂФТЉѓсѓіуХџсЂЉсѓІсЂЊсЂесЂ»жЏБсЂЌсЂёсЂеУеђсЂѕсЂЙсЂЎсђѓ
СЙІсЂѕсЂ░сђЂу┤ЁУїХсѓёуиЉУїХсЂ»сЂЕсѓїсЂасЂЉжЋисЂёТЎѓжќЊсђЂУїХУЉЅсѓњсЂіТ╣»сЂФсЂцсЂЉсЂдсЂісЂёсЂЪсЂІсЂФсѓѕсЂБсЂдТійтЄ║сЂЋсѓїсѓІсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ«жЄЈсЂФти«сЂїућЪсЂўсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЙсЂЪсђЂУїХУЉЅсѓёсѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝У▒єсЂ»УЄфуёХжБЪтЊЂсЂДсЂЎсЂІсѓЅсђЂтљїсЂўсЃќсЃЕсЃ│сЃЅсЂ«УїХУЉЅсѓёУ▒єсЂДсЂѓсЂБсЂдсѓѓсђЂсЂЮсЂ«т╣┤сЂ«тцЕтђЎсѓётіатиЦжЂјуеІсЂ«жЂЋсЂёсЂФтидтЈ│сЂЋсѓїсђЂтИИсЂФтљїсЂўсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ«жЄЈсѓњтљФсѓЊсЂДсЂёсѓІсЂесЂ»УеђсЂѕсЂЙсЂЏсѓЊсђѓ
сѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сЂДсЂ»т╝▒сЂЎсЂјсЂдсЂЌсЂЙсЂєС║║сѓѓсЂёсѓІсЂІсѓѓсЂЌсѓїсЂЙсЂЏсѓЊсђѓ
тЈѓУђЃ№╝џсђјСИђУѕгуџёсЂфжБ▓ТќЎсЂФтљФсЂЙсѓїсѓІсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│жЄЈсђЈ
4.сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│тцџжЄЈТЉѓтЈќсЂ«Тѓфтй▒жЪ┐
С╗ќсЂ«тї╗УќгтЊЂсЂеСИђуињсЂФсѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сѓњжБ▓сѓђсЂесђЂТѓфсЂёСйюућесЂїтЄ║сЂдсЂЌсЂЙсЂєсЂЊсЂесЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓСЙІсЂѕсЂ░сђЂт┐ЃТЕЪУЃйсѓёУАђтюДсђЂУё│ТЕЪУЃйсѓёТЃЁуињсЂИсЂ«Тѓфтй▒жЪ┐сЂДсЂЎсђѓ
сѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сЂ«тЂЦт║исЂИсЂ«Тў»жЮъсЂФсЂцсЂёсЂдсЂ» сђјсѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сЂ»СйЊсЂФУЅ»сЂёсЂ«№╝ЪТѓфсЂёсЂ«№╝ЪсђЈ сѓњУфГсѓЊсЂДсЂЈсЂасЂЋсЂёсЂГсђѓ
5.ТюфТѕљуєЪтЁљуФЦсЂ«сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│ТЉѓтЈќсЂ«тЋЈжАї

СИђУѕгуџёсЂФсђЂТѕљжЋиТюЪсЂФсЂѓсѓІТюфТѕљуєЪтЁљуФЦсЂїсђЂсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сѓњуЕЇТЦхуџёсЂФТЉѓсѓІсЂЊсЂесЂ»тІДсѓЂсѓЅсѓїсЂЙсЂЏсѓЊсђѓ
ТЌЦТюгсѓѓу▒│тЏйсѓѓсђЂуЅ╣сЂФтГљСЙЏсЂ«сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│ТЉѓтЈќжЄЈсЂФТўјуб║сЂфтѕХжЎљсѓњУеГсЂЉсЂдсЂёсЂЙсЂЏсѓЊсЂїсђЂсѓФсЃісЃђсЂФсЂ»сѓгсѓцсЃЅсЃЕсѓцсЃ│сЂїсЂѓсѓісђЂТЌЦТюгсЂ«тјџућЪті┤тЃЇуюЂсЂ»сђЂсЂЮсѓїсѓњтЈѓУђЃсЂФсЂЎсѓІсѓѕсЂєсЂФсЂесЃЏсЃ╝сЃасЃџсЃ╝сѓИсЂФТј▓У╝ЅсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎ№╝ѕС╗ќтіЏТюгжАў№╝ЪугЉ№╝Ѕ
т╣┤жйб№╝џ
- 4№йъ6ТГ│№╝џ45 mgТюфТ║ђ
- 7№йъ9ТГ│№╝џ62 mgТюфТ║ђ
- 10№йъ12ТГ│№╝џ85 mgТюфТ║ђ
сЂДсѓѓсђЂсЂЊсѓїсЂ»ADHDсЂДсЂ»сЂфсЂётЁљуФЦсЂ«сЂЪсѓЂсЂ«сѓгсѓцсЃЅсЃЕсѓцсЃ│сЂДсЂЎсЂІсѓЅсђЂADHDсЂ«тЁљуФЦсЂФсЂцсЂёсЂдсЂ»сђЂС┐ЮУГиУђЁсЂ«тѕцТќГсЂїт┐ЁУдЂсЂФТђЮсѓЈсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
УќгсѓњжБ▓сЂЙсЂЏсѓІсѓѕсѓісѓѓсђЂ1ТЌЦсЂФ№╝њ№йъ№╝ЊТЮ»сЂ«сѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сЂїтй╣сЂФуФІсЂцсЂІсѓѓсЂЌсѓїсЂфсЂёсЂеТђЮсѓЈсѓїсЂЪсЂфсѓЅсђЂт┐ЁсЂџСИ╗Т▓╗тї╗сЂесЂћуЏИУФЄсЂЈсЂасЂЋсЂёсђѓсЂЮсЂЌсЂдсђЂсЂітГљсЂЋсѓЊсЂФсѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝жБ▓сЂЙсЂЏсѓІсЂЊсЂесѓњжЂИТіъсЂЌсЂЪта┤тљѕсЂФсЂ»сђЂтї╗УќгтЊЂсѓњжБ▓сЂЙсЂЏсЂЪТЎѓсЂетљїсЂўсѓѕсЂєсЂФсЂітГљсЂЋсѓЊсѓњТ│еТёЈТи▒сЂЈУдІт«ѕсЂБсЂдсЂЈсЂасЂЋсЂёсђѓ
ТюфТѕљуєЪтЁљуФЦсЂДсЂЎсЂІсѓЅсђЂт░ЉжЄЈсЂ«сѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂДсѓѓтцДсЂЇсЂфтцЅтїќсѓњсѓѓсЂЪсѓЅсЂЎтЈ»УЃйТђДсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓТћ╗ТњЃТђДсѓёСИЇуюасѓёСИІуЌбсђЂжаГуЌЏсЂфсЂЕсђЂсѓѓсЂЌуЈЙсѓїсѓІсѓѕсЂєсЂДсЂЌсЂЪсѓЅсђЂуЏ┤сЂљсЂФСИ╗Т▓╗тї╗сЂФта▒тЉісЂЌсЂдсЂЈсЂасЂЋсЂёсђѓ
тГдТаАсЂ«ТѕљуИЙсѓѓтцДтѕЄсЂДсЂЎсЂїТюгС║║сЂ«УЄфти▒Уѓ»т«џТёЪсЂ»сѓѓсЂБсЂетцДтѕЄ

ТюђУ┐ЉсЂДсЂ»сђЂADHDсЂ«Т▓╗уЎѓсЂФсЂ»сђЂсЂЎсЂљсЂФУќгсѓњтЄдТќ╣сЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїТГБсЂЌсЂёжЂИТіъсЂДсЂѓсѓІсЂІсЂ«сѓѕсЂєсЂфжбеТй«сЂДсЂЎсЂїсђЂжЮътИИсЂФУ┐ЉУдќую╝уџёсЂДТйютюеуџёсЂфТДўсђЁсЂфтЇ▒жЎ║сѓњсЂ»сѓЅсѓЊсЂДсЂёсѓІухљУФќсЂДсЂѓсѓІсѓѕсЂєсЂФТёЪсЂўсЂЙсЂЎсђѓ
ТѕљжЋиТюЪсЂ«Уё│сЂИсѓбсЃ│сЃЋсѓДсѓ┐сЃЪсЃ│у│╗сЂ«сђЂтљЉу▓ЙуЦъУќгу│╗сЂ«сђЂж║╗Уќгу│╗сЂ«УќгсѓњСИјсЂѕсѓІсЂЊсЂесЂ«тЙїжЂ║уЌЄсЂасЂЉсЂДсЂфсЂЈсђЂтГљСЙЏсЂ«УЄфти▒Уѓ»т«џТёЪсѓёУЄфт░іТёЪТЃЁсѓњтѓисЂцсЂЉсѓІухљТъюсЂФсЂфсѓЅсЂфсЂёсЂІт┐ЃжЁЇсЂДсЂЎсђѓ
УќгсѓњжБ▓сѓЂсЂ░УЄфтѕєсЂїсђїуЌЁТ░ЌсђЇсЂДсЂѓсѓІсЂетГљСЙЏсЂ»ТђЮсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂДсѓѓсѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сЂфсѓЅУЄфтѕєсЂ«УАїтІЋсѓњуЋ░тИИсЂасЂеТёЪсЂўсЂџсЂФТИѕсЂ┐сЂЙсЂЎсђѓт░ЉсЂЌт╝исЂётђІТђДсЂЈсѓЅсЂёсЂФТђЮсЂѕсѓІсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂёсЂДсЂЌсѓЄсЂєсЂІсђѓсЂЮсЂ«УфЇУГўсЂ»сђЂтГљСЙЏсЂ«УЄфти▒Уѓ»т«џТёЪсѓёУЄфт░іТёЪТЃЁсЂФтцДсЂЇсЂфжЂЋсЂёсѓњућЪсѓђсѓѕсЂєсЂФТђЮсЂєсЂ«сЂДсЂЎсђѓ
ADHDТ▓╗уЎѓУќгсЂ»сѓбсЃ│сЃЋсѓДсѓ┐сЃЪсЃ│у│╗сЂ«УќгсЂДсЂЎсђѓсѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сЂ»жБ▓ТќЎсЂДсЂЎсђѓ
ТйютюеуџёсЂФтЇ▒жЎ║сЂфУќгсЂФСЙЮтГўсЂЎсѓІтЅЇсЂФсђЂсѓ│сЃ╝сЃњсЃ╝сѓёу┤ЁУїХсђЂуиЉУїХсђЂсЃђсЃ╝сѓ»сЃЂсЃДсѓ│сЃгсЃ╝сЃѕсЂфсЂЕсѓњУЕдсЂЎсЂЊсЂесѓњТцюУејсЂёсЂЪсЂасЂЉсѓїсЂ░сЂеТђЮсѓЈсЂџсЂФсЂ»сЂёсѓЅсѓїсЂЙсЂЏсѓЊсђѓ
сЂАсЂфсЂ┐сЂФсЂЊсѓЊсЂфТќ╣Т│ЋсѓѓADHDсЂФті╣ТъюсЂѓсЂБсЂЪсЂесЂЎсѓІта▒тЉісѓѓсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓсђјућўсЂёсѓѓсЂ«Тг▓Т▒ѓсѓњуДЉтГдуџёсЂФТіЉсЂѕсѓІтИЃтЏБсЂБсЂдсЂЕсѓЊсЂфтИЃтЏБ№╝ЪсђЈ
сѓйсЃЋсѓБсѓбсѓдсЃЃсѓ║сЃ╗сѓцсЃ│сѓ╣сЃєсѓБсЃєсЃЦсЃ╝сЃѕсЂІсѓЅсЂ«сЂћТЈљТАѕ

тЁгУфЇсЃЏсЃфсѓ╣сЃєсѓБсЃЃсѓ»сЃ╗сЃўсЃФсѓ╣сѓ│сЃ╝сЃЂсЂ»сђЂжБЪС║ІсЂасЂЉсЂДсЂфсЂЈсђЂсЂѓсЂфсЂЪсѓњтЈќсѓіти╗сЂЈТДўсђЁсЂфсЂЊсЂе№╝ѕуњ░тбЃсђЂС╗ЋС║ІсђЂт«ХТЌЈсђЂС║║жќЊжќбС┐ѓсЂфсЂЕ№╝ЅсѓњУђЃТЁ«сЂЌсЂдсђЂсЃЌсЃГсѓ░сЃЕсЃасЂФтЈЇТўасЂЋсЂЏсђЂсЂѓсЂфсЂЪсЂїсђЂсЂфсѓісЂЪсЂёсЂѓсЂфсЂЪсЂФсЂфсѓїсѓІсѓѕсЂєсѓ│сЃ╝сЃЂсЃ│сѓ░сѓњТЈљСЙЏсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
сЃўсЃФсѓ╣сѓ│сЃ╝сЃЂсЂесђЂСИђт║дсђЂУЕ▒сѓњсЂЌсЂдсЂ┐сЂЙсЂЏсѓЊсЂІ№╝Ъ
сЃЌсЃЕсѓцсЃЎсЃ╝сЃѕсЃ╗сЃўсЃФсѓ╣сѓ│сЃ╝сЃЂсЃ│сѓ░сЃ╗сЃЌсЃГсѓ░сЃЕсЃасЂФсЂцсЂёсЂд
сЂіТ░ЌУ╗йсЂФсЂћуЏИУФЄсЂЈсЂасЂЋсЂёсђѓ
тѕЮтЏъуЏИУФЄсѓњуёАТќЎсЂДсЂітЈЌсЂЉсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сЂѓсѓІсЂёсЂ»сђЂсѓйсЃЋсѓБсѓбсѓдсЃЃсѓ║сЃ╗сѓцсЃ│сѓ╣сЃєсѓБсЃєсЃЦсЃ╝сЃѕсЂ«сЃъсѓцсЃ│сЃЅсЃ╗сЃюсЃЄсѓБсЃ╗сЃАсЃЄсѓБсѓисЃ│УгЏт║Дсѓ╗сЃФсЃЋсЃЅсѓ»сѓ┐сЃ╝сѓ│сЃ╝сѓ╣сЂДсЂ»сђЂсЂѓсЂфсЂЪсЂїжБЪсѓњжђџсЂЌсЂдсЂћУЄфУ║ФсЂ«СИ╗Т▓╗тї╗№╝ѕсѓ╗сЃФсЃЋсЃЅсѓ»сѓ┐сЃ╝№╝ЅсЂФсЂфсѓІсЂЪсѓЂсЂФсђЂт┐ЁУдЂсЂфуЪЦУГўсЂесѓ╣сѓГсЃФсѓњТЋЎсЂѕсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
Тќ░тГдТюЪсЂ»сђЂТ»јт╣┤3ТюѕсЂе9ТюѕсЂДсЂЎсђѓУгЏт║ДсЂДсЂіС╝џсЂёсЂЌсЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓ

т┐ЃсЂеСйЊсѓњсЂцсЂфсЂёсЂДтЂЦт║исЂет╣ИсЂЏсѓњТЅІсЂФтЁЦсѓїсѓІ
сЃІсЃЦсЃ╝сѓ╣сЃгсѓ┐сЃ╝сЂ«сЂћуЎ╗жї▓сЂ»сђЂсЂЊсЂАсѓЅсЂІсѓЅ
ух▒тљѕжБЪжцітГд№╝ѕсЃЏсЃфсѓ╣сЃєсѓБсЃЃсѓ»ТаёжцітГд№╝ЅтєітГљсЂїуёАТќЎсЃђсѓдсЃ│сЃГсЃ╝сЃЅсЂДсЂЇсЂЙсЂЎ
тЈѓУђЃТќЄуї«№╝џ
- РђюCaffeine regulates frontocorticostriatal dopamine transporter density and improves attention and cognitive deficits in an animal model of attention deficit hyperactivity disorderРђЮ, Pablo Pandolfoab Nuno, J. Machadob Attila K├Хfalvib Reinaldo, N.Takahashia Rodrigo, A.Cunhabc, European Neuropsychopharmacology, Volume 23, Issue 4, April 2013, Pages 317-328, https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2012.04.011
- РђюTea consumption maybe an effective active treatment for adult attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)РђЮ, Kezhi Liu Xuemei, Liang Weihong Kuang, Medical Hypotheses, Volume 76, Issue 4, April 2011, Pages 461-463, https://doi.org/10.1016/j.mehy.2010.08.049
- РђюDouble-blind study of dextroamphetamine versus caffeine augmentation for treatment-resistant obsessive-compulsive disorderРђЮ, Koran LM, Aboujaoude E, Gamel NN, J Clin Psychiatry. 2009 Nov;70(11):1530-5. doi: 10.4088/JCP.08m04605. Epub 2009 Jun 30
- РђюOstracising caffeine from the pharmacological arsenal for attention-deficit hyperactivity disorder–was this a correct decision? A literature reviewРђЮ, Ioannidis K, Chamberlain SR, M├╝ller U, J Psychopharmacol. 2014 Sep;28(9):830-6. doi: 10.1177/0269881114541014. Epub 2014 Jul 1
- РђюNew Developments on the Adenosine Mechanisms of the Central Effects of Caffeine and Their Implications for Neuropsychiatric DisordersРђЮ, Ferr├Е S, D├Гaz-R├Гos M, Salamone JD, Prediger RD, J Caffeine Adenosine Res. 2018 Dec 1;8(4):121-131. doi: 10.1089/caff.2018.0017. Epub 2018 Dec 7.
- РђюCaffeine Frequently Asked QuestionsРђЮ, October 2011, Information for Parents on Caffeine in Energy Drinks
- РђюCaffeine ChartРђЮ, Center for Science in the Public Interest
- сђїжБЪтЊЂсЂФтљФсЂЙсѓїсѓІсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ«жЂјтЅ░ТЉѓтЈќсЂФсЂцсЂёсЂдQ№╝єA №йъсѓФсЃЋсѓДсѓцсЃ│сЂ«жЂјтЅ░ТЉѓтЈќсЂФТ│еТёЈсЂЌсЂЙсЂЌсѓЄсЂє№йъсђЇ тјџућЪті┤тЃЇуюЂ
сѓйсЃЋсѓБсѓбсѓдсЃЃсѓ║сЃ╗сѓцсЃ│сѓ╣сЃєсѓБсЃєсЃЦсЃ╝сЃѕ – сЃЏсЃфсѓ╣сЃєсѓБсЃЃсѓ»сЃўсЃФсѓ╣сѓ│сЃ╝сЃЂсЃ│сѓ░