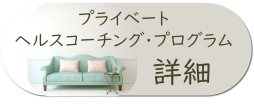バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。
心と体をつなぐホリスティックな食事法について、
ニュースレター登録者限定のキャンペーン情報等も配信しています。
ご登録は、こちらから
もれなく統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます
目次
最近、ナイアシンが長寿タンパク質サーチュインに必要な栄養素だという情報が広まり、ナイアシンのサプリメントに人気が集まっているという話を聞きました。
ナイアシンのサプリメントの安易な服用には危険が伴います。
そこで、今回は、ナイアシンについてお伝えすることにしました。かなり長い記事になっていますが、それだけナイアシンの研究が行われているということです。
最後までがんばって読んでいただけたら嬉しいです(笑)
ナイアシンの食品摂取基準(2020)
ナイアシンは、食品から直接得られるだけでなく、アミノ酸の一種トリプトファンから体内でも合成され、トリプトファン60mgがナイアシン1mgになると推計されます。そのため、食品に含まれているトリプトファンの量も考慮して、ナイアシン当量として表示されることが一般的です。
次の数値はナイアシン当量(トリプトファンから変換される推定量を含む)の基準です。
- 1日の必要量・・・女性:9~10mg、男性:13mg
- 1日の推奨量・・・女性:11~12mg、男性:15mg
- 1日の限界量・・・女性:250mg、男性:300~350mg
ナイアシンは小腸から吸収されます。
食品中のナイアシンの利用効率は約60%と推定されています。
ナイアシンの性質
ビタミンB群という言葉を耳にしたことがある人は多いでしょう。B”群”というくらいですから、ビタミンBにはたくさんの種類があります。
ナイアシンは、ビタミンB3とも呼ばれる、ビタミンB群に含まれる水溶性ビタミンです。
そして、ナイアシンは、次の化合物の総称でもあります。
- ニコチン酸
- ニコチン酸アミド
- ニコチン酸アミドリボシド
- など
ニコチン酸は、たばこに含まれているニコチンと名前が似ていますが、まったく異なる物質です。
ナイアシンは生命維持に不可欠
ナイアシンは、体内で生命維持に欠かせないニコチンアミド補酵素(NAD)を作るために使用されます。
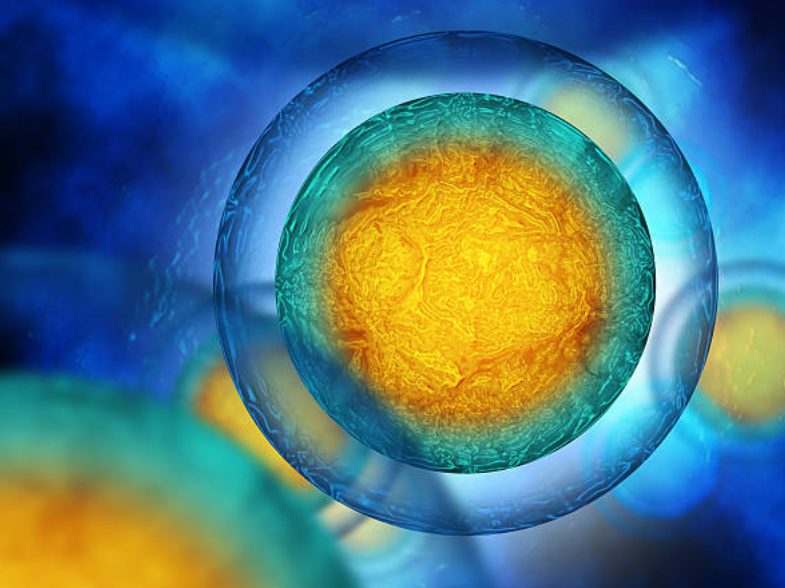
NAD(ニコチンアミド補酵素)には、酸化型のNAD+ と還元型の NADH(還元型NAD)があります。
NAD+ と NADH は、あなたの体の元気の素 ATP から P(リン酸)を受け取って、NADP(NADリン酸)+ や NADPH(還元型NADP)になったり、戻ったりを繰り返して、リサイクルされています。
体内にある400以上の酵素は、電子の授受(酸化還元反応)によって機能しています。生物エネルギー(元気)の大部分は、細胞間の電子の移動(酸化還元反応)によって生まれているのです。
つまり、酸化と還元を繰り返しているNADとNADHは生命維持には不可欠、だから、ナイアシンは、生命にとってなくてはならない成分なんです。
ニコチンアミド補酵素(NAD)の役割
NAD とNADH には、異なる役割があります。
NADの大半は、細胞の酸化剤として電子を受け取る役割をしています。一方、NADHの大半は、細胞の還元剤として電子を提供する役割をしています。
1. NAD
細胞の酸化剤として電子を受け取る役割をしているNADは、次の栄養素などを分解して、エネルギーを生成する際に活躍します。
- 炭水化物
- 脂肪
- タンパク質
- アルコール
二日酔い予防や改善にナイアシン豊富な食べ物が良いと言われる理由です。
ただし、ヒトや動物では加齢とともに減少することが知られています。
2. NADH
細胞の還元剤として電子を提供する役割をしているNADHは、次の機能にとって不可欠な存在です。
- 脂肪酸の合成
- ステロイド(コレステロール、胆汁酸、ステロイドホルモンなど)の合成
- 他の高分子の構成要素などの合成
- 解毒と抗酸化システムの構成要素の再生
3. 両方の総合力として
NADとNADHは共に手を携えて、次の役割を果たしています。
- エネルギー(元気の素)を造る
- コレステロールを一定に保つ
- 皮膚の健康維持(お肌を炎症や外部刺激などから守る)
- 脳機能の維持向上
ニコチンアミド補酵素(NAD)のサポート機能

NADは、酵素の触媒作用を助けることで、次の機能を間接的にサポートしています。
- ストレス応答
- 細胞シグナル伝達
- ゲノムの完全性の維持
- DNA修復
- 転写制御、アポトーシス
- 細胞分化
- 抗ウイルス防御
つまり、がん予防や老化予防に関係する機能をサポートしているんです。
1. サーチュインの活性化
老化した細胞に働きかけ、DNAを修復し細胞を若返らせてくれるサーチュインと呼ばれるタンパク質は、ヒトに7種類あることが確認されていますが、サーチュインはNADに依存している酵素のひとつです。
サーチュインは、エネルギーを感知して調節でき、加齢に伴う疾患(心血管疾患、がん、認知症、関節炎など)の発症を遅らせる上で重要な役割を果たしていると考えられています。
そうしたことから、世の中では「サーチュイン」に注目が集まっていますが、ナイアシンがなければ、サーチュインはあなたの老化を遅らせたり、健康寿命を延ばしたりできないってことです。
2. 体内のカルシウム調節
体内のカルシウムの量は、カルシウムシグナル伝達という細胞間コミュニケーションによって一定に保たれています。細胞内に一時的にカルシウムを流入させたり、細胞内の貯蔵庫からカルシウムを放出したりして調節しています。
このカルシウムシグナル伝達を使ってカルシウムを調節している主要な酵素(CD38とCD157)は、NAD+ファミリーの一員です。
そして、このカルシウムシグナル伝達は、次のプロセスに関与しています。
- 神経伝達
- すい臓のβ細胞からのインスリン放出
- 筋細胞の収縮
- 免疫T細胞の活性化
また、サーチュインの活性によっても、カルシウムの流入がコントロールされていることが分かっています。
3. 細胞のスイッチを入れる作動薬

さまざまな体内機能に関与し、ほぼすべての細胞に存在する「P2Y」と呼ばれる受容体があります。
NADとNADPは、このP2Y受容体と結合することによって、各細胞のスイッチを入れて(細胞を起動させて)います。
例えば、自律神経によって管理されている内臓の働きは、あなたの意志で止めたり動かしたりすることはできません。でも、内臓の平滑筋の神経接合部にあるP2Y受容体とNADがくっつくと、内臓の働きを落ち着かせられることが判明しています。
つまり、ナイアシンは、自律神経の働きを乱すような高ストレスの状況で、体に起こるストレス反応を鎮める働きをしてくれているのです。
また、細胞の外では、NAD+は、炎症性サイトカインのように作用し、免疫細胞を活性化させることが判明しています。例えば、免疫細胞(顆粒球)のP2Y受容体とNAD+がくっつくと、スーパーオキシド(活性酸素の一種で殺菌作用がある)の産生が刺激されます。
さまざまな病気にかかりにくくなるということです。
ナイアシン欠乏症の症状

ナイアシン欠乏症の最も一般的な症状は、3つの「D」と呼ばれます。
- 日光過敏性皮膚炎(solar irritating Dermatitis)・・・皮膚疾患
- 下痢(Diarrhea)・・・消化器疾患
- 認知症(Dementia)・・・神経疾患
重度のナイアシン欠乏症の後期段階を「ペラグラ」と呼びます。「ペラグラ」とは、荒れた肌を意味するイタリア語の「ペッレ・アグラ」に由来しています。
そして、欠乏症がそのまま放置されると、4つめの「D」、死(Death)が起こります。
3つのDの症状
最初の3つのDの具体的な症状は次の通りです。
- 日光過敏性皮膚炎・・・日光にさらされた場所が厚く、鱗状になり、濃い色素沈着の発疹が対称的に発生する
- 消化器症状・・・口と舌の炎症(舌が真っ赤になる)、嘔吐、便秘、腹痛、最終的に下痢
- 神経症状・・・頭痛、無関心、疲労、うつ、意識障害、記憶喪失など
ただし、この3つの症状のすべてが現れるわけではありません。症状の現れ方は人によって異なり、例えば、皮膚症状がないナイアシン欠乏症の人もいます。
ただ、消化器系の疾患と下痢が起こると、栄養素の吸収が損なわれるため、改善が難しくなります。
ナイアシン欠乏症が起こる原因
ナイアシンが欠乏あるいは不足する原因には、病気や医薬品による影響もありますが、偏食など食生活に起因することが多いです。
1. 西洋食と栄養失調

ナイアシンは、和食の出汁に用いられる食材に多く含まれています。そのため、出汁を用いた和食を食べる機会が少ない人は、ナイアシン不足になっている可能性があります。
また、ナイアシン欠乏症は栄養失調と関連して起こることが多いです。
特に、NADの材料となるアミノ酸のトリプトファンを含む食事が不十分なことが原因ではないかと考えられています。トリプトファンを多く含む食品は『トリプトファン』をご確認ください。
例えば、次のような食生活の人にしばしば観察されます。
- ホームレス
- 神経性食欲不振の人
- 極端な食事制限をしている人
- トウモロコシを主食にして動物性タンパク質が少ない食事をしている人
最後の項目は日本人には少ないかもしれませんね。詳しくは後述します。
また、他のビタミンB群や一部の微量ミネラルが不足しても、ナイアシン欠乏症が悪化します。
2. グルタミン不足
グルタミンは、トリプトファンとニコチン酸をNAD+ に変換(合成)するために必要な栄養素です。そのため、グルタミンが不足してもナイアシン欠乏症が起こります。
グルタミンは体内でグルタミン酸から作られるアミノ酸です。
グルタミン酸は次の食品に多く含まれていますので、次の食品をあまり食べない人はナイアシンが不足している可能性があると考えられます。


3. 消化器の病気
腸内におけるナイアシンの吸収不良を起こす疾患には、次のようなものがあります。
- クローン病
- 巨大十二指腸
など
そのほか、次の疾患によってもナイアシン欠乏が起こります。
- ハートナップ病|トリプトファンの吸収不全を引き起こす遺伝性疾患
- カルチノイド症候群|カルチノイド腫瘍は、トリプトファンをナイアシン合成ではなく、セロトニン合成のために利用してしまう
- 腎臓疾患(透析患者)
- がん
- HIV/AIDS
- アルコール依存症|慢性的なアルコール摂取によって、食事からのナイアシン吸収を減少させ、トリプトファンのNAD変換を妨げます
4. 他の医薬品
トリプトファンが体内でナイアシンに合成される経路を妨害することが知られている医薬品は次の通りです。
- 免疫抑制薬(アザチオプリン/イムラン、6-メルカプトプリン)
- 抗がん剤(5-フルオロウラシル/5-FU/アドルシル)
- パーキンソン病薬(レボドパ/カルビドパ、シネメット)
- 抗結核薬イソニアジド|長期服用によってナイアシン欠乏症が起こる
体内合成ができなくなるので、食事から直接ナイアシンを摂る必要が生じるため、不足しやすくなると考えられています。
言い換えれば、上記したお薬を服用している人は、意識してナイアシン豊富な食品を食べることで欠乏症を予防できます。
欠乏症の治療
世界保健機関(WHO)は、ナイアシン欠乏症の人のナイアシンの補給には「ニコチン酸アミド」のサプリメントを用いることを推奨しています。
「ニコチン酸」のサプリメントでは、大量摂取で紅潮が起こることがあるからです。ニコチン酸の副作用については、後述する「ニコチン酸のサプリメント」の項をご確認ください。
治療ガイドラインでは、次の用法と用量のどちらかで3~4週間摂取することを推奨しています。
- 経口投与・・・1日300mgを分割して投与
- 静脈投与・・・1日100mgを分割して投与
また、ビタミンB群の複合体製剤の投与が推奨されています。(なぜビタミンB群の複合体投与が必要なのかについては、『ビタミンB群』をご参照ください。)
がんとの関係
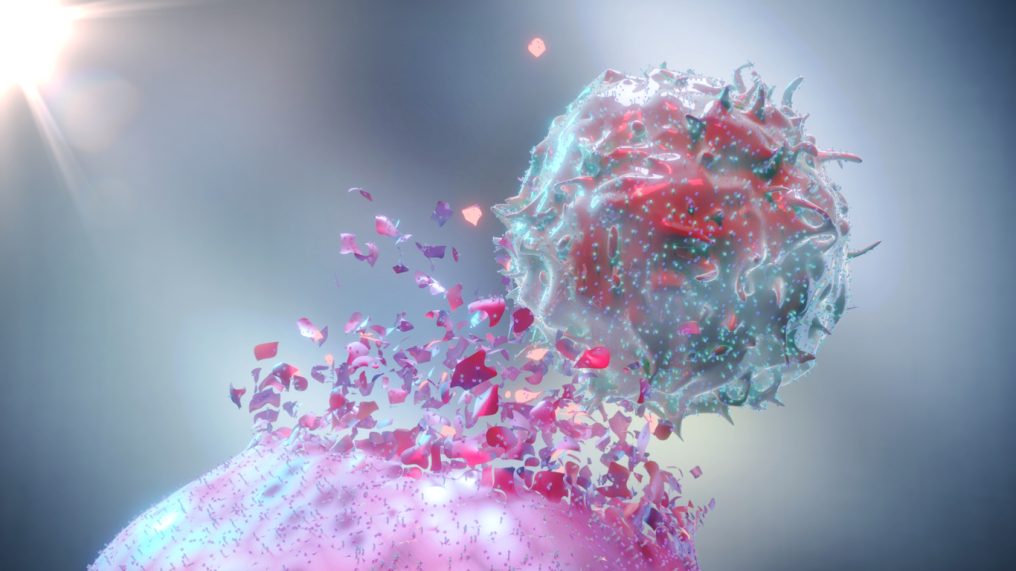
試験管試験において、NADがゲノムの安定性を維持するメカニズムに影響をもっているという証拠が提供されています。ゲノムの安定性が損なわれるとがんが発症します。
また、細胞内でNADが枯渇すると、ヒトの乳房、皮膚、肺の細胞で、腫瘍抑制タンパク質(がんを抑制してくれるタンパク質)が減少することがわかっています。
DNAが損傷された後、がん抑制効果を最適化するために必要な細胞内のNAD量も食事から必要となる摂取量もまだ判明していません。しかし、どちらも欠乏症予防に必要な量よりも多いと考えられています。
1. 骨髄内のNADの量
骨髄は体内で最も増殖性が高い臓器のひとつなので、化学療法剤(抗がん剤)の主な標的となります。そのため、がん患者は化学療法後、骨髄抑制に苦しむことがよくあります。
そして、ナイアシン欠乏症は、がん患者によくみられる症状です。
ナイアシンが欠乏することで骨髄組織が刺激され、化学療法の効果が抑制される可能性があることがマウスを用いた研究で示唆されています。
例えば、ナイアシンと骨髄中のNADの量と白血病リスクとの次の関係が示されています。
- ナイアシンが欠乏すると、骨髄のNADが減少し、白血病リスクが増加する
- ニコチン酸やニコチン酸アミドを薬理学的用量で投与すると、骨髄内のNADが増加し、白血病リスクが減少する
ただし、ヒトの細胞内のNADの量とDNAの修復との関係はほとんどわかっていません。

2人の健康な個人を対象としたある研究では、1日100 mgのニコチン酸を8週間服用すると、血中リンパ球(免疫細胞)のNAD量が増加したこと、また、サプリメントを摂取しなかった個体と比較して、サプリメントを摂取した個体では、リンパ球のDNA鎖切断が減少したことが報告されています。
また、職業上、発がん性物質の電離放射線に慢性的にさらされているパイロット82名のDNA損傷を評価した研究があります。この研究では、ナイアシンの食事摂取量が少ない被験者(1日に約20.5 mg)に比べて、ナイアシン摂取量が多い被験者(1日に約28.4mg)の方が、染色体異常が発生する率が有意に低かったことが報告されています。
放射線(X線)が照射された免疫細胞(リンパ球)でNAD+の量が多いと、DNA修復が促進されて生存率が高くなることも判明しています。
喫煙者に効果なし
一方で、21人の健康な喫煙者を対象とした研究では、14週間にわたり1日あたり最大100mgのニコチン酸を摂取しても、プラセボ(偽薬)と比較して、喫煙によって誘発される血中リンパ球の遺伝子損傷が減少するという証拠は得られていません。
2. 上部消化管のがん
DNA修復の生化学的、そして、細胞的な側面に関する研究で、ヒトによるナイアシンの食事摂取量とがんリスクとの関係に関心が高まっています。
イタリア北部とスイスで行われた大規模な症例対照研究は、抗酸化栄養素とともにナイアシンの食事摂取量の増加が、次のがんの発生率減少と関連していることを明らかにしました。
- 1日に食べるナイアシンの量が6.2mg増加すると、口腔がんと咽頭がんの発症リスクが約40%減少する
- 1日に食べるナイアシンの量が5.2mg増加すると、食道がんの発症リスクが約40%減少する
3. 皮膚がん

ナイアシンが欠乏すると、重度の日光過敏症を引き起こすこと、また、NADを必要とする酵素がDNA修復に関係していることを考えると、皮膚がんや皮膚の健康に対するナイアシンの効果に関心が寄せられています。
(1)ニコチン酸アミドに紫外線保護効果
マウスを用いた研究は、ナイアシンを追加補給させると紫外線による皮膚がんのリスクが減少したことを報告しています。そのことから、ナイアシンには、皮膚バリアの完全性を保護する効果があると考えられています。
逆に、ニコチン酸アミドを制限し、細胞内のNADを枯渇させると、酸化ストレスによってDNA損傷が増加することが示されていることから、NADには、がんから細胞を保護する役割があることが示唆されています。
米国モーズ外科学会会員1,500名を対象に行われた2021年の調査では、長年の紫外線暴露が主な原因とされる、表皮のケラチノサイト(角化細胞)から発生する有棘細胞がん(扁平上皮がん)に代表される「ケラチノサイトがん」の予防に、皮膚科医の76.9%がニコチン酸アミドを推奨していることが明らかにされています。
(2)非黒色腫皮膚がん予防に効果
基底細胞がんや扁平上皮がんなどの非黒色腫皮膚がん(メラノーマではない皮膚がん)は、主に紫外線によって引き起こされる一般的ながんです。
41,808人の男性と72,308人の女性を最長26年間追跡した米国の2つの大規模な前向きコホート研究の統合分析は、ナイアシンの摂取量(食事やサプリメン)が少ない人と比較して、多い人では、扁平上皮がんが予防される可能性があることが示されています。一方で、基底細胞がんとメラノーマは予防できない可能性も示されました。
一方、米国のヴァンダービルト大学メディカルセンター(VUMC)と米退役軍人省の共同研究チームが行った、退役軍人省コーポレートデータウェアハウスに保管されている33,822人の患者の電子健康記録データ(1999年10月1日~2024年12月31日)を用いた後ろ向きコホート研究は、1日2回ニコチン酸アミド(1回500mg)を30日以上服用したグループと服用しなかったグループを比較しています。
ニコチン酸アミドを服用していたグループでは、次の効果が示されています。
- 皮膚がん全体の発症リスク・・・有意に14%減少
- 最初の皮膚がん発症後にニコチン酸アミドの使用を開始しても再発リスク・・・54%減少
発症リスクの減少は皮膚がん全体だけでなく、基底細胞がん、皮膚扁平上皮がんでも認められ、皮膚扁平上皮がんで最も大きなリスク減少が認められています。
(3)再発予防効果
メラノーマではない皮膚がんの病歴を持つ386人の被験者を対象とした第III相ランダム化二重盲検プラセボ対照臨床試験が行われ、18か月の間に3ヶ月間隔で12ヶ月間、1日にニコチン酸アミドを2回(1回500mg)服用し、皮膚がんの再発に及ぼす効果を試験しています。
ニコチン酸アミドの大量摂取は、12か月後にプラセボ(偽薬)と比較して、次のがんの再発リスクを効果的に減少させました。
- 前癌性日光角化症・・・11%減
- 扁平上皮がん・・・30%減
- 基底細胞がん・・・20%減
しかし、この保護効果は、6か月後には消えてしまいました。つまり、皮膚がんの再発予防のためには、大量のナイアシンを摂り続ける必要があるということでしょうか・・。
I型糖尿病との関係

小児の1型糖尿病は、すい臓でインスリンを分泌するβ細胞が自己免疫によって破壊されることで起こります。高リスクの人の血液からは、糖尿病の症状が発生する前に、膵島細胞の自己抗体 (ICA)など特異的な抗体が検出されることがあります。
動物実験では、高容量のニコチン酸アミドにβ細胞の保護効果があることが示されていますが、抗体が検出された高リスクの人(ヒト)に薬理学的用量(1日に最大3g)を投与したとしても、I型糖尿病の発症を遅らせたり、予防したりする効果は確認されていません。
10件の臨床試験(うち5件はプラセボ対照試験)では、1年間ニコチン酸アミドで治療した後、β細胞の機能が改善したことが確認できたものの、血糖コントロールの改善は見られないことが報告されています。
I型糖尿病患者の兄弟姉妹(3~12歳)のうちICA抗体をもっている者を対象とした大規模多施設ランダム化比較試験でも、ニコチン酸アミドの摂取と、3年後の1型糖尿病の発生率に差は見られませんでした。
また、I型糖尿病患者のICA陽性親族552人を対象とした無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同試験でも、ニコチン酸アミド(1日に最大3g)を摂取した親族が5年以内に1型糖尿病を発症した割合は、プラセボ(偽薬)を摂取した親族と同じでした。
一方で、I型糖尿病の発症リスクをもつ小児に、ニコチン酸アミド(1日体重1kgあたり25mg)とアセチル-L-カルニチン(1日体重1kgあたり50mg)を併用することで、有望な症例報告があるとのことです。
循環器疾患予防との関係
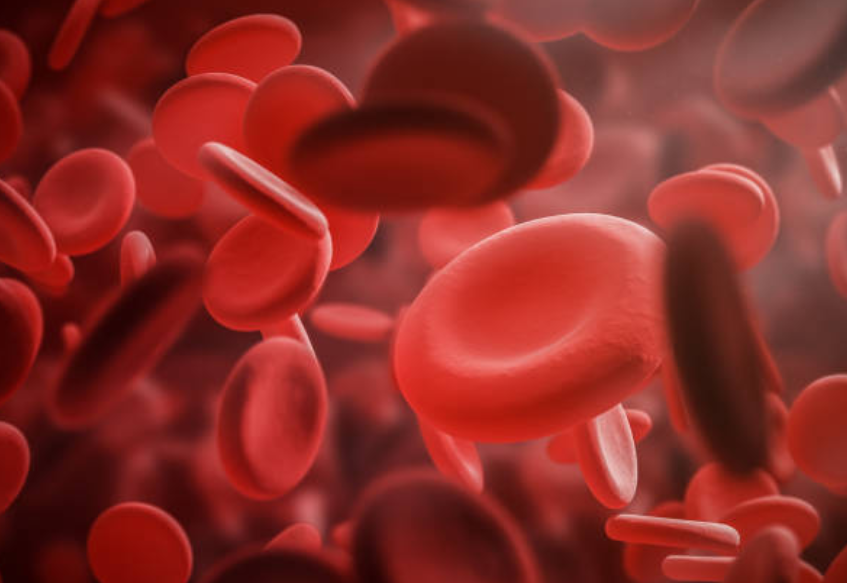
ナイアシン(ニコチン酸)は、脂質低下剤としてよく知られています。
1. 脂質低下効果
半世紀以上にわたって、薬理学的用量(大抵は高容量)でニコチン酸を摂取すると、血液中のコレステロール値が低下するものの、ニコチン酸アミドの摂取では低下しないことが知られています。しかし、ニコチン酸の脂質低下効果の根底にある正確なメカニズムはまだ明確には分かっていません。
試験管試験では、ニコチン酸が中性脂肪の合成と悪玉(LDL)コレステロールの生成を阻害し、善玉(HDL)コレステロールの減少を抑制することが観察されています。
善玉(HDL)コレステロール濃度の低下は、冠状動脈性心疾患(CHD)の主要な危険因子の1つです。言い換えれば、善玉(HDL)コレステロール濃度の増加は、リスクの減少を意味します。
また、ニコチン酸と結合する受容体は、脂質代謝にとって主要な次の組織に存在しています。
- 脂肪細胞
- 免疫細胞(リンパ球を除く)
- 網膜色素細胞
- 結腸上皮細胞
- ケラチノサイト
- 乳房細胞
- ミクログリア
- 肝臓
そのため、ニコチン酸療法によって、次のような心臓保護効果が得られるのではないかと期待されています。
- 善玉(HDL)コレステロール濃度の顕著な増加
- 血液中のリポタンパク質(a)濃度の減少
- 小さくて密度の高い悪玉(LDL)コレステロールの粒子を浮力の高い大きな粒子に変換
ただし、臨床試験(ヒトを対象とした研究)では、ニコチン酸単独では血液中の脂質には影響を及ぼさないことが示されています。
2. 低用量のニコチン酸
ニコチン酸の高容量摂取には有害な副作用(後述します)があるため、ニコチン酸療法では、少量のニコチン酸を脂質低下薬(主に、スタチン)と組み合わせて使用されることが多いです。
しかし、スタチン(セリバスタチン、アトルバスタチン、またはシンバスタチン)を服用している39人の患者を対象としたプラセボ対照研究では、低用量のニコチン酸(1日100mg)では、善玉(HDL)コレステロールを2.1mg/dLしか増加させず、併用による悪玉(LDL)コレステロール、総コレステロール、中性脂肪濃度への効果がなかったことを報告しています。
3. 高用量の徐放性のニコチン酸
『コレステロール低下による治療効果の調査のための動脈生物学(ARBITER 2)』という二重盲検プラセボ対照試験では、冠状動脈性心疾患をもち、アテローム性動脈硬化症の発症のサインである頸動脈内膜中膜内の善玉コレステロール濃度が低い167 人を対象に、スタチン療法にニコチン酸(1日1g)を追加した場合の効果が調査されました。
シンバスタチン単独療法と比較して、シンバスタチンに徐放性ニコチン酸(長時間に渡って徐々に体内に放出されるニコチン酸)を追加すると、頸動脈内膜中膜の厚さの増加が防止されました。
ARBITER研究シリーズの有効性比較試験(ARBITER 6)では、スタチンを服用している患者に、もう一種類のコレステロール低下薬であるエゼチミブを追加投与するよりも、徐放性ニコチン酸(1日に2gを14か月)を追加投与する方が、頸動脈内膜中膜の厚さが大幅に減少することが示されています。
4. 糖尿病の有無で効果に差
血糖値が正常な患者においては、善玉コレステロールの濃度の増加によって、アテローム性動脈硬化の進行を阻止できることが示されています。
しかし、空腹時血糖値の不全や糖尿病などがある患者においては、善玉(HDL)コレステロールの濃度が増加しても、 頸動脈内膜中膜の厚さの減少やアテローム性動脈硬化の遅延は期待できませんでした。
5. 血流依存性血管拡張反応
血流依存性血管拡張反応は、血管内皮の機能を測定する方法で、高いほど、心疾患リスクが低くなります。
状動脈性心疾患を発症するリスクがある患者とすでに冠状動脈性心疾患を発症している患者441人を対象に、血流依存性血管拡張反応へのニコチン酸の影響を調べた7件のランダム化対照試験のメタアナリシスでは、1日に1~2gのニコチン酸を12週間~1年間投与すると、血流依存性血管拡張反応が2%も有意に増加したことが示されています。
循環器疾患治療との関係

いくつかの無作為化プラセボ対照多施設共同試験で、心血管疾患を発症したその後の状態について、ニコチン酸療法を単独で実施した場合や他の脂質低下剤と併用した場合の有効性と安全性が調査されています。
血管疾患の病歴を持つ39,195人の被験者を対象とした、下にご紹介する『CDP試験』、『AIM-HIGH試験』、『HPS2-THRIVE試験』を含む23件のランダム化比較試験のメタ分析は、ニコチン酸の単独投与または他のコレステロール低下薬との併用による効果を比較した結果、ニコチン酸療法の心臓血管疾患治療への利点が存在しなかったことを発表しています。
1日約2gのニコチン酸補給を約11.5ヶ月間続けても、致死的な心筋梗塞と脳卒中の数だけでなく、致死的ではない数も減少しませんでした。
冠状動脈薬物プロジェクト(CDP)
『冠状動脈薬物プロジェクト(CDP)』は、過去に心筋梗塞を患ったことのある8,000人以上の男性を対象に6年間追跡調査しています。
偽薬を服用したグループと比較して、即時放出型のニコチン酸を毎日3g 摂取した患者では次の改善が見られました。
・総血中コレステロール・・・平均10%減少
・中性脂肪・・・26%減少
・再発性非致死性心筋梗塞・・・27%減少
・脳卒中や一過性脳虚血発作・・・26%減少
さらに9年間の追跡調査では、ニコチン酸治療により死亡総数が10%減少したことが明らかになりました。
HDL-アテローム性動脈硬化症治療研究(HATS)
冠状動脈性心疾患と低善玉(HDL)コレステロール濃度が確認されている160 人の患者を対象とした3年間のランダム化対照試験である『HDL-アテローム性動脈硬化症治療研究(HATS)』は、偽薬を服用していたグループと比較して、シンバスタチンとニコチン酸(1日2~3g)を併用していたグループにおいて、次の効果を確認しています。
・善玉(HDL)コレステロール 濃度の増加
・冠状動脈狭窄の進行抑制
・心筋梗塞や脳卒中を含む心血管疾患の発症頻度の減少
なお、スタチン治療を受けている患者では横紋筋融解症が増加する傾向があることが分かっています。横紋筋融解症は、筋肉細胞が破壊され、酵素や電解質が血液中に放出され、場合によっては腎不全を起こす比較的まれな症状です。その横紋筋融解症の発症リスクが、ニコチン酸とスタチンの同時投与によって高まることが示唆されています。
<メタボや糖尿病がある患者>
HATS研究の参加者のうち、メタボリックシンドロームをもっている患者では、ニコチン酸治療によって、グルコースとインスリン代謝が中程度に損なわれたものの、心疾患の発生率が低下したことが示されています。
また、HATS研究終了後、投薬と食事によって8か月後には、血糖値コントロールが研究参加前の状態に戻ったことが報告されています。
<栄養素との相互作用>
『HATS研究』によって、次の栄養素を追加摂取することで、シンバスタチンとニコチン酸の併用療法の効果が失われることが示されています。
・ビタミンC・・・1日1,000mg
・RRR-α-トコフェロール(天然ビタミンE)・・・1日800IU
・セレン・・・1日100μg
・β-カロテン・・・1日25mg
なぜ効果が失われるのかのメカニズムは不明です。コレステロール低下薬を服用している人は、抗酸化ビタミン/成分のサプリメント飲む前に、医師や薬剤師に相談することをお勧めします。
AIM-HIGH試験
スタチン治療で悪玉コレステロールが減少している場合
心血管疾患とアテローム性脂質異常症をもち、シンバスタチン(+/-エゼチミブ)で治療を受けた3,414人の患者を対象に、徐放性ニコチン酸(1日に1.5~2g)の増分効果を調べた『AIM-HIGH試験(低HDL/高中性脂肪を伴うメタボリックシンドローム患者へのアテローム性血栓症介入試験:グローバルな健康転帰への影響)』は、研究開始前に、既に悪玉(LDL)コレステロールの目標濃度(70mg/d未満)を達成していた患者では、ニコチン酸治療による善玉(HDL)コレステロール上昇の効果による心血管疾患に関係する症状の発症数を減少させることはできませんでした。
慢性腎臓病がある患者
さらに、ステージ3の慢性腎臓病の505人の参加者を対象とした事後分析では、プラセボ(偽薬)を服用していたグループと比較して、ニコチン酸治療を受けたグループで、全死因死亡率が増加していることが判明しました。
HPS2-THRIVE試験
アテローム硬化性疾患治療薬/脂質異常症治療薬と併用
血管疾患をもつ25,673人を対象としたかなり大規模な多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照試験である『HPS2-THRIVE試験(心臓保護研究2:血管イベントの発生率を減らすためのHDL治療)』では、血管イベントの発生率に対する徐放性ニコチン酸(1日2g)とラロピプラント(アテローム硬化性疾患治療薬/脂質異常症治療薬、1日40mg)の増分効果が調べられています。
ラロピプラントには、ニコチン酸による紅潮を軽減する作用があります。
プラセボ(偽薬)と比較して、ニコチン酸+ラロピプラントは、約3.9年の追跡期間後に、次の効果を示しました。
・LDLコレステロール・・・平均10mg/dL減少
・中性脂肪・・・33mg/dL減少
・HDLコレステロール・・・6mg/dL増加
しかも、主要な血管イベントの発生率やいかなる原因による死亡にも影響を与えませんでした。
<スタチン治療との併用>
HPS2-THRIVE試験とは別に、シンバスタチン治療を受けた25,000人を超える被験者を対象に、ニコチン酸とラロピプラントの追加による副作用の可能性を特定する無作為化プラセボ対照試験が行われています。
スタチン療法にニコチン酸とラロピプラントを追加すると、特にアジア人の被験者においてミオパチーと横紋筋症のリスクが増加することが報告されています。スタチン治療にニコチン酸とラロピプラントを追加することは、特定の人種集団においては、スタチン治療の効果を低下させてしまう可能性があると研究者は述べています。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)との関係
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、喫煙と加齢が原因で発症する進行性の治癒不可能な病気です。世界における死亡原因の第3位となっている疾患です。
デンマークのコペンハーゲン大学が行った小規模なランダム化二重盲検プラセボ対照試験では、ニコチン酸アミドリボシドのCOPDに対する効果が検証されています。
安定期のCOPD患者と、身体的特徴が類似した健康な被験者をそれぞれランダムに次の2つのグループに分け、6週間にわたり薬を服用した後、炎症性物質のインターロイキン8(IL8)の変化量を調査しています。
- COPD患者+ニコチン酸アミドリボシド・・・2g
- COPD患者+プラセボ(偽薬)
- 健常者+ニコチン酸アミドリボシド・・・2g
- 健常者+プラセボ(偽薬)
1. 気道炎症の減少
6週間後、ニコチン酸アミドリポシドを服用していたCOPD患者グループの IL8 が−46.2%減少しましたが、偽薬を服用していたグループでは、13.4%増加していました。両グループ間の差は−52.6%となります。しかも、この効果は12週間後も持続していたことが報告されています。
研究者は、ニコチン酸アミドリポシドによって、気道におけるゲノムの完全性に関連する遺伝子経路が上方制御された兆候だと考えています。
2. 細胞老化の減少
更に、ニコチン酸アミドリポシドを服用していたグループの全血中のNAD+量が2倍以上増加したこと、その一方で、血漿中の IL-6 量が変化しなかったことが示されています。
上述したように、NAD+は、加齢に関連した免疫機能や炎症などの複数の経路に関与している中心的な分子ですが、加齢とともに減少します。
研究開始時点と6週間後のNAD+の量の変化は次の通りでした。
- COPD患者+ニコチン酸アミドリポシド: 31.9µM → 71.1µM(2.2倍)
- 健常者+ニコチン酸アミドリポシド: 34.8µM → 49.4µM(1.4倍)
COPD患者と健常者の偽薬を服用したグループでは、有意な変化はありませんでした。
研究者は、おそらく細胞老化のエピジェネティック老化の減少の兆候が示されたと述べています。つまり、栄養補給などの食事性の要因によって老化細胞が減ったことを意味します。
この研究は、COPD患者を対象とした研究でしたが、ニコチン酸アミドリポシドを服用していた健常者にも効果が現われていることを考えると、ナイアシン豊富な食事をすることで老化現象を予防できると言えそうですね!
遺伝性疾患との関係

先天性NAD欠乏症は、食事からナイアシンの吸収と運搬にかかわる遺伝子やNAD+を作る過程に関係している遺伝子などの変異が原因で起こると考えられています。
1. ハートナップ病
ハートナップ病は、トリプトファンの輸送に関係している経路の欠陥によって起こります。主に、腎臓と腸で発現する遺伝子の変異が原因です。
ニコチン酸またはニコチン酸アミドのサプリメントの服用によって病状が管理できます。
2. 複合型先天奇形
トリプトファンからナイアシンを合成する過程で必要な酵素を作る遺伝子に変異があると、脊椎、肛門、心臓、気管食道、腎臓、四肢の複合型先天奇形が起こります。これらの奇形は、NAD+の枯渇が原因であることが判明しています。
マウスを用いた実験ですが、母マウスが妊娠中にナイアシンを十分に摂取して、NAD+の適切な量が確保できると、遺伝子変異を持つ胎児の先天異常の発現を予防できることが報告されています。
ただし、ヒトでは、NAD欠乏症によって引き起こされる先天性複合型奇形を回避するために必要な NAD+の用量はまだ判明していません。
3. 先天性代謝異常症
多くの先天性代謝異常は、遺伝子変異によって、補酵素の結合の強さ(結合親和性)と反応速度(酵素効率)が低下することが原因で発生します。
多くの場合、ナイアシンを高容量で摂取することで、酵素活性が部分的に回復し、遺伝病の兆候を軽減することができます。
NADを必要とする酵素が多いことを考えると、症状の多くはナイアシンの補給によって改善されるのではないかと考えられています。
4. フリードライヒ運動失調症
フリードライヒ運動失調は、遺伝性の運動失調症に一般的にみられる症状で、早期に発症し、次の特徴を持っています。
- 進行性運動失調
- 側弯症
- 構音障害
- 心筋症
- 糖尿病など
この疾患では、ミトコンドリアタンパク質のひとつフラタキシンが大幅に減少します。
フリードライヒ運動失調症の成人患者10人を対象とした非盲検の用量漸増パイロット試験では、最長8週間にわたるニコチン酸アミド(1回2~8g)の単回および反復投与が良好な忍容性を示すことが判明しています。 また、3.5~6gのニコチン酸アミドを毎日繰り返し投与すると、末梢白血球のフラタキシン濃度が大幅に増加することが報告されています。
しかし、フラタキシンが増加しても、神経学的な改善は見られませんでした。
統合失調症との関係
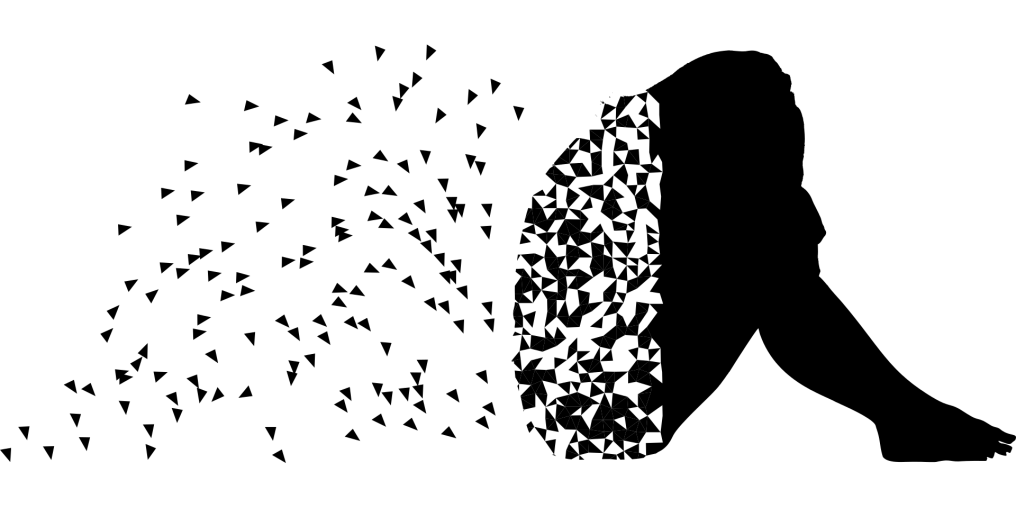
統合失調症は、純粋に臨床症状から診断される、病因が不明瞭な神経疾患です。
ペラグラ(ナイアシン欠乏症)による神経障害の症状が急性統合失調症に似ていることから、ナイアシンを用いた治療が1950年代~1970年代にかけて研究されました。
高容量のニコチン酸を服用すると、主な副作用として皮膚に紅潮が現れますが、統合失調症の患者には、紅潮が起こらない傾向があります。
皮膚の紅潮は、血管の拡張を促すプロスタグランジンD2と呼ばれるタンパク質(プロスタノイド)ファミリーによって引き起こされます。 そのため、紅潮が起こらないということは、統合失調症の患者ではプロスタノイドによるシグナル伝達に異常が起こっていることを示唆しています。
既に、統合失調症患者におけるナイアシン感受性の変化と、より大きな機能障害との間に関連性が見出されていて、これは脂質代謝の変化が脳の発達を重大に損ない、疾患の一因となっている可能性を示唆する他の研究によっても裏付けられています。
興味深いのは、皮膚の紅潮反応の鈍化は、統合失調症の患者の一親等の親族にも多く見られる現象です。つまり、ナイアシンに対する感受性は、遺伝的な特性であることを示唆しています。
女性ホルモン剤との関係
生理痛やPMS、そして更年期症状の改善のために処方されるエストロゲン製剤とエストロゲンを含む女性ホルモン剤は、アミノ酸トリプトファンをナイアシンの合成に優先的に使用させることが知られています。
その結果、ナイアシンが不足する可能性は低くなりますが、体内で過剰になる可能性は高くなります。
同時に、同じようにトリプトファンを必要とする幸せホルモンのセロトニンの合成が不足する可能性があり、うつ症状が現れやすくなることが報告されています。
サプリメントの安全性と危険性

ニコチン酸はナイアシンという栄養素ですが、医療にも用いられているものです。そのため、医薬品と同じように扱う必要がある成分です。
コレステロール値を改善したいなどの希望がある人は、ご自身で判断することなく必ず医師にご相談の上、サプリメントの購入を行ってください。
ナイアシンのサプリメント/医療用補助剤は、次の形態で購入できます。
- ニコチン酸アミド・・・サプリメントや食品強化に添加物として通常使用されているもの
- ニコチン酸アミドリボシド
- ニコチン酸・・・コレステロール低下剤として店頭および処方箋で購入可能
高脂血症治療用のニコチン酸には、次の3種類があります。
- 即時放出型(結晶)ニコチン酸・・・吸収時間1 ~ 2 時間
- 徐放性ニコチン酸・・・吸収時間8 ~ 12 時間
- 持続放出性ニコチン酸・・・吸収時間12 時間超
1. ニコチン酸アミド
ニコチン酸アミドは一般にニコチン酸よりも忍容性に優れていて、顔面の紅潮は通常では起こりません。
ただし、1日10g以上のかなりの高用量を服用した場合には、次の副作用が観察されています。
- 吐き気、嘔吐
- 肝毒性の兆候(肝酵素の上昇、黄疸)
2. ニコチン酸アミドリボシド
12人の健康な被験者を対象とした研究は、100mgの用量のニコチン酸アミドリボシドが1回の服用で、安全に血中のNAD+を増加させることができることを示しています。
- 300mg・・・参加者のうち2人が皮膚紅潮を報告
- 1,000mg(1g)・・・参加者のうち2人が熱を感じたと報告
120人の健康な成人(60~80歳)を対象に行われた無作為化プラセボ対照試験では、ニコチン酸アミドリボシド(250mg、500mg)+プテロスチルベン(50mg、100mg)を毎日8週間摂取しましたが、プラセボ(偽薬)と比較して、重篤な副作用が起こることはありませんでした。
40人の肥満男性(年齢40~70歳)を対象とした無作為化プラセボ対照試験では、ニコチン酸アミドリボシドを1日2,000mg(2g)を2回に分けて12週間摂取すると、次のような軽度の副作用が起こることが報告されています。
- 過剰な発汗
- そう痒症
- 膨満感などの軽度の胃腸症状
ナイアシンの過剰摂取による副作用
ナイアシン(ニコチン酸)の一般的な副作用には、次のようなものが含まれます。
皮膚の紅潮は、血管の拡張を促すプロスタグランジンD2と呼ばれるタンパク質(プロスタノイド)ファミリーによって引き起こされます。
- 紅潮
- そう痒症(皮膚の重度のかゆみ)
- 皮膚の発疹
- 吐き気や嘔吐などの胃腸障害
- 一時的な低血圧や頭痛
- かすみ目やその他の眼疾患(1日1.5~5gの高用量で)
- 痛風発作(尿酸の排出の減少)
- 肝細胞損傷による肝臓酵素の上昇や黄疸
- 耐糖能の喪失(糖尿病の発症と重篤化)
1.~7.の症状は、摂取を止めれば元に戻ります。
しかし、8.~9.については、下に特記します。
1. 肝毒性
ニコチン酸の摂取量が1日750mgの低量でも肝毒性が観察されています。また、徐放性ニコチン酸を2か月間1日500mgという少量の服用した場合でも肝炎が観察されています。
ただし、重篤な肝炎は、高コレステロール値を治療するために数か月~1年以上1日3~9gの高用量を使用した場合に報告されています。
即時放出型ニコチン酸が徐放性ニコチン酸よりも肝毒性が低いかどうかは不明です。しかし、即時放出型ニコチン酸は、徐放型よりも高用量で使用されることが多く、同等の用量で徐放性ニコチン酸を即時放出型ニコチン酸に置き換えた個人で重度の肝毒性が発生しています。
2. 耐糖能の喪失
ナイアシンを大量に摂取すると、インスリン感受性が低下し耐糖能が損なわれることが観察されています。 耐糖能とは、血糖値が上昇した際に即座に通常値にもどす体の仕組みのことです。
糖尿病リスクの高い人で耐糖能障害が一時的にも起こると、血糖値の上昇とII型糖尿病が引き起こされる可能性があります。
『HPS2-THRIVE試験』の研究開始時にII型糖尿病ではなかった参加者17,374人のデータを用いた分析では、約3.9 年間にプラセボ(偽薬)を服用したグループと比較して、ニコチン酸+ラロピプラントを服用したグループで、新たにII型糖尿病と診断された人の割合が有意に高いことが判明しています。(プラセボ4.3%:ニコチン酸+ラロピプラント5.7%)
研究開始時点ですでに糖尿病をもっていた8,299人の参加者では、プラセボグループと比較して、ニコチン酸+ラロピプラントを服用したグループでは入院につながる糖尿病の重篤な障害リスクが有意に上昇したことが報告されています。
3. 心血管疾患の発症リスク上昇
2024年の米国とドイツの研究グループによる大規模コホート調査によって、ナイアシンの最終的な代謝物である次の2つの物質の血中濃度の上昇と心血管疾患リスクの上昇が関連していることが示されています。
過剰なナイアシン摂取によって心疾患リスクが上昇する可能性を示しています。
- N1-メチル-2-ピリドン-5-カルボキサミド(2PY)・・・米国1.64倍、欧州2.02倍
- N1-メチル-4-ピリドン-3-カルボキサミド(4PY)・・・米国1.89倍、欧州1.99倍
さらに、可溶性血管接着分子-1(sVCAM-1)の濃度が2PYと4PYの両方の濃度と有意に相関することが示されています。
可溶性血管接着分子-1(sVCAM-1)は、動脈硬化や関節リウマチなどで増加する血管接着分子-1(VCAM-1)が、サイトカイン(炎症性物質)によって加水分解されたものです。つまり、sVCAM-1が増えるということは、体内に動脈硬化などの病変があることを表します。
体内でナイアシンの代謝物が増加し過ぎると動脈硬化が起こる可能性を示したものです。
サプリメントと医療用補助剤の服用に注意が必要な人
サプリメント(栄養補助食品)としてのニコチン酸を含め、次の病歴がある人は、一般の人よりもナイアシンのサプリメントによる悪影響を受けやすい可能性があります。
- 肝機能に異常がある人、または肝疾患
- 糖尿病
- 活動性消化性潰瘍
- 痛風
- 不整脈
- 炎症性腸疾患
- 片頭痛
- アルコール依存症
そして、ニコチン酸の副作用は、特定の薬剤との併用で悪化する可能性があります。
1. ミオパチーリスクの上昇
次の薬と併用することで、ミオパチーのリスクがさらに高まる可能性があります。
- 胆汁酸封鎖剤(コレスチラミン、コレスチポールなど)
- 抗高脂血症薬
- ゲムフィブロジル(ロピド)
2. 肝毒性の増強
次の医薬品と併用することでニコチン酸の肝毒性が増強されます。
- パラセタモール
- アミオダロン(コルダロン)
- カルバマゼピン(テグレトール)
- など
3. 薬効作用の妨害
また、次の医薬品の作用を妨げます。
- プロベネシド(尿酸排泄促進剤)
ナイアシンを多く含む食品
ナイアシンを不足させないために、そして、ナイアシンの過剰摂取を避けるためには、サプリメントからではなく、「食事」をしてほしいとヘルスコーチとして願います。
それが一番安心で安全な方法だからです。
下の画像を見ていただくと分かる通り、ナイアシンを豊富に含む食品には、和食の出汁に用いられる食品が多いです。


かつお節、煮干し、椎茸、昆布などです。昆布(100g中に2~3mg)は上のリストに入っていませんが、1日の必要量の10%以上を含んでいます。
ですから、和食の出汁を使ったお料理をよく食べる人は、ナイアシン不足を心配する必要はありません。
生鮮食品中のナイアシンは、主にNADやNADHの形で存在しています。食品を加熱調理したり加工する過程でNADとNADHは分解されて、次の成分になります。
・動物性食品・・・ニコチン酸アミド
・植物性食品・・・ニコチン酸
生で食べる場合には、消化器官で分解されて、動物性のものも植物性のものもニコチン酸アミドになります。
ただし、食品によって分解率/消化率や吸収率が異なります。日本で一般的に食べられている食事中のナイアシンの利用効率は約60%と推定されています。
1. トウモロコシを主食にする場合
熟したトウモロコシには、かなりの量のナイアシンが含まれていますが、それはヒトが栄養として利用できない形のものです。でも、熟す前の未熟なトウモロコシには、ヒトが利用できる形のナイアシンが含まれています。
メキシコなどトウモロコシを主食にしている地域では、伝統的にトウモロコシを調理前に石灰(酸化カルシウム)溶液(=アルカリ溶液)に浸し、そのまま加熱調理します。そうすることでナイアシンが生体利用可能な状態になることが明らかにされています。
トウモロコシを主食にする場合の必要なひと手間、伝統の知恵ですね。
言い換えれば、トウモロコシからナイアシンを得たいなら、石灰と一緒に茹でて食べると良いということです。
ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス

最近、サーチュインとの関係で、ナイアシンへの注目度が高まっているようです。また、血圧が高めだったり、高コレステロールが気になる人にとっては、魅力的なサプリメントに映るかもしれません。
でも、今回、お伝えしてきた通り、ナイアシンのサプリメントにはある一定の医療効果が認められているからこそ、副作用も大きく、重篤にもなりえます。
サプリメントではなく、まずは、ナイアシンを豊富に含む食品を多く食卓に並べることから始めましょう。あなたは1日に3食は食べるのです。その食事を変えることから始めましょう。ナイアシンは、和食の出汁に多く含まれていますから、まずは食事を和食中心にしてはいかがでしょうか。
でももし、おひとりで取り組むことに不安や難しさを感じるのでしたら、ヘルスコーチと、一度、話をしてみませんか?
公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。
プライベート・ヘルスコーチング・プログラムについて
お気軽にご相談ください。
初回相談を無料でお受けしています。
あるいは、ソフィアウッズ・インスティテュートのマインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースで学びませんか?セルフドクターコースでは、あなたが食を通してご自身の主治医(セルフドクター)になるために、必要な知識とスキルを教えています。
新学期は、毎年3月と9月です。講座でお会いしましょう。

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる
ニュースレターのご登録は、こちらから
統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます
参考文献
- “Niacin”, Micronutrient Information Center, Linus Pauling Institute, Oregon State University
- “Effect of nicotinamide riboside on airway inflammation in COPD: a randomized, placebo-controlled trial.”, Norheim, K.L., Ben Ezra, M., Heckenbach, I. et al., Nat Aging (2024). https://doi.org/10.1038/s43587-024-00758-1
- “A terminal metabolite of niacin promotes vascular inflammation and contributes to cardiovascular disease risk.”, Ferrell M, Wang Z, Anderson JT, Li XS, Witkowski M, DiDonato JA, Hilser JR, Hartiala JA, Haghikia A, Cajka T, Fiehn O, Sangwan N, Demuth I, König M, Steinhagen-Thiessen E, Landmesser U, Tang WHW, Allayee H, Hazen SL., Nat Med. 2024 Feb;30(2):424-434. doi: 10.1038/s41591-023-02793-8. Epub 2024 Feb 19. Erratum in: Nat Med. 2024 Jun;30(6):1791. doi: 10.1038/s41591-024-02899-7. PMID: 38374343; PMCID: PMC11841810
- “Nicotinamide for Keratinocyte Carcinoma Chemoprevention: A Nationwide Survey of Mohs Surgeons.”, Desai S, Olbricht S, Ruiz ES, Hartman RI., Dermatol Surg. 2021 Apr 1;47(4):452-453. doi: 10.1097/DSS.0000000000002788. PMID: 33625146.
- “Nicotinamide for Skin Cancer Chemoprevention.”, Breglio KF, Knox KM, Hwang J, Weiss R, Maas K, Zhang S, Yao L, Madden C, Xu Y, Hartman RI, Wheless L., JAMA Dermatol. 2025 Sep 17:e253238. doi: 10.1001/jamadermatol.2025.3238. Epub ahead of print. Erratum in: JAMA Dermatol. 2025 Oct 15. doi: 10.1001/jamadermatol.2025.4473. PMID: 40960808; PMCID: PMC12444641.
- “A Phase 3 Randomized Trial of Nicotinamide for Skin-Cancer Chemoprevention.”, Chen AC, Martin AJ, Choy B, Fernández-Peñas P, Dalziell RA, McKenzie CA, Scolyer RA, Dhillon HM, Vardy JL, Kricker A, St George G, Chinniah N, Halliday GM, Damian DL., N Engl J Med. 2015 Oct 22;373(17):1618-26. doi: 10.1056/NEJMoa1506197. PMID: 26488693.
ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング