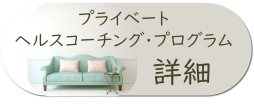バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。
心と体をつなぐホリスティックな食事法について、
ニュースレター登録者限定のキャンペーン情報等も配信しています。
ご登録は、こちらから
もれなく統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます
目次
フラボノイドと認知機能に関係性はあるのか
2021年3月と7月に発表されたハーバード大学による大規模な追跡調査によって、苺の赤色、ホウレン草の緑色、かぼちゃの黄色など、お野菜やフルーツに含まれているフラボノイドが認知機能を保護することや様々な病気による死亡リスクを減らすことが裏付けられました。
この2つの研究の両方に、ハーバード大学の疫学と栄養学の教授であり、私が資格を取得したニューヨークの学校(IIN)の先生のおひとりでもあるウォルター・ウィレット博士が参加されています。
今回はこの2つの研究についてお伝えします。

77,000人以上の中年の男女の健康診断データと、自己申告による食事情報を20年以上に渡り追跡調査した結果が2021年7月に発表されました。
申告された情報には、被験者がフラボノイド豊富な食品を食べる頻度や食品の種類と、70代になってからの認知機能の変化が含まれています。
1. 認知機能の調査項目
認知機能については、次の事柄に困難を感じるかが申告されています。
- 最近の出来事やアイテムの短いリストを覚える
- 次から次へと物事を覚える
- 指示を理解する
- グループでの会話やテレビのあらすじについていく
- なじみのある街の道を歩く
2. 6種類のフラボノイドについて検証
フラボノイドについては、申告された食事内容から摂取したフラボノイドの量を、次の6種類に分けて集計しています。
- フラボノール|ケルセチンなど(玉ねぎやケールなどに多い)
- フラボン|ルテオリンなど(ピーマンやセロリなどに多い)
- フラバノン|ナリンゲニンなど(グレープフルーツやオレンジなどに多い)
- フラバン-3-オールモノマー|カテキンなど(赤ワインやイチゴなどに多い)
- アントシアニン|シアニジンなど(ブラックベリーや赤キャベツなどに多い)
- ポリマー|テアフラビンなど(紅茶などに多い)
3. フラボノイドの摂取が多かった人

年齢、体重、運動、アルコール摂取、うつ病、フラボノイドを含まない食品の摂取量など、認知機能に影響を与える可能性のある要因を考慮しても、フラボノイドの1日の平均摂取量が最も少ない人と比較して、最も多い人は記憶と思考に関わる不調を報告することが約19%少ないことが示されています。
ウォルター・ウィレット博士は次のように述べています。
「この結果は、フラボノイドを多く含む食品を食べることで、
晩年の記憶やその他の認知プロセスの低下を防止
または遅らせることができることを示しています。」
そして、研究の筆頭著者であり、ハーバード・オックスフォード大学プログラムの疫学と、ハーバード大学栄養学のポストドクター研究員であるティアンシン・イェ博士は次のように述べています。
「この研究を通して、フラボノイド豊富な食品を人生の早期から
食べ始めることで、脳の保護効果が向上するように思えます。
しかし、人生の後半に多く食べ始めた参加者にさえ、
利点が見られました。」
フラボノイドは魔法成分か?

フラボノイドがなぜ認知機能を保護できるのか、詳細なメカニズムについては、まだ判っていません。
でも、フラボノイドが強力な抗酸化物質であること、そして、アルツハイマー病の特徴である脳の炎症やアミロイドβタンパク質の蓄積を抑制することは、既に判っています。加えて、フラボノイドが内臓炎症と腫瘍の成長を抑制し、血圧を改善することも既に判明している事実です。また『野菜とフルーツに多いフラボノイドは多く食べるほど太らない』もご参照ください。
抗酸化物質は、血管を健康に保つことで、脳への血流を維持することに貢献しているのではないかと、研究者は述べています。
脳への血行は、脳由来の神経栄養因子の量を増やし、脳細胞を修復し、脳細胞同士の結合を強化し、新しい脳細胞の成長を促し、記憶(覚えることと思い出すことの両方)に関与している脳の海馬のサイズを拡大するために重要だからです。
脳の保護作用が強かった3つのフラボノイド
6つのフラボノイドの中でも、次の3種類が最も脳の保護作用が強かったことも今回の研究で報告されています。
- フラボン|自己申告による認知機能低下リスクを38%低下
- フラバノン|自己申告による認知機能低下リスクを36%低下
- アントシアニン|自己申告による認知機能低下リスクを24%低下
認知機能の保護効果が高い食品

今回発表された36種類の野菜と果物の中で、認知機能の保護に効果が高かった順に10位までご紹介します。全てご覧になりたい方は、最後に裏付けとなる研究論文を参考文献として一覧にしていますのでご確認ください。
1. 認知機能の保護効果トップ10
なお、ソフィアウッズ・インスティテュートが各食品の詳しい健康効果について執筆した記事へのリンクもつけていますのでご参照ください。
ちなみに、36種類中最下位だったのは、赤ワインでした。
2. 生のホウレン草はほどほどに
4位にランクインしている生のホウレン草はシュウ酸が多い食品です。そのため、食べ過ぎると結石ができやすくなるので要注意です。認知症予防のために結石になっても構わなければ止めませんが(笑)ほどほどに食べることが肝要ですね。
また、サツマイモが上位に入っているのがなんだか意外ですが、嬉しいです。
フラボノイドは1日にどれくらい必要なのでしょうか

今回の研究の対象者達が摂取していたフラボノイドの量は、次のとおりです。
- 最も少ない人・・・1日150mg
- 最も多い人・・・1日620mg
1. フラボノイドは数えなくて良い
しかし、ひとつの食品には、通常、複数のフラボノイドが含まれているので、ひとつひとつの食品に含まれているフラボノイドの量を追跡していくのは、カロリー計算などとは比較できないくらい非常に複雑で困難です。
そのため、ハーバード大学の研究者は次のように述べています。
「フラボノイドの計算はしなくても良い」
2. ソフィアウッズ・インスティテュートのアプローチ

ソフィアウッズ・インスティテュートの記事を読まれている人、プライベート・ヘルスコーチング・プログラムを受けたことがある人、そしてマインド・ボディ・メディシン講座を受講されたことがある人には、耳ダコだと思いますが、統合食養学はホールフードで食べることを勧める栄養学です。
統合食養学がミクロ栄養素で食事を勧めることはありません。
3. 虹色に食べる
ですから、ソフィアウッズ・インスティテュートのアドバイスもハーバード大学の研究者と同じです。フラボノイドで摂ろうとするのではなく、フラボノイドを多く含むお野菜と果物をホールフードで、皮ごと丸々食べることを勧めます。
食事を虹色にする
それだけです。
フラボノイドのそれぞれの色については、マインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースのがん予防のレクチャーで詳しくお話しています。
そして、フラボノイドの量を測る代わりに、野菜を1日3食食べることと果物を1日2食食べることを勧めています。
フラボノイドの量を測る代わりに

2021年3月1日に『サーキュレーション』誌に発表されたもうひとつの研究が、「1日野菜3食+果物2食」の利点を裏付けています。
1984年から2014年に看護師健康調査(Nurses’ Health Sturdy)に登録されていた基礎疾患のない女性66,719人と、1986年から2014年に医療従事者フォローアップ調査(Health Professionals Follow-up Study)に登録されていた男性42,016人を最長で30年間追跡調査した研究です。
1. 最も死亡リスクが減る量
1日に2食だけ果物または野菜のどちらかを食べていた人と比較して、「1日に野菜3食+果物2食」を食べていた人には次の様な特徴があったことが報告されています。
- あらゆる原因による死亡リスクが13%低い
- 心臓病や脳卒中による死亡リスクが12%低い
- がんによる死亡リスクが10%低い
- 慢性閉塞性肺疾患などの呼吸器疾患による死亡リスクが35%低い
研究者は、果物と野菜には、特に心臓と血管の健康に強く関与している栄養素が多く含まれていることが理由ではないかと述べています。
2. 多く食べればよいわけではない
ただ、1日に「野菜3食+果物2食」より多く食べても死亡リスクはそれ以上下がらなかったことも報告されています。
寿命を延ばすには複雑な炭水化物も良質な脂肪も必要です。そうした他の食品とのバランスも重要だということではないでしょうか。そのことについては、マインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースの中で詳しくお伝えしています。
フルーツジュースには効果なし

野菜の中でも、効果が期待できないものもありました。
1. でんぷん質の多い野菜
芋類や豆類やトウモロコシなど、デンプン質の多いものにはあまり効果がないことが示されています。
先の7月の研究ではサツマイモのフラボノイドには高い認知機能保護効果があることが示されたものの、この3月の研究ではデンプン質の多い野菜には死亡リスク低減効果があまりないと報告しています。この辺り、悩ましいですね。やっぱり、何事も「ほどほどに」と、いうことなのかもしれませんね。
2. フルーツジュース
また、フルーツはジュースにして摂っても効果がないことが示されています。
ジュースについての詳細は『実はどっちもそれほどヘルシーではなかった!?ジュースとスムージー徹底比較』をご参照ください。
ある日の野菜や果物が少なくても問題はない
こうした研究は何十年にも渡る調査結果を総合判断した話しであって、特定の日の話ではありません。
ですから、例えば、ある日の食事に野菜や果物が少なかったとしても問題はありません。その週を平均して見たら「1日野菜3食+果物2食」くらいになっていることを目指せば良いと、研究者は述べています。
1. ソフィアウッズ・インスティテュートのアプローチ

ソフィアウッズ・インスティテュートのプライベート・ヘルスコーチングも同じです。完璧を目指す必要はないとお伝えしています。人生いろいろあります。本人はそうしたい希望があっても、毎日毎食理想的にできないこともあります。
完璧にやろうとしてストレスに感じたり、理想的な食事ができなかったことで自分を責めたりすることの方が、ずっと心にも体にも健康的とは言えません。
目標とするバランスで食事ができない日があったら、その前後で調節すれば良いのです。
食事は楽しくなければね!
ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス

もしおひとりで取り組むことに不安や難しさを感じるのでしたら、ヘルスコーチと、一度、話をしてみませんか?
公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。
プライベート・ヘルスコーチング・プログラムについて
お気軽にご相談ください。
初回相談を無料でお受けしています。
あるいは、ソフィアウッズ・インスティテュートのマインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースで学びませんか?セルフドクターコースでは、あなたが食を通してご自身の主治医(セルフドクター)になるために、必要な知識とスキルを学びます。
新学期は、毎年3月と9月です。講座でお会いしましょう。

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる
ニュースレターのご登録は、こちらから
統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます
参考文献:
- “Long-term Dietary Flavonoid Intake and Subjective Cognitive Decline in US Men and Women”, Tian-Shin Yeh, Changzheng Yuan, Alberto Ascherio, Bernard A Rosner, Walter C Willett, Deborah Blacker, Neurology, 2021 Sep 7;97(10):e1041-e1056. doi: 10.1212/WNL.0000000000012454. Epub 2021 Jul 28, PMID: 34321362, PMCID: PMC8448553
- “Can flavonoids help fend off forgetfulness?”, Heidi Godman, Executive Editor, Harvard Health Letter, September 17, 2021
- “Fruit and Vegetable Intake and Mortality: Results From 2 Prospective Cohort Studies of US Men and Women and a Meta-Analysis of 26 Cohort Studies”, Dong D. Wang, Yanping Li, Shilpa N. Bhupathiraju, Bernard A. Rosner, Qi Sun, Edward L. Giovannucci, Eric B. Rimm, JoAnn E. Manson, Walter C. Willett, Meir J. Stampfer, Frank B. Hu, 1 Mar 2021, Circulation Vol. 143, No. 17, https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048996Circulation, 2021;143:1642–1654
ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング