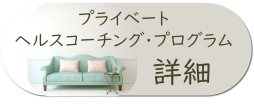バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。
心と体をつなぐホリスティックな食事法について、
ニュースレター登録者限定のキャンペーン情報等も配信しています。
ご登録は、こちらから
もれなく統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます
目次
ピロリ菌は胃粘膜の厚さに応じて胃液を調節している
2015年に『ピロリ菌は病原菌ではなく共生細菌(1)ピロリ菌を除菌すると食道がんの発症リスクが高まる』を執筆してから、7年が経った2022年、とうとうピロリ菌除菌が胃酸過剰や逆流性食道炎などの発症の原因のひとつとして日本消化器病学会のホームページにも掲載されるようになりました。
ピロリ菌を除菌する人が増加するに伴い、胃酸の逆流や逆流性食道炎になる人も増えています。
ピロリ菌を除菌してしまった人の胃には、胃液をコントロールしてくれるピロリ菌がいないため、加齢によって胃粘膜が薄くなっても、胃液は若い時のまま分泌され続けます。結果、胃粘膜の厚さに対して胃液が過剰な状態となります。
胃粘膜が薄くなり始める50代以降のピロリ菌除菌者に、逆流性食道炎が増加し、食道がんも比例するように増えていると、考えられています。
胃酸の逆流が起きているサイン

ピロリ菌の除菌による胃酸過多だけでなく、一般的にも胃酸の逆流は、さまざまな要因によって、意外と起こりがちな症状です。
胃酸が逆流した時に起こる症状がどんなものか知っていますか?
多くの場合、その症状はとても軽いため、何年も自分が胃食道逆流症だと気づかないことがあります。次のような症状は全て、胃酸が逆流しているかもしれないサインです。
- 喉の奥が酸っぱい/苦い
- 膨満感/ゲップ/胃の膨満感
- 胸やけ・・・胸が焼けつくような感覚です。食後に起こることが多く、横になると悪化することがあります。
- しゃがれ声/喉の痛み・・・朝、顕著になります。
- 慢性の咳・・・長く続く咳です。
- 喘息/喘息の悪化
- 歯の侵食・・・歯のエナメル質が溶かされることがあります。
- 胸痛・・・心臓の痛みと間違われることがあります。
- 嚥下障害・・・食べ物が喉や食道に詰まっているような感じがします。
- 喉頭炎・・・しゃがれ声や声の変化を特徴とする炎症です。
- 吐き気
- など
また、『臨床医療ジャーナル(Journal of Clinical Medicine)』 に掲載された研究では、シリアック病をもっている人は、胃食道逆流症を起こしやすいと報告されています。ただし、その理由についてはまだ、明らかになっていません。
胃酸の逆流による夜の咳の予防と改善については『夜の咳』をご参照ください。
胃酸の逆流を放置すると
胃酸の逆流を放置して、それが慢性的になるとバレット食道という病態が現れることがあります。
バレット食道
バレット食道とは、胃の粘膜が食道の方にまで浸食している状態です。
具体的には、食道の扁平上皮が胃の円柱上皮に置き換わってしまっている状態です。症状がないため、胃の内視鏡検査をするまで気がつかないことが多いものです。
バレット食道は、食道腺がんに発展する可能性が高い症状ですから、注意が必要です。
発症率には人種差があり欧米人に多くアジア人に少ないと言われていますが、食の欧米化によって、日本人の発症率も上昇傾向にあると言われています。女性よりも男性に多く発症するがんです。
秋田大学大学院消化器内科学・神経内科学講座が、2013~17年の全国17施設の33,478人(男性20,411人、女性13,067人)の健康診断データを用いて多施設後ろ向きコホート研究を実施し、次の結果を報告しています。
【バレット食道の有病率】
- 男女とも30~70歳代の全年齢層で比較的高い
- 一貫して女性と比べて男性で高い(男性は女性の2.43倍)
- 男性は全年齢層で15~20%と比較的均一な有病率
- 女性は加齢に伴い8%から14%へと上昇
男性では胴回りが大きくなるにつれて、バレット食道の有病率が高くなる傾向があり、肥満との関係が示唆されています。女性ではBMIや胴回りとの関連性はありませんでした。
また、日本人の食道がんの5年生存率は40%ですが、食道腺がんの5年生存率は25%と予後が芳しくないがんです。
胃酸の逆流が起こる原因
ピロリ菌除菌以外で胃酸の逆流が起こる原因には、次の様なものがあります。
- 下部食道括約筋の不調/不全
- 胃酸の分泌を刺激するライフスタイル
- 胃酸の分泌を刺激する食品
- 食道裂溝ヘルニア(食道裂孔を通って胃の一部が胸の方へ飛び出す疾患)
今回は、4.を除き、1~3に共通する対処法、その予防と改善策について最新研究による報告を交えてお伝えします。
なお、裏付けとなる研究論文は、最後に参考文献として一覧にしています。
1. 下部食道括約筋の機能不調/不全

逆流性食道炎は、胃酸の過剰分泌だけでなく、胃酸が少ない人でも起こります。
胃と食道の間には、下部食道括約筋という弁があって、胃酸が食道へ逆流することを防いでくれています。でも、様々な理由で、その弁がちゃんと閉まらないことがあり、胃酸の量が少なくても食道へ逆流してしまうのです。
下部食道括約筋が閉まらなくなる原因
次の疾患や食生活を含むライフスタイルによって弁が機能不全になることが判明しています。
- 喫煙
- ストレス
- うつ病/不安症
- ビタミンB12欠乏/不足
ビタミンB12は、僅かな藻類を除いて、動物性食品にしか含まれていないビタミンです。そのため、動物性食品をあまり食べない人に、ビタミンB12の欠乏や不足が起こりがちです。
たばこを吸っている人やベジタリアン/ヴィーガンの人で、慢性的な胃酸の逆流がある人は、ライフスタイルや食生活の見直しが必要かもしれませんね。
なお、ビタミンB12の詳しい機能と多く含む食品については『ビタミンB12』をご確認ください。
2. 胃酸の分泌を刺激するライフスタイル

胃酸の分泌を刺激するライフスタイルとその改善策についてお伝えします。
1)食後直ぐに横になる
食後直ぐに横になる、あるいは、夕食が遅いために夕食後直ぐにベッドに入る人は、それが胃酸の逆流の原因になることがあります。
食後は少なくとも1~2時間空けてから横になりましょう。
特に夕食は、就寝の3時間前までに終わらせておくことが、寝ている間の逆流予防になるだけでなく、健康的な体重の維持にとっても有効です。
2)運動前に食べ過ぎている
エアロビクスでも、ヨガでも、体を動かす前には、食べ過ぎないことが重要です。
運動中に体をねじったりする動きによって内臓が締め付けられることで、逆流が起こりやすくなります。
3)締め付け機能のある下着や服
胃腸を締めつける下着や服装は、胃酸のスムーズな流れを阻害して、逆流を起こしやすくします。
体型保全のためにと体を締めつけ過ぎる下着や洋服は避け、運動と食生活の見直しをしましょう。
4)仰向けに寝ている
低い枕で仰向けに眠ると胃液の逆流が起こりやすくなります。
就寝中に逆流が起こる場合には、横向きに寝る、あるいは、上体を少し起こして眠るようにしましょう。ただし、枕だけを高くしても効果はありませんので、背中から徐々に上体を起こすことができる、ゆるやかな三角形の枕などがお勧めです。
詳しくは『ウェッジ枕』をご確認ください。
3. 胃酸の分泌を刺激する食品

ビタミンB12(動物性食品)の不足だけでなく、次の食品が胃を刺激し、胃酸の分泌を過剰にすると考えられています。また、それだけでなく、下部食道括約筋の開閉機能を弱らせてしまうことも分かっています。
- 酸味の強い柑橘類
- トマトやトマトの加工食品
- 塩分
- チョコレート(テオブロミンが原因)
- コーヒー(カフェインが原因)
- アルコール
- 炭酸飲料
- 揚げ物
- 辛味の香辛料
- ペパーミント
- ガーリック、玉ねぎ
- 加工食品(天然ではない食品添加物が原因)
胃酸逆流の症状がある人は、こうした食品を務めて避けることが必須です。
また、単なる食べ過ぎによっても胃酸の逆流は起こります。食べ過ぎをコントロールすることも予防のために不可欠です。
更に、食物アレルギーや過敏症がある場合には、胃液が過剰に分泌されることがあると考えられています。
あなたの症状にあった方法を選択する
ドラッグストアには胃酸を抑えるためのたくさんの選択肢があります。でも、そのひとつひとつについてお店で確認していくのはとても面倒なことです。
また、症状が軽度な場合や、時々にしか起こらない場合には、直ぐに薬を飲むのではなく、何か自然な方法で改善させたいと考える人もいらっしゃることでしょう。
そのため、このブログを執筆することにしました。
とはいえ、このブログの内容は、あなたの主治医や薬剤師のアドバイスに代わるものではありません。
もし胃酸の逆流が慢性的に起こっていたり、その症状が重かったり、その他にも胃腸に不調が起きているのでしたら、必ず、病院を受診して検査をしてもらってください。
医薬品であろうと、自然な代替手段であろうと、それぞれに利点と注意点があります。まずナチュラルな方法による改善法をお伝えした後で、医薬品についてお伝えしていきます。
胃酸逆流による不快感を緩和するナチュラルな方法
胃酸の逆流による不快な症状が起きた時に、薬に頼ることなく、一時的にその症状を緩和するためのナチュラルな方法です。

1. マシュマロの根

時々起こる胸やけにお勧めです。
このマシュマロは、白いふわふわしたお菓子のマシュマロとは関係ありません。まったく異なる食品です。マシュマロの根の樹液には、消化器官を保護する粘液(水溶性食物繊維)が多く含まれています。
メリーランド大学メディカル・センターと『The New Holistic Herbal(新しいホリスティック・ハーブ)』の著者デイヴィッド・ホフマン氏もそのご著書の中で、マシュマロの根を乾燥させた粉末を使ったマシュマロ茶を勧めています。
注意:血糖値や水分バランスに影響を与える可能性があるため、糖尿病薬や利尿剤を服用している人にはお勧めできません。
2. 重曹

胃酸過多による急な胸やけや胃痛の応急処置として最適です。
胃をアルカリ化することで、胃痛や胸やけを和らげる制酸剤としてよく知られているものです。ただし、胃炎や食道炎を治すものではなく、あくまでも痛みや不快感を一時的に解消させるものです。
小さじ1杯半くらいをコップ一杯の水に溶かして飲みます。
注意:ナトリウムを含んでいるので、心血管系に問題のある人や高血圧の人にはお勧めできません。また、日常的に飲用することもお勧めできません。
重曹を自然療法に使う方法については『重曹の7つの用途』もご参照ください。
3. アロエジュース

胃の不快感の予防や緩和にお勧めです。
アロエのジュースには、逆流の鎮静作用と抗炎症作用があります。胃の内壁を癒し、胃酸逆流による炎症を軽減します。(アロエの詳しい機能については『アロエ』をご確認ください。)
フレッシュなアロエの葉の皮をむき、ブレンダーで1/4カップの水といっしょに混ぜてスムージーにして、食前に飲みます。ただし大量に飲むとお腹を下す場合がありますので、少しずつ試してくださいね。
注意: 必ず食用のアロエベラを用いることが重要です。一部のアロエの種類の葉には、強力な下剤作用がある成分が含まれています。
4. マスチックガムを噛む
症状は軽いものの、食事と食事の間に、胃酸の逆流が起こる人にお勧めです。
マスチックガムは、マスティックという低木の樹液から作られる天然の食用ガムです。噛むとヒノキに似た香があり、「キリストの涙」とも呼ばれているものです。
古代ギリシア時代から、虫歯や歯周病や口臭の予防など口腔内の健康と、胃痛、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの治療に用いられてきました。近年では、抗炎症作用と抗菌作用があることや、ピロリ菌に効果があることが報告されているものです。胃の内壁を癒し炎症を軽減します。
唾液の分泌が促され、唾液が食道に定期的に流れることで、胃液の逆流を防止します。
注意:樹液にアレルギーがある人は、使用しないでくださいね。
5. アップルサイダービネガー(リンゴ酢)

比較的軽い症状の緩和に適しています。
胃酸の逆流に「酢」というのは、直感に反するように思えるかもしれません。
でも、アップルサイダービネガー(リンゴ酢)は、胃の酸性度のバランスを整え、消化を助ける機能があると考えられています。実際、酢には体内をアルカリ化する作用があります。
注意:アップルサイダービネガーは、必ず水で薄めてから飲用にしてください。そのまま飲むことで、胃潰瘍や食道炎を悪化させてしまう可能性があります。
胃酸逆流による炎症を予防改善するナチュラルな方法
一時的な症状の緩和だけでなく、胃酸によって炎症が起きた胃を補修し、炎症が起きにくい胃にするための食事です。

ピロリ菌除菌で起きた逆流性食道炎の根本治癒には、ピロリ菌への再感染が有効ですが、ピロリ菌は今のところ再感染も移植もできないことが判っています。移植してもそのうちに体の外に出て行ってしまうのだそうです。
でも、私たちは食べたものでできています。胃の粘膜も胃壁もあなたが食べたもので作られています。だから、食べるものを変えることによって、粘膜や胃壁を修復して、炎症が起こりにくくすることができるはずです。
そして、炎症を軽くして胃壁を修復することができれば、どんな理由によって起きた胃酸の逆流であっても、食道がんを予防できるはずです。
1. ゆっくりと腹八分目
基本は適正体重を保つことです。
そのためには、腹八分目に食べることを意識しましょう。前述した通り、食べ過ぎによっても胃酸の逆流は起きます。
胃への圧力が高まるのを防ぐため、少量ずつ頻繁に食事を摂りましょう。
2. 腹式呼吸をする
お腹から深い呼吸をしましょう。
あなたは、自分でも気がつかないうちに1日の間に頻繁に息を止めています。
意識して腹式呼吸をすることで、横隔膜が強化され、消化と胃酸の逆流の調節の両方に役割を果たしている迷走神経がリセットされます。
3. 胃酸の分泌を刺激する食品を避ける
前述した胃酸の分泌を刺激する食品を極力避ける努力が必要です。

4. アルカリ性の食品
アルカリ性で低脂肪、消化しやすい食品を選びましょう。
例えば、次のような食品です。

- オートミール、白米、バナナ、蒸し野菜、皮なし鶏肉、柑橘類以外の果物
- アボカドやオリーブオイルなどの健康的な脂肪(適量)
- 酸性でないハーブティー(カモミールティーやマシュマロティーなど)
- など
5. ヌメリのある食品
動物の粘膜や唾液などに含まれているネバネバしたヌメリのある物質は、ムチンと呼ばれる成分です。ほとんどの動物の粘液に含まれています。私たちの胃粘液や腸粘液もムチンでできています。

ヌメリのある植物性食品のネバネバの成分は、水溶性食物繊維のひとつで、こちらもムチンと呼ばれることがありますが、こちらは高分子の多糖類とたんぱく質が結合したもので、動物の粘液に含まれるムチンとは異なります。
しかし、動物性でも植物性でも、食品中のネバネバした成分は、粘膜を潤し強化する働きがあるため、次の効果があると考えられています。
- 食道や胃の粘膜を助け細胞膜を保護する
- 傷ついた食道や胃の粘膜を修復する
その結果、食道炎や胃潰瘍・胃炎を予防したり、回復する効果があると考えられているのです。
東洋医学においてもヌメリのある食品には、次の効果があると考えられています。
- 鼻の粘膜を強化菌
- 腎臓・肝臓機能の向上
- 細胞の活性化
なお、オクラの詳しい機能については以前記事にしていますので『オクラ』をご参照ください。
また、ネバネバ成分を直接食べる以外にも、胃や腸の粘膜ムチンの素となる成分を多く含む食品については『腸粘膜の栄養戦略』をご参照ください。
6. 亜鉛カルノシン
亜鉛カルノシンは、亜鉛とカルノシンという2つの栄養素を融合させた物質です。

亜鉛カルノシンが腸の内壁の粘膜を補修して、消化器官の不快感や炎症、胃痛、胸やけ、消化不良、吐き気、膨満感を解消させること、臨床研究においても、胃腸疾患の患者に有効に働き、胃の共生細菌のバランスを保つことが報告されています。
カルノシンは、鶏肉、馬肉、豚肉に多く含まれているアミノ酸が2つ結合して造られているジペプチドです。筋肉の中で瞬発力を高める働きがあり、アンチエイジングや疲労回復に効果があると考えられています。
亜鉛は、主に海藻類に多く含まれています。亜鉛の詳しい機能と多く含む食品は『亜鉛』をご確認ください。
亜鉛カルノシンは、サプリメントとして購入することができますが、日々の食事の中にカルノシンや亜鉛を多く含む食品を取り入れることでも同じですから、食事をすることを第一に考えていただければと思います。
注意:亜鉛カルノシンのサプリメントは、特定の抗生物質や利尿剤と相互作用する可能性があるため、何かしらの医薬品を処方されている人は、サプリメント服用前に医師・薬剤師に必ず相談してください。
7. ビタミンCとβカロテン
ビタミンCは、胃がんや食道がんの発病率を下げる機能があり、βカロテンには、細胞を守り、体内の粘膜を強化する働きがあります。そのため、その両方を豊富に含む食品を一覧にしてみました。

ビタミンCについては、厚生労働省が日本人の摂取基準を定めているので、その1日の必要量の10%以上を100g中に含むものに限定し、その中で、βカロテン含有量が多いものを表にしています。また、亜鉛まで1日の必要量の10%以上を含んでいるものには★印をつけました。
ビタミンCの詳しい機能と多く含む食品については『ビタミンC』をご確認ください。
また、上の表以外でβカロテンを多く含む果物は次の通りです。

果物以外で、βカロテンを多く含む食品は下の画像の通りです。

β-カロテンは、サプリメントで摂ると危険になる病気がありますので、必ず、食品を食べてくださいね!
詳しくは『β-カロテン』をご確認ください。
8. 発酵食品
発酵食品には、健康にとって良い働きをする善玉菌が多く含まれていますが、一部の善玉菌には、ヒスタミンを増加させ胃酸の分泌を促しガスを発生させる働きがあります。そのため、逆流性食道炎や胃食道逆流症の症状が悪化してしまいます。
一方で、胃酸とガスを減少させる作用をもっている善玉菌もいます。
逆流性食道炎/胃食道逆流症の改善に良い菌は次の通りです
- ビフィズス菌インファンティス| 消化を改善し、ガス、膨満感、腹部の不快感を軽減
- ビフィズス菌ロンガム| 全体的な炎症を軽減し、敏感な消化と逆流に有効
- ビフィズス菌ブレーベ| 下部消化管のガス圧を軽減し、逆流の主な原因である腹腔内圧を低下
- 乳酸菌ラムノサスGG| 消化を改善し、微生物の多様性を高めて炎症を鎮めることで逆流を緩和する
- 乳酸菌プランタラム(の一部の亜種のみ)| ガスと腹部膨満感を軽減(効果は特定の亜種によって異なる)
ビフィズス菌属は大抵の発酵食品に含まれていますが、乳酸菌プランタラムは、野菜(植物性食品)の発酵食品にしか含まれていません。
逆流性食道炎/胃食道逆流症の人が避けた方が良いヒスタミンを多く発生させる菌は次の通りです
- 乳酸菌カゼイ
- 乳酸菌ブルガリクス
- 乳酸菌ロイテリ
- など
スーパーなどでヨーグルトを購入する際には、気を付けたいですね。
胃酸の逆流改善薬の問題点
胃酸の逆流を改善するための薬(制酸剤や胃酸遮断薬)の中には、ビタミンやミネラルの吸収を妨げるものがあります。
これらは胃のpHを変化させ、食物から抽出された栄養素を含むあらゆるものの吸収を妨げるため、どの栄養素であっても、それを欠乏させてしまう危険性がある薬です。
また、こうした薬の慢性的な使用は、胃の内容物のスムーズな移動を遅らせ、消化機能不全や麻痺を引き起こす可能性があります。
最後に、多くの制酸剤や胃酸遮断薬(プロトンポンプ阻害剤/ブロッカー)は、グルテンや乳製品への過敏症を引き起こす可能性があると考えられています。
プロトンポンプ阻害薬の詳しい影響については『プロトンポンプ阻害薬(PPI)』をご確認ください。
また、一般的にドラッグストアにある制酸剤と医師から処方される胃酸遮断薬(PPI)の利点と注意点について、ホリスティック薬剤師のスージー・コーエン先生がひとつひとつの製品に簡単な説明をしてくださっています。『制酸剤/遺産逆流改善薬それぞれの長所と短所』をご確認ください。
そして、必ず、かかりつけの医師や薬剤師さんに相談してくださいね。
ソフィアウッズ・インスティテュートからのアドバイス

今回は、胃酸の逆流に関して、さまざまな情報をお伝えしました。あなたの胃酸が逆流する「理由」が何であれ、この問題がたまに起きる不快な症状以上になった場合は、食生活を見直す機会です。
お薬を処方してもらっていてもいなくても、あなたは1日に3食は食べるのです。その食事が、不快な症状を予防したり緩和したりするものでなければなりません。
ぜひ、お伝えした食品や方法を取り入れてみてくださいね。
でももし、おひとりで取り組むことに不安や難しさを感じるのなら、ヘルスコーチと、一度、話をしてみませんか?
公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。
プライベート・ヘルスコーチング・プログラムについて
お気軽にご相談ください。
初回相談を無料でお受けしています。
あるいは、ソフィアウッズ・インスティテュートのマインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースで学びませんか?セルフドクターコースでは、あなたが食を通してご自身の主治医(セルフドクター)になるために、必要な知識とスキルを教えています。
新学期は、毎年3月と9月です。講座でお会いしましょう。

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる
ニュースレターのご登録は、こちらから
統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます
参考文献:
- “What Your Doctor Didn’t Tell You About GERD”, Amy Myers, MD
- “Age distribution and risk factors for Barrett’s esophagus by sex at health check-up settings in Japan.”, Fukuda S, Watanabe K, Kubota D, Yamamichi N, Takahashi Y, Watanabe Y, Adachi K, Ishimura N, Koike T, Sugawara H, Asanuma K, Abe Y, Kon T, Ihara E, Haraguchi K, Otsuka Y, Yoshimura R, Iwaya Y, Okamura T, Manabe N, Horiuchi A, Matsumoto M, Onochi K, Takahashi S, Yoshida T, Shimodaira Y, Iijima K., J Gastroenterol. 2025 Feb 10. doi: 10.1007/s00535-025-02222-2. Epub ahead of print. PMID: 39928142.
- “Seven Foods that Trigger GERD”
- “Home Remedies for Acid Reflux”
- “15 Natural Remedies To Treat Acid Reflux and Ulcers”, Dave Mihalovic, Apr 5, 2014
- “7 Annoying Reasons You’re Burping Too Much”, Suzy Cohen
ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング