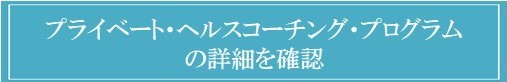バイオ個性で食べて、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるホリスティックな食事法をコーチングする、ソフィアウッズ・インスティテュート代表 公認統合食養ヘルスコーチ(CINHC)、公認国際ヘルスコーチ(CIHC)の森ちせです。
心と体をつなぐホリスティックな食事法について、
ニュースレター登録者限定のキャンペーン情報等も配信しています。
ご登録は、こちらから
もれなく統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます
目次
バイオ個性にヒントがある
抗がん剤などの治療薬は、必ずしも万人に対して同じ様に効くとは限りません。なぜ、効かない人達がいるのでしょうか。
2017年8月31日の科学専門誌『ネイチャー』には、免疫療法が効かないがん患者の腫瘍には、免疫T細胞が分泌するタンパク質(アペリン)の機能を喪失させる遺伝子変異が起きていたことを発見したことが報告されていました。
なぜ、どのようにして、遺伝子変異が起きたのかについては、まだ不明です。
ただ、2017年6月6日のネイチャーに掲載された論文にヒントがあるように思い、要約しながらお伝えします。
この論文を読んで、統合食養学が大切にしている、バイオ個性に沿って食べることの重要性を改めて感じました。
ヒトゲノムによるパーソナル・メディシンの限界

ヒトゲノム
従来の個別化医療(パーソナル・メディシン)の研究は、特定の薬に対する体の反応を、個々人のゲノム(遺伝子)に合わせてコントロールすることに焦点があてられてきました。
マイクロバイオーム
一方、近年、特定の薬が、ある人に効くのかどうかを判別するために、個々人に固有の共生細菌のゲノム(マイクロバイオーム)が、鍵となり得ることを示す証拠が蓄積されています。
6月4日、米国ルイジアナ州のニューオリンズで開かれた米国生物学会(the American Society for Microbiology)の会合では、
健康な人であっても、
共生細菌の構成の違いによって
薬を代謝する過程が異なる
と、いう証拠データが提出されました。
つまり、ヒトの遺伝子に合わせて薬を造るだけでは十分ではなく、腸内細菌の遺伝子に合わせて薬を造ることが必要であることが示されたのです。
腸内細菌の顔ぶれはひとりひとり異なる
人間に共生しているバクテリア(共生細菌)は、そこに存在する栄養を食べて生きています。「そこに存在する栄養」つまりそれは、私達(宿主)が食べる食事です。
宿主が好んで食べる食事を、好んで代謝する細菌が、結果として腸内に残り、多く繁殖するのです。
当然、私達ひとりひとりが好む食事によって、腸内に棲む細菌の顔ぶれも変わることになります。
医薬品の構造を変容させてしまう腸内細菌がいる

通常、薬は、肝臓のグルクロン酸抱合と呼ばれる化学物質群を通して無毒化され代謝されます。しかし、ある種の腸内細菌が発する酵素が、グルクロン酸抱合群を除去してしまい、薬を有毒化することが判明しました。
ニューヨーク市にあるアルバートアインシュタイン医科大学(the Albert Einstein College of Medicine)の数理分析生物学者のリー・ガスリー(Leah Guthrie)博士は、特定の患者に下痢などの副作用を起こしてしまうイリノテカンと呼ばれる抗がん剤について論じています。
具体的には、マウスを使った研究で、ある種の腸内細菌が産生するβ-グルクロニダーゼと呼ばれる酵素が、イリノテカンや他の薬の化学構造を変化させてしまうことが観察されたのです。
ガスリー博士と共同研究者達は、ヒトの腸内細菌が薬をどのように代謝するのかを見極めるために、20人の健康な人達から大便のサンプルを採取し、それにイリノテカンを混ぜ、イリノテカンに接触した腸内細菌が産生した物質を調べると、4つのサンプルから、高度に有毒化したイリノテカンが検出されました。
更に、その腸内細菌が産生したタンパク質を分析すると、次の特徴がありました。
- 代謝の高い腸内細菌を有している人達に、β-グルクロニダーゼをつくる腸内細菌が多いこと
- 同時に、糖分を細胞に輸送するタンパク質(グルコース・トランスポーター)を高い水準で保有していること
また、有毒化したイリノテカンを発生したサンプル(糞便)の所有者たちは、毒物を吸収しやすく、消化器官に問題を起こしやすい人達だということが示唆されています。
β-グルクロニダーゼの影響は広範に及ぶ可能性

イリノテカンだけでなく、グルクロン酸抱合群を利用して、肝臓は様々な薬を処理します。
ある種の腸内細菌が産生するβ-グルクロニダーゼが、グルクロン酸抱合群を排除し、他の薬をも有毒化するとしたら、影響はかなり広範に及ぶ可能性を、研究者は示唆しています。
抗炎症性医薬品
ある種のβ-グルクロニダーゼが、イブプロフェンなどの抗炎症性の薬を変容させ、長期間の使用によって腸内で毒性を発生させてしまうことが既に観察されています。
パーキンソン病薬/抗不安薬
腸内細菌が、パーキンソン病や抗不安薬などの医薬品を変容させることを示唆する多くの事例が既に報告されています。
HIV予防薬
6月2日に発表された論文では、膣の中に塗るジェルタイプのHIV予防薬テノフォヴィルは、ガードネレラ菌を膣内にもっている女性には効果がないと報告しています。この細菌は、薬を素早く分解し不活性化させてしまうとのことです。
創薬への示唆

「医薬品を開発する際、動物実験段階では毒性が見られないのに、ヒトで毒性をもってしまう化合物がなぜあるのかを腸内細菌による干渉よって説明できるかもしれない。なぜなら、動物はヒトとは異なる腸内細菌をもっているのだから」
と、ハーバード大学の生化学者エミリー・バルスカス(Emily Balskus)博士は言います。
しかしまだ多くのことが疑問として残っています。例えば、薬を崩壊させてしまう腸内酵素を、まだほとんど特定できていません。
腸内細菌と医薬品との相互作用を理解し、医者が治療の一環として処方できるようになるまでには、もう少し時間がかかるかもしれません。
でもその内に、腸内細菌のスクリーニングができるようになり、どの菌を持っている人には、どの薬が効くのか判定できるようになるかもしれません。
特殊な食事療法が鍵になる
「もし腸内細菌が問題を起こしそうであれば、腸内細菌の酵素の発生を抑制する薬を処方したり、あるいは、腸内細菌の構成を変えるための特殊な食事療法を提供できるようになるかもしれない。」
と、バルスカス博士は言います。
心臓病薬(ディゴキシン)のケース
あるマウスを使った実験では、食事療法によって腸内細菌の顔ぶれを変更したことで、ディゴキシンと呼ばれる心臓病薬の構造が壊されなかったことが報告されています。
統合食養学のバイオ個性に沿った食事

統合食養学には「バイオ個性」という考え方があります。私達はひとりとして同じではないという考え方です。遺伝子構成がまったく同じ一卵性双生児も、バイオ個性は異なるとのアプローチを執ります。
私はこのバイオ個性というアプローチは、つきつめたらマイクロバイオーム(共生細菌のゲノム)のことなのではないかと思っています。
遺伝子では1%しか説明できない
私達は、私達自身の遺伝子だけでなく、その100倍もの共生細菌のゲノムから影響を受けて生きています。(詳しくは『バクテリア・コミュニケーション』をご参照ください。)
ヒトゲノムの解析から得た情報だけでは、私達の体の反応について1%くらいしか分からないということです。つまり、病気が起きた原因も、薬の副作用の原因も、私達自身の遺伝子だけでは99%が説明不可能だということです。
エピジェネティクス要因
既に多くのエピジェネティクス(ゲノムの発現に影響を与える環境要因)の研究によって、食事やその他のライフスタイル要因(運動や飲酒・喫煙などの習慣)を変えることによって、特定の遺伝子のスイッチをオンにしたりオフにしたりできることが報告されています。
食事やライフスタイル要因は、私達自身の遺伝子のスイッチのオン/オフだけでなく、腸内細菌の顔ぶれも変えます。
詳しくは、『腸内細菌の構成は遺伝(変えられない)と食事(変えられる)のどっちで決まる?』をご確認ください。
統合食養学は社会的なつながりも考慮する

統合食養学の考えるバイオ個性は、ひとりひとりの遺伝子的な要因や食事とライフスタイル要因だけでなく、個人の人間関係、仕事/キャリア、季節や土地との調和なども考慮します。そして、バイオ個性は、時と共に変化していくものです。
だから、ひとりとして同じではないのです。
そして、私達の体の内外で共生している細菌達の顔ぶれも、
- 食事
- ライフスタイル
- 人間関係
- 仕事/キャリア
- 季節
- 土地
によって変化します。
そして、共生細菌の顔ぶれは、私達の心の状態にも影響を与えます。詳しくは、『マイクロバイオータ(共生細菌・腸内ミクロフローラ)が私達の世界観を左右する』をご参照ください。
統合食養学はバイオ個性に沿って食べることを最優先します

あなたのバイオ個性に沿った食事をすることで共生細菌の顔ぶれを変えることができます。
腸内細菌に関する最新の食事戦略については『炎症性腸疾患(IBD)・壊死性腸炎・大腸がんを予防・改善する腸内細菌と腸粘膜の栄養戦略』もご参照ください。
バイオ個性は、ひとりひとり異なります。誰かと同じではない、あなたのための食事やライフスタイル、バイオ個性に沿って生きることが大切なのです。
公認ホリスティック・ヘルスコーチは、食事だけでなく、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮して、プログラムに反映させ、あなたが、なりたいあなたになれるようコーチングを提供します。
ヘルスコーチと、一度、話をしてみませんか?
プライベート・ヘルスコーチング・プログラムについて
お気軽にご相談ください。
初回相談を無料でお受けしています。
あるいは、ソフィアウッズ・インスティテュートのマインド・ボディ・メディシン講座セルフドクターコースでは、あなたが食を通してご自身の主治医(セルフドクター)になるために、必要な知識とスキルを教えています。
新学期は、毎年3月と9月です。講座でお会いしましょう。

心と体をつないで健康と幸せを手に入れる
ニュースレターのご登録は、こちらから
統合食養学(ホリスティック栄養学)冊子が無料ダウンロードできます
参考文献:”Gut bacteria can stop cancer drugs from working“, 06 June 2017, Sara Reardon
ソフィアウッズ・インスティテュート – ホリスティックヘルスコーチング