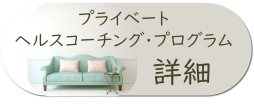гғҗгӮӨгӮӘеҖӢжҖ§гҒ§йЈҹгҒ№гҒҰгҖҒеҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҺгҖҒеҒҘеә·гҒЁе№ёгҒӣгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒӘйЈҹдәӢжі•гӮ’гӮігғјгғҒгғігӮ°гҒҷгӮӢгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲд»ЈиЎЁгҖҖе…¬иӘҚзөұеҗҲйЈҹйӨҠгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒпјҲCINHCпјүгҖҒе…¬иӘҚеӣҪйҡӣгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒпјҲCIHCпјүгҒ®жЈ®гҒЎгҒӣгҒ§гҒҷгҖӮ
еҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒӘйЈҹдәӢжі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒ
гғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјзҷ»йҢІиҖ…йҷҗе®ҡгҒ®гӮӯгғЈгғігғҡгғјгғіжғ…е ұзӯүгӮӮй…ҚдҝЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ”зҷ»йҢІгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮү
гӮӮгӮҢгҒӘгҒҸзөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰпјҲгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜж „йӨҠеӯҰпјүеҶҠеӯҗгҒҢз„Ўж–ҷгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ
зӣ®ж¬Ў
- еҘіжҖ§гҒҢжӣҙе№ҙжңҹгҒ гҒЁж°—гҒҘгҒҸгҒҫгҒ§гҒ«зҙ„1е№ҙд»ҘдёҠгҒӢгҒӢгӮӢ
- жӣҙе№ҙжңҹгҒ®е§ӢгҒҫгӮҠгҒҜгҒ„гҒӨпјҹ
- жӣҙе№ҙжңҹгҒ®з”ҹзҗҶ
- жӣҙе№ҙжңҹгҒ®з—ҮзҠ¶гҒҜгғӣгғғгғҲгғ•гғ©гғғгӮ·гғҘд»ҘдёҠ
- гӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒ®жёӣе°‘гҒҢиө·гҒ“гҒҷеҪұйҹҝ
- жёӣе°‘гҒҷгӮӢгӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒЁеў—еҠ гҒҷгӮӢдҪ“еҶ…зӮҺз—ҮгҒЁд»ҳгҒҚеҗҲгҒҶгҒ«гҒҜ
- гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒӢгӮүгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№
еҘіжҖ§гҒҢжӣҙе№ҙжңҹгҒ гҒЁж°—гҒҘгҒҸгҒҫгҒ§гҒ«зҙ„1е№ҙд»ҘдёҠгҒӢгҒӢгӮӢ
з”ҹзҗҶгӮ„з”ҹзҗҶз—ӣгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒеҰҠеЁ гӮ„еҰҠеЁ дёӯгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ®жғ…е ұгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒдҪ“гҒ«гҒ©гӮ“гҒӘеӨүеҢ–гҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒ®гҒӢзӯүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©ігҒ—гҒ„ж§ҳгҖ…гҒӘжғ…е ұгӮ’еҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ§гӮӮгҖҒеҘіжҖ§гҒ®дәәз”ҹгҒ®дёӯзӣӨгҒ§иө·гҒ“гӮӢгҖҢй–үзөҢгҖҚгҒЁгҖҒгҒқгҒ“гҒ«иҫҝгӮҠзқҖгҒҸгҒҫгҒ§гҒ®зҠ¶ж…ӢпјҲжӣҙе№ҙжңҹпјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠеӨ§гҒҚгҒӘеЈ°гҒ§иӘһгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒ©гӮ“гҒӘеӨүеҢ–гҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒ®гҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®жғ…е ұгӮӮгҒӘгҒӢгҒӘгҒӢиҰӢгҒӨгҒӢгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
з§ҒиҮӘиә«гӮӮ40д»ЈгҒ®дёӯй ғгҒӢгӮүгҖҒе°‘гҒ—гҒҡгҒӨгҖҒгҒ„гҒҫгҒҫгҒ§гҒЁгҒҜйҒ•гҒҶдҪ“иӘҝгҒ®еӨүеҢ–гҒҢж°—гҒ«гҒӘгӮҠе§ӢгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҹгҒ гҖҒеҪ“жҷӮгҖҒдјҒжҘӯиІ·еҸҺгҒӘгҒ©гҒЁгҒ„гҒҶи¶…гӮ№гғҲгғ¬гӮ№гғ•гғ«гҒӘд»•дәӢгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҰж…ўжҖ§зҡ„гҒӘзқЎзң дёҚи¶ігҖҒйҒӢеӢ•дёҚи¶ігҖҒз–ІеҠҙж„ҹгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒйЈҹдәӢгҒҜгӮҖгҒЎгӮғгҒҸгҒЎгӮғгҒ§гҒ—гҒҹгҒӢгӮүдҪ“иӘҝдёҚиүҜгҒ®еҺҹеӣ гҒҢгҒӮгӮҠйҒҺгҒҺгҒҰгҖҒгҒҹгҒҫгҒ«гҖҢжӣҙе№ҙжңҹпјҹгҖҚгҒЁз–‘е•ҸгҒ«жҖқгҒЈгҒҰиӘҝгҒ№гҒҰгҒҝгҒҰгӮӮгҖҒгҖҢгҒ“гӮҢгҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҹж¬ІгҒ—гҒ„жғ…е ұгӮӮгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҖҒгҒҶгӮ„гӮҖгӮ„гҒ«гҒ—гҒҰйҒҺгҒ”гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒӮгҒӘгҒҹгҒҜгҒ©гҒҶгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
гғҸгғјгғҗгғјгғүеӨ§еӯҰжҸҗжҗәгҒ®гғ–гғӘгӮ¬гғ еҘіжҖ§з—…йҷўгҒ®дёӯе№ҙжңҹпҪһй–үзөҢжңҹгҒ®е°Ӯй–ҖеҢ»гғҳгӮ¶гғјгғ»гғҸгғјгӮ·гғҘеҢ»её«гҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒдҪ“гҒ«иө·гҒ“гӮӢдёҚеҸҜи§ЈгҒӘз—ҮзҠ¶гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒҢжӣҙе№ҙжңҹгҒ®гҒӣгҒ„гҒ гҒЁж°—гҒҘгҒҚгҖҒеҘіжҖ§гҒҢеҜҫеҮҰгҒ—е§ӢгӮҒгӮӢгҒҫгҒ§гҒ«гҒҜгҖҒеӨ§жҠө1е№ҙд»ҘдёҠгҒӮгӮӢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
зўәгҒӢгҒ«гҒқгҒҶгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
з§ҒгӮӮгҖҢгҒ“гӮҢгҒЈгҒҰжӣҙе№ҙжңҹгҒ®е§ӢгҒҫгӮҠгҒӘгҒ®пјҹгҒқгӮҢгҒЁгӮӮгҒҹгҒҫгҒҹгҒҫпјҹж°—гҒ®гҒӣгҒ„пјҹгҖҚгҒЁжҖқгҒ„е§ӢгӮҒгҒҰгҒӢгӮүгҖҒиҮӘеҲҶгҒҢжӣҙе№ҙжңҹгҒ«е…ҘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒЁзўәдҝЎгҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҖҒдҪ•е№ҙгӮӮпјҲпј‘е№ҙгӮҲгӮҠгӮӮгҒӢгҒӘгӮҠгӮӮгҒЈгҒЁпјүгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҺҹеӣ гҒҢдҪ•гҒӘгҒ®гҒӢеҸ–гӮҠж•ўгҒҲгҒҡзӣҙгҒҗгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒ°гҖҒгӮӮгҒЈгҒЁдёҚе®үгҒҢжёӣгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ«гҒӯгҖӮ
жӣҙе№ҙжңҹгҒ®е§ӢгҒҫгӮҠгҒҜгҒ„гҒӨпјҹ
гҒ“гӮҢгҒ§гҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮҢгҒ°гҖҒгҒҡгҒЈгҒЁгӮӮгҒЈгҒЁе®үеҝғгҒ—гҒҰжҡ®гӮүгҒӣгӮӢгҒ®гҒ«гҖҒд»ҠгҒ®з§‘еӯҰгҒ§гҒҜгҒ“гӮҢгӮ’дәҲиЁҖгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮ“гҒ§гҒҷгҖӮ
й–үзөҢгҒ®еүҚеҫҢ5е№ҙй–“гҖҒ45жӯіпҪһ55жӯігҒҸгӮүгҒ„гҒ®жңҹй–“гӮ’гҖҒжӣҙе№ҙжңҹгҒЁе‘јгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢй–үзөҢгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгҖҢз”ҹзҗҶгҒҢжӯўгҒҫгӮӢгҖҚгҒ“гҒЁгҒ гҒЁиЁҖгҒҶгҒ“гҒЁгҒҜзҡҶзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ§гӮӮгҖҒгҒ„гҒӨжӯўгҒҫгӮӢгҒ®гҒӢгҒҜеҢ»иҖ…гҒ«гӮӮиӘ°гҒ«гӮӮеҲӨгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒгҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒқгҒ®зҙ„5е№ҙеүҚгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢжӣҙе№ҙжңҹгҒ®е§ӢгҒҫгӮҠгӮ’дәҲжё¬гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
ж—Ҙжң¬дәәеҘіжҖ§гҒ®е№іеқҮй–үзөҢе№ҙйҪўгҒҜгҖҒ50.5жӯігҒ§гҒҷгҖӮгҒЎгҒӘгҒҝгҒ«гӮўгғЎгғӘгӮ«дәәгҒ®е№іеқҮгҒҜ52жӯігҒ§гҒҷгҖӮгҒ§гӮӮгҖҒ50.5жӯігҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮүгҖҒзӘҒ然гҖҒз”ҹзҗҶгҒҢжӯўгҒҫгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
жӣҙе№ҙжңҹгҒ®з”ҹзҗҶ

гҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжғ…е ұгӮӮгҒӮгҒҫгӮҠгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚиӘҝгҒ№гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢжңүзӣҠгҒ гҒЁжҖқгҒҲгӮӢжғ…е ұгҒ«еҮәдјҡгҒҲгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒж•ўгҒҲгҒҰгҒ“гҒ“гҒ«жӣёгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
жӣҙе№ҙжңҹгҒ«е…ҘгӮӢгҒЁгҖҒе№іеқҮ7ж—Ҙй–“гҒӮгҒЈгҒҹз”ҹзҗҶжңҹй–“гҒҢ次第гҒ«зҹӯгҒҸгҒӘгӮҠпј“ж—ҘгҒЁгҒӢ4ж—ҘгҒ§зөӮгӮҸгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёҖж–№гҒ§гҖҒз”ҹзҗҶе‘ЁжңҹгҒҢйҖҹгҒҫгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зөҢйЁ“гҒҷгӮӢеҘіжҖ§гҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒҜгҖҒз”ҹзҗҶгҒҢйҒ…гҒҸгҒӘгӮӢгҒЁжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжӣҙе№ҙжңҹгҒ®еүҚеҚҠгҒ§гҒҜгҖҒгҒқгҒ®йҖҶгҖҒд»ҠгҒҫгҒ§28ж—ҘпҪһ30ж—Ҙе‘ЁжңҹгҒ§жқҘгҒҰгҒ„гҒҹгӮӮгҒ®гҒҢгҖҒ25ж—ҘгҒЁгҒӢ20ж—ҘгҒ§жқҘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
з§ҒгҒҜеҪ“жҷӮгҖҒжӣҙе№ҙжңҹгҒ§гҒҜз”ҹзҗҶгҒҢйҒ…гҒҸгҒӘгӮӢгҒЁжҖқгҒ„иҫјгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒз”ҹзҗҶе‘ЁжңҹгҒҢйҖҹгҒҫгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹжҷӮгҒ«гҒҜдҪ•гҒӢеҲҘгҒ®з—…ж°—гҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁдёҚе®үгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгӮ“гҒӘгҒ“гӮ“гҒӘгҒҢдҪ•е№ҙгҒӢз¶ҡгҒ„гҒҹеҫҢгҖҒзҡҶгҒ•гӮ“гҒҢдәҲжғігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢйҖҡгӮҠгҖҒз”ҹзҗҶе‘ЁжңҹгҒҜ次第гҒ«пј’гҒӢжңҲгҒ”гҒЁгҖҒ3гҒӢжңҲгҒ”гҒЁгҖҒеҚҠе№ҙгҒ”гҒЁгҒЁй•·гҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰжңҖеҫҢгҒ«з”ҹзҗҶгҒҢжқҘгҒҰгҒӢгӮү1е№ҙд»ҘдёҠз”ҹзҗҶгҒҢжқҘгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮүгҖҢй–үзөҢгҖҚгҒҢе®ЈиЁҖгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
з…©гӮҸгҒ—гҒ„жҜҺжңҲгҒ®гӮӨгғҷгғігғҲгҒӢгӮүгҒ®и§Јж”ҫгҒ§гҒҷгҖӮ
жӣҙе№ҙжңҹгҒ®з—ҮзҠ¶гҒҜгғӣгғғгғҲгғ•гғ©гғғгӮ·гғҘд»ҘдёҠ

жӣҙе№ҙжңҹгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӘһгӮүгӮҢгӮӢжҷӮгӮҲгҒҸиҖігҒ«гҒҷгӮӢдёҚиӘҝгҒ«гҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- гғӣгғғгғҲгғ•гғ©гғғгӮ·гғҘпјҲгҒ”еҸӮиҖғгҒ«гҖҺгғӣгғғгғҲгғ•гғ©гғғгӮ·гғҘгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢгғҠгғҒгғҘгғ©гғ«гғ¬гғЎгғҮгӮЈгҖҸпјү
- жғ…з·’дёҚе®үе®ҡпјҸж°—еҲҶгҒ®гғ гғ©
- иҶЈгҒ®д№ҫзҮҘпјҸиҶЈгҒ®з—ӣгҒҝ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжӣҙе№ҙжңҹгҒ®з—ҮзҠ¶гҒҜгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ«з•ҷгҒҫгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҹгҒЈгҒҹ2пҪһ3е№ҙеүҚгҒҫгҒ§еҒҘеә·гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҒ®гҒ«гҖҒзӘҒ然гҖҒ
гҖҢгҒҫгӮӢгҒ§иҮӘеҲҶгҒ®дҪ“гҒҢиҮӘеҲҶгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҖҚ
гҒЁиЎЁзҸҫгҒҷгӮӢеҘіжҖ§гҒҜе°‘гҒӘгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
дҪ•гҒҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҒЁиЁҖгҒҲгҒ°гҖҒгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖҒеҘіжҖ§гғӣгғ«гғўгғігҒҢжёӣе°‘гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
1. еҘіжҖ§гғӣгғ«гғўгғігҒҢгғ”гғігғқгғізҺүгҒ®ж§ҳгҒ«еӢ•гҒҸ
жёӣе°‘гҒҷгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
жӣҙе№ҙжңҹгҒ«е…ҘгӮӢгҒЁгҖҒе…ЁгҒҰгҒ®еҘіжҖ§гғӣгғ«гғўгғігҒҢгғ”гғігғқгғізҺүгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҢҷеӢ•гӮ’гҒ—е§ӢгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮжҝҖгҒ—гҒҸеӨүеҢ–гҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒж•°е№ҙгҒӢгҒ‘гҒҰжёӣе°‘гҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
зү№гҒ«гҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒҢжҝҖжёӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§и»ҪеәҰгҒ®дҪ“еҶ…зӮҺз—ҮгҒ®жіўгҒҢиө·гҒ“гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒҢдҪ“дёӯгҒ«дёҚиӘҝгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
3. е…ЁгҒҰгҒ®иҮ“еҷЁгҒҢгӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒЁй–ўдҝӮгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ
е…ЁгҒҰгҒ®иҮ“еҷЁгҒ«гҒҜгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғіеҸ—е®№дҪ“гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒе…ЁгҒҰгҒ®иҮ“еҷЁгҒҢгӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒЁдҪ•зӯүгҒӢгҒ®й–ўдҝӮгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒ®еӨүеҢ–гҒҜгҖҒе…ЁгҒҰгҒ®иҮ“еҷЁгҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
жёӣе°‘гҒҷгӮӢгӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒЁеў—еҠ гҒҷгӮӢдҪ“еҶ…зӮҺз—ҮгҒҜжӮӘеҫӘз’°гӮ’дҪңгӮҠдёҚиӘҝгӮ’жӮӘеҢ–гҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
2020е№ҙгҒ®гҖҺзҘһзөҢзӮҺз—ҮгӮёгғЈгғјгғҠгғ«пјҲJournal of NeuroinflammationпјүгҖҸгҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгҒҹи«–ж–ҮгҒҜгҖҒ й–үзөҢгӮ’гҖҢзӮҺз—ҮгҒ®еј•гҒҚйҮ‘гҖҚгҒЁиЎЁзҸҫгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жӣҙе№ҙжңҹгҒ®еҫҢеҚҠгҖҒз”ҹзҗҶе‘ЁжңҹгҒҢ60ж—Ҙд»ҘдёҠгҒ«гҒӘгӮӢй ғгҖҒз—ҮзҠ¶гҒҢгғ”гғјгӮҜгҒ«йҒ”гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒ®жёӣе°‘гҒҢиө·гҒ“гҒҷеҪұйҹҝ

1. и„ігҒёгҒ®еҪұйҹҝ
жӣҙе№ҙжңҹгҒ®еҘіжҖ§гҒӢгӮүгҖҒгҖҢз§ҒгҒҜиӘҚзҹҘз—ҮгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹгҖҚгҒЁиЁҠгҒӢгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒЁгҒҰгӮӮеӨҡгҒ„гҒЁгҖҒгғҸгғјгӮ·гғҘеҢ»её«гҒҜиЁҖгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒҢжёӣе°‘гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒй ӯгҒ«гғўгғӨгҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒдҪ•гҒӢгӮ’иҖғгҒҲгҒҹгӮҠгҖҒйӣҶдёӯгҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢгғ–гғ¬гӮӨгғігғ»гғ•гӮ©гӮ°пјҲи„ігҒ®йң§пјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒҷгҖӮгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘзҸҫиұЎгҒҢиө·гҒ“гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®гӮөгӮӨгғігҒ«гҒҜж¬ЎгҒ®ж§ҳгҒӘгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
- зү©еҝҳгӮҢ
- йӣҶдёӯеҠӣгҒ®ж¬ еҰӮ
- жғ…е ұгӮ’зҗҶи§ЈгҒҷгӮӢеҠӣгҒ®дҪҺдёӢ
гҒӘгҒ©
гҒ§гӮӮгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒҢдёӯе№ҙжңҹгҒ«иө·гҒ“гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜзЁҖгҒ§гҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒ65жӯід»ҘдёӢгҒ§гӮўгғ«гғ„гғҸгӮӨгғһгғјз—…гӮ’зҷәз—ҮгҒҷгӮӢдәәгҒҜгҖҒдәәеҸЈгҒ®10%гӮӮгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ§гӮӮгӮӮгҒ—гҖҒеҚҳгҒӘгӮӢзү©еҝҳгӮҢгӮ„йӣҶдёӯеҠӣгҒ®ж¬ еҰӮгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘз—ҮзҠ¶гҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгӮ„гҖҒ家ж—ҸгӮ„гҒ”еҸӢдәәгҒӢгӮүжҢҮж‘ҳгҒ•гӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒз—…йҷўгӮ’еҸ—иЁәгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
- зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе ҙжүҖгҒ§иҝ·еӯҗгҒ«гҒӘгӮӢ
- ж—Ҙеёёзҡ„гҒӘд»•дәӢгҒ®гӮ„гӮҠж–№гӮ’еҝҳгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгӮёгғЈгӮұгғғгғҲгҒ®гғ•гӮЎгӮ№гғҠгғјгҒ®з· гӮҒж–№гӮ„гӮ¬гӮ№гӮігғігғӯгҒ®дҪҝгҒ„ж–№гҒӘгҒ©
- еӨұгҒҸгҒ—зү©гҒҢеў—гҒҲгҒҹгӮҠгҖҒеӨүгҒӘе ҙжүҖгҒ«гӮӮгҒ®гӮ’д»•иҲһгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢ
з§ҒгӮӮзү©еҝҳгӮҢгҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮд»ҠгҒҫгҒ§гҒ гҒЈгҒҹгӮүгҒӮгӮҠеҫ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒгӮ¶гғ«гҒӢгӮүгҒ“гҒјгӮҢиҗҪгҒЎгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гғңгғӯгғңгғӯеҝҳгӮҢгҒҫгҒҷпјҲ笑пјүгҖӮд»ҠгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚеӨ§дәӢгҒ«гҒҜиҮігҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҒҢпјҲгҒқгҒ®еүҚгҒ«жҖқгҒ„еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпјүгҖҒгғ’гғӨгҒЈгҒЁгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜпј‘еәҰгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“пјҲжӮ©пјү
2. ж¶ҲеҢ–еҷЁе®ҳгҒёгҒ®еҪұйҹҝ

жӣҙе№ҙжңҹгҒ®еҘіжҖ§гҒ®зҙ„еҚҠж•°гҒҢгҖҒиғёгӮ„гҒ‘гӮ„йҖҶжөҒжҖ§йЈҹйҒ“зӮҺгӮ’иө·гҒ“гҒҷгҒЁгҒ®иӘҝжҹ»е ұе‘ҠгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дҪ“еҶ…гҒ®зӮҺз—ҮгҒҜгҖҒгғӘгғјгӮӯгғјгӮ¬гғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢз—ҮзҠ¶гҒЁй–ўдҝӮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгғӘгғјгӮӯгғјгӮ¬гғғгғҲгҒҜгҖҒи…ёгҒ®еҶ…еЈҒгҒ®й–“гӮ’з—…еҺҹиҸҢгҒҢйҖҡгӮҠжҠңгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ§гҖҒгӮ¬гӮ№гӮ’зҷәз”ҹгҒ•гҒӣгҒҹгӮҠгҖҒзӮҺз—ҮжҖ§и…ёзӮҺгҒ®з—ҮзҠ¶гӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒ®жёӣе°‘гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиө·гҒ“гӮӢдҪ“еҶ…зӮҺз—ҮгҒҢж¶ҲеҢ–еҷЁе®ҳгҒ«зӮҺз—ҮгӮ’зҷәз”ҹгҒ•гҒӣгҒҹгӮҠгҖҒж—ўгҒ«гҒӮгӮӢзӮҺз—ҮгӮ’жӮӘеҢ–гҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
йҖҶжөҒжҖ§йЈҹйҒ“зӮҺгҒ®ж”№е–„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺйҖҶжөҒжҖ§йЈҹйҒ“зӮҺгҖҸгӮ’гҒ”еҸӮз…§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
3. зҡ®иҶҡпјҸгҒҠиӮҢгҒёгҒ®еҪұйҹҝ
жӣҙе№ҙжңҹгҒ«гҒҜгҖҒиӮҢд№ҫзҮҘгӮ„зҡ®иҶҡгҒҢи–„гҒҸгҒӘгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒзӣ®гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢеӨүеҢ–гҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮжӣҙе№ҙжңҹгҒ®еҘіжҖ§гҒ®зҙ„еҚҠж•°гҒҢгҖҒз—ҮзҠ¶гҒ®жӮӘеҢ–гӮ’иЁҙгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иӮҢиҚ’гӮҢгӮ„зҷәз–№гҖҒеҗ№гҒҚеҮәзү©гӮ„иөӨгӮүйЎ”гҒӘгҒ©гҒҢиө·гҒ“гҒЈгҒҹгӮҠгҖҒжӮӘеҢ–гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮд№ҫзҷ¬гӮӮеў—гҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠиӮҢгӮ’иӢҘгҖ…гҒ—гҒҸдҝқгҒӨгҒ«гҒҜгҖҺгӮөгғ—гғӘгғЎгғігғҲгҒӢгӮүгҒҜеҫ—гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҒҠиӮҢгӮ’иҖҒеҢ–гҒ•гҒӣгҒҡгҒ«иӢҘгҖ…гҒ—гҒҸдҝқгҒӨжҲҗеҲҶгҒЁжңҖеј·йЈҹе“ҒгҖҸгӮӮгҒ”еҸӮз…§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
4. й–ўзҜҖгҒёгҒ®еҪұйҹҝ
жӣҙе№ҙжңҹгҒ®еҘіжҖ§гҒ®еҚҠеҲҶд»ҘдёҠгҒҢгҖҒй–ўзҜҖз—ӣгӮ’зөҢйЁ“гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиӘҝжҹ»е ұе‘ҠгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўзҜҖгҒҢгҒ“гӮҸгҒ°гҒЈгҒҹгӮҠгҖҒз—ӣгҒҝгӮ’гҒЁгӮӮгҒӘгҒҶи…«гӮҢгҒҢиө·гҒ“гҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒ®жёӣе°‘гҒ«гӮҲгӮӢдҪ“еҶ…зӮҺз—ҮгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸеҪұйҹҝгҒ—гҖҒйӘЁй–ўзҜҖзӮҺгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒжӮӘеҢ–гҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўзҜҖгҒ®з—ӣгҒҝгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺгӮӨгғ–гғ—гғӯгғ•гӮ§гғігҒ«й јгӮүгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮз—ӣгҒҝгӮ’е’ҢгӮүгҒ’гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢйЈҹе“ҒгҖҸгӮ’гҒ”еҸӮз…§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒ30д»ЈпҪһ50д»ЈгҒ®еҘіжҖ§гҒ«еӨҡгҒ„й–ўзҜҖгғӘгӮҰгғһгғҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺй–ўзҜҖгғӘгӮҰгғһгғҒгҒҜгғҙгӮЈгғјгӮ¬гғігҒ§жІ»гӮӢпјҹгҖҸгӮ’гҒ”еҸӮз…§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
5. зӣ®гҒёгҒ®еҪұйҹҝ
жӣҙе№ҙжңҹгҒ®еҘіжҖ§гҒ®10дәәгҒ«6дәәд»ҘдёҠпјҲ60%д»ҘдёҠпјүгҒ«ж¬ЎгҒ®ж§ҳгҒӘзӣ®гҒ®з—ҮзҠ¶гҒҢиө·гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
- гғүгғ©гӮӨгӮўгӮӨ
- зӣ®гҒ®гҒӢгӮҶгҒҝ
- гӮҒгӮ„гҒ«
- зӣ®гҒ®зӮҺз—Ү
гҒӘгҒ©
2017е№ҙгҒ®гҖҺй–үзөҢпјҲMenopauseпјүгҖҸгӮёгғЈгғјгғҠгғ«иӘҢгҒ«гҒҜгҖҒжҖ§гғӣгғ«гғўгғігҒ®жёӣе°‘гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒж¶ҷж¶ІеұӨгҒ®иіӘгҒЁйҮҸгҒ«еӨүеҢ–гҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зӣ®гҒ®д№ҫзҮҘгҒЁж”№е–„жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺгғүгғ©гӮӨгӮўгӮӨгҒ®ж”№е–„гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨйЈҹе“ҒгҒЁж„ҸеӨ–гҒӘзҝ’ж…ЈгҖҸгӮ’гҒ”еҸӮз…§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮгҒҫгҒҹгҖҺзӣ®гҒ®еҒҘеә·гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гӮөгғ—гғӘгғЎгғігғҲгӮ’йЈІгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢдәәгҒҜжңҹеҫ…гҒҢиЈҸеҲҮгӮүгӮҢгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖҸгӮӮгҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
6. иҖігҒёгҒ®еҪұйҹҝ
дҪ“гҒ®е№іиЎЎж„ҹиҰҡгӮ’еҸёгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҶ…иҖігӮӮжҖ§гғӣгғ«гғўгғігҒӢгӮүеҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒгӮҒгҒҫгҒ„гӮ„з«ӢгҒЎгҒҸгӮүгҒҝгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еҖӢдәәзҡ„гҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҫ©еҸ”жҜҚгҒҢжӣҙе№ҙжңҹгҒ®жҷӮгҒ«е·ҰиҖігҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒд»ҠгҒ§гӮӮгҖҒиҒһгҒ“гҒҲгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮе№іиЎЎж„ҹиҰҡгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒиҒҙиҰҡгҒ«гӮӮеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
7. йЎҺпјҸеҸЈгҒёгҒ®еҪұйҹҝ
2022е№ҙгҒ®гҖҺй–үзөҢпјҲMenopauseпјүгҖҸгӮёгғЈгғјгғҠгғ«иӘҢгҒ«гҒҜгҖҒжӣҙе№ҙжңҹгҒ®еҘіжҖ§гҒҜгҖҒз”·жҖ§гҒ®2еҖҚгҒ®зўәзҺҮгҒ§йЎҺй–ўзҜҖз—ҮгҒ«гҒӘгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«гҖҒз”ҹзҗҶгӮөгӮӨгӮҜгғ«гҒҢ60ж—Ҙд»ҘдёҠгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹй ғгҒ«гҖҒйЎҺй–ўзҜҖз—ҮгӮ’зҷәз—ҮгҒҷгӮӢеҘіжҖ§гҒҢжңҖгӮӮеӨҡгҒ„гҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
8. еҝғиҮ“гҒёгҒ®еҪұйҹҝ
жӣҙе№ҙжңҹгҒ®еҘіжҖ§гҒ®зҙ„47%гҒҢеӢ•жӮёгӮ’зөҢйЁ“гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгғҸгғјгӮ·гғҘеҢ»её«гҒҜиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеӢ•жӮёгҒҜгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒ®жёӣе°‘гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеҝғиҮ“гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«з–ҫжӮЈгҒҢгҒӮгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒжӨңжҹ»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еӢ§гӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еӢ•жӮёгҒҢиө·гҒҚгҒҹж—ҘгҒЁжҷӮй–“еёҜгӮ’гҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ®жӣҙе№ҙжңҹгҒ®з—ҮзҠ¶гҒЁе…ұгҒ«иЁҳйҢІгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
9. гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒ®зҷәз—ҮгҒЁжӮӘеҢ–
гӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒ®жёӣе°‘гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒ40д»ЈгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹйҖ”з«ҜгҒ«иҠұзІүз—ҮгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒиҠұзІүз—ҮгҒ®з—ҮзҠ¶гҒҢжӮӘеҢ–гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒд»ҠгҒҫгҒ§дҪ•гҒЁгӮӮгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹйЈҹгҒ№зү©гҒ«гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢиө·гҒ“гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жҖ§гғӣгғ«гғўгғігҒ®жёӣе°‘гҒҢдҪ“еҶ…гҒ®гғ’гӮ№гӮҝгғҹгғігӮ’еў—еҠ гҒ•гҒӣгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮӢгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјеҸҚеҝңгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶиЁҖгҒҲгҒ°гҖҒз§ҒгҒҢгӮўгғҲгғ”гғјжҖ§гҒ®зҷҪеҶ…йҡңгҒ§еӨұжҳҺгӮ’гҒ—гҒҹгҒ®гӮӮ40д»ЈгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгҒ®й ғгҒҜгҖҒгҒқгҒ®д»–гҒ«гӮӮгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ®гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒҢзҷәз—ҮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒҰгҒЈгҒҚгӮҠгҒқгҒ®еҪ“жҷӮгҒ®йЈҹз”ҹжҙ»гҒЁгғ©гӮӨгғ•гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒЁгӮ№гғҲгғ¬гӮ№гҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ гҒЁгҒ°гҒӢгӮҠжҖқгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒ®жёӣе°‘гӮӮдёҖжһҡеҷӣгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ
жёӣе°‘гҒҷгӮӢгӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒЁеў—еҠ гҒҷгӮӢдҪ“еҶ…зӮҺз—ҮгҒЁд»ҳгҒҚеҗҲгҒҶгҒ«гҒҜ
гғҸгғјгӮ·гғҘеҢ»её«гҒҜгҖҒжӣҙе№ҙжңҹгҒҜе…Ёиә«з—ҮзҠ¶гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰгҖҒжӣҙе№ҙжңҹгҒ®еҘіжҖ§гҒ®иЁәж–ӯгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзү№е®ҡеҲҶйҮҺгҒ®еҢ»её«гҒ гҒ‘гҒ§еҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒз·ҸеҗҲзҡ„гҒ«дёҚиӘҝгҒ®й–ўйҖЈжҖ§гҒ«еҜҫеҮҰгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ гҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
1. еҘіжҖ§гғӣгғ«гғўгғіеүӨгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

еҘіжҖ§гғӣгғ«гғўгғігғҗгғ©гғігӮ№гҒ®дёҚиӘҝгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒPMSгӮ„з”ҹзҗҶз—ӣгӮ„жӣҙе№ҙжңҹгҒ®дёҚиӘҝгҒ§з—…йҷўгҒ«иЎҢгҒҸгҒЁгҖҒжјўж–№и–¬гҒӢеҘіжҖ§гғӣгғ«гғўгғіеүӨгҒ®гҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜдёЎж–№гҒҢеҮҰж–№гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҢжҷ®йҖҡгҒ§гҒҷгҖӮ
жңҖиҝ‘гҒ®еҘіжҖ§гғӣгғ«гғўгғіеүӨгҒ«гҒҜеүҜдҪңз”ЁгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒҜгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒз„ЎгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮи©ігҒ—гҒҸгҒҜгҖҒж–°гҒ—гҒҸе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҹз ”з©¶гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҹгҖҺеҘіжҖ§гғӣгғ«гғўгғіеүӨгҒ§гғ“гӮҝгғҹгғіB6ж¬ д№Ҹз—ҮгӮ„гҒҶгҒӨгҒ«гҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҖҸгӮ’гҒ”еҸӮз…§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒжјўж–№и–¬гҒ«гҒҜеүҜдҪңз”ЁгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгӮҲгҒҸиҒһгҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮӮиӘӨгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
жјўж–№гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮи–¬гҒҜи–¬гҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгӮӮз”ҹи–¬гӮ’иҮӘеҲҶгҒ§з…ҺгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҢ–еӯҰзҡ„гҒ«жҲҗеҲҶгӮ’еҶҚзҸҫгҒ—гҒҰйҖ гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢз—…йҷўгҒ§еҮҰж–№гҒ•гӮҢгӮӢжјўж–№и–¬гҒҜзү№гҒ«жіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ«гҖҒеҘіжҖ§гғӣгғ«гғўгғіеүӨгӮӮжјўж–№и–¬гӮӮгҖҒгҒ©гҒЎгӮүгӮӮеҘіжҖ§гғӣгғ«гғўгғігҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒҢд№ұгӮҢгӮӢж №жң¬зҡ„гҒӘеҺҹеӣ гӮ’жІ»гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮз—ҮзҠ¶гӮ’з·©е’ҢгҒҷгӮӢжүӢдјқгҒ„гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒйЈІгӮ“гҒ§гҒ„гӮҢгҒ°иӘҝеӯҗгҒҜгҒ„гҒ„гҒҢгҖҒйЈІгҒҫгҒӘгҒ„гҒЁдёҚиӘҝгҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзҠ¶ж…ӢгҒӢгӮүжҠңгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒӮгҒӘгҒҹгҒҢж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ®дёӯгҒ§гҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғӣгғ«гғўгғігҒҢиҗҪгҒЎзқҖгҒҸгҒ®гӮ’еҫ…гҒӨй–“гҖҒдҪ“гҒҢдёҠжүӢгҒ«еӨүеҢ–гҒ«йҒ©еҝңгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒгҒқгҒ—гҒҰеў—еҠ гҒҷгӮӢдҪ“еҶ…зӮҺз—ҮгӮ’жҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒйЈҹдәӢгҒЁгғ©гӮӨгғ•гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гӮ’еӨүеҢ–гҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жёӣе°‘гҒҷгӮӢгӮЁгӮ№гғҲгғӯгӮІгғігҒЁеў—еҠ гҒҷгӮӢдҪ“еҶ…зӮҺз—ҮгҒЁд»ҳгҒҚеҗҲгҒҶгҒ«гҒҜпјҲгҒӨгҒҘгҒҚпјүгҖҖпјһпјһ
гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒӢгӮүгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№

гғһгӮӨгғігғүгғ»гғңгғҮгӮЈгғ»гғЎгғҮгӮЈгӮ·гғіи¬ӣеә§гӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒйЈҹдәӢгӮ„гғ©гӮӨгғ•гӮ№гӮҝгӮӨгғ«гҒ®еҜҫеҝңгҒ®д»•ж–№гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒ家еәӯгҒ®еӨ–гҒ§еғҚгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢеҘіжҖ§гӮӮеӨҡгҒ„зҸҫд»ЈгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒиҒ·е ҙз·ЁгҒЁгҒ”家еәӯз·ЁгҒ«еҲҶгҒ‘гҒҰгҖҒгӮ№гғҲгғ¬гӮ№гӮ’жёӣгӮүгҒ—гҒҰеҝғгӮ’е®ҲгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸе…·дҪ“зҡ„гҒӘж–№жі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж•ҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒз”·жҖ§гҒ®жӣҙе№ҙжңҹгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгӮ«гғҗгғјгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӮгҒӘгҒҹгӮӮгӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§дёҖз·’гҒ«еӯҰгҒігҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹ
гӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢйЈҹгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҒ”иҮӘиә«гҒ®дё»жІ»еҢ»пјҲгӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјпјүгҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҝ…иҰҒгҒӘзҹҘиӯҳгҒЁгӮ№гӮӯгғ«гӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж–°еӯҰжңҹгҒҜгҖҒжҜҺе№ҙ3жңҲгҒЁ9жңҲгҒ§гҒҷгҖӮи¬ӣеә§гҒ§гҒҠдјҡгҒ„гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒгӮӮгҒ—гҒҠгҒІгҒЁгӮҠгҒ§еҸ–гӮҠзө„гӮҖгҒ“гҒЁгҒ«дёҚе®үгӮ„йӣЈгҒ—гҒ•гӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӘгӮүгҖҒгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒЁгҖҒдёҖеәҰгҖҒи©ұгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹ
з§ҒиҮӘиә«гҖҒзөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰгҒ«жІҝгҒЈгҒҹйЈҹдәӢгӮ’гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҖҒж—ҘеёёгҒ«еҪұйҹҝгҒҷгӮӢгҒ»гҒ©гҒ®з—ҮзҠ¶гӮ’иө·гҒ“гҒҷгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸйҒҺгҒ”гҒӣгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е…¬иӘҚгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒҜгҖҒйЈҹдәӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгӮ’еҸ–гӮҠе·»гҒҸж§ҳгҖ…гҒӘгҒ“гҒЁпјҲз’°еўғгҖҒд»•дәӢгҖҒ家ж—ҸгҖҒдәәй–“й–ўдҝӮгҒӘгҒ©пјүгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰгҖҒгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«еҸҚжҳ гҒ•гҒӣгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢгҖҒгҒӘгӮҠгҒҹгҒ„гҒӮгҒӘгҒҹгҒ«гҒӘгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгӮігғјгғҒгғігӮ°гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ—гғ©гӮӨгғҷгғјгғҲгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°гғ»гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
гҒҠж°—и»ҪгҒ«гҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
еҲқеӣһзӣёи«ҮгӮ’з„Ўж–ҷгҒ§гҒҠеҸ—гҒ‘гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§еҒҘеә·гҒЁе№ёгҒӣгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢ
гғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјгҒ®гҒ”зҷ»йҢІгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮү
зөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰпјҲгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜж „йӨҠеӯҰпјүеҶҠеӯҗгҒҢз„Ўж–ҷгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ
еҸӮиҖғж–ҮзҢ®
- вҖңBeyond hot flashesвҖқ, Maureen Salamon, Executive Editor, Harvard Women’s Health Watch, September 1, 2022
- вҖңThe peri-menopause in a woman’s life: a systemic inflammatory phase that enables later neurodegenerative diseaseвҖқ, Micheline McCarthy, Ami P Raval, J Neuroinflammation, 2020 Oct 23;17(1):317. doi: 10.1186/s12974-020-01998-9, PMID: 33097048, PMCID: PMC7585188
- вҖңDry Eye Syndrome in Menopause and Perimenopausal Age GroupвҖқ, Travis Peck, Leslie Olsakovsky, Shruti Aggarwal, J Midlife Health, 2017 Apr-Jun;8(2):51-54. doi: 10.4103/jmh.JMH_41_17, PMID: 28706404, PMCID: PMC5496280
- вҖңDoes temporomandibular disorder correlate with menopausal symptoms?вҖқ, Alessandra Pucci Mantelli Galhardo, Marcia Katsuyoshi Mukai, Maria CГўndida P Baracat, Angela Maggio da Fonseca, Cristiane Lima Roa, Isabel Cristina EspГіsito Sorpreso, Edmund Chada Baracat, Jose Maria Soares Junior, Menopause, 2022 Jun 1;29(6):728-733. doi: 10.1097/GME.0000000000001962, PMID: 35544600
- вҖңMenopause Hot Flashes and Molecular Mechanisms Modulated by Food-Derived Nutrients.вҖқ, Forma E, UrbaЕ„ska K, BryЕӣ M., Nutrients. 2024 Feb 26;16(5):655. doi: 10.3390/nu16050655. PMID: 38474783; PMCID: PMC10935406
гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲ – гғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°