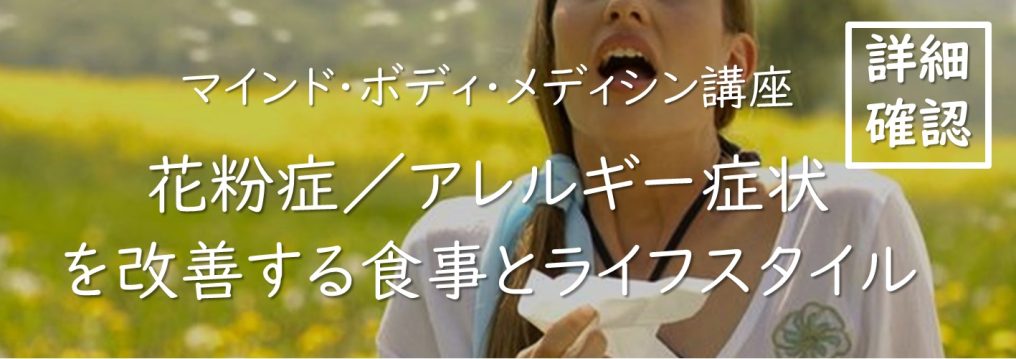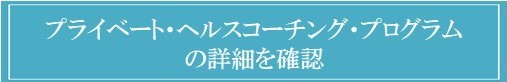гғҗгӮӨгӮӘеҖӢжҖ§гҒ§йЈҹгҒ№гҒҰгҖҒеҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҺгҖҒеҒҘеә·гҒЁе№ёгҒӣгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒӘйЈҹдәӢжі•гӮ’гӮігғјгғҒгғігӮ°гҒҷгӮӢгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲд»ЈиЎЁгҖҖе…¬иӘҚзөұеҗҲйЈҹйӨҠгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒпјҲCINHCпјүгҖҒе…¬иӘҚеӣҪйҡӣгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒпјҲCIHCпјүгҒ®жЈ®гҒЎгҒӣгҒ§гҒҷгҖӮ
еҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгҒӘйЈҹдәӢжі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒ
гғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјзҷ»йҢІиҖ…йҷҗе®ҡгҒ®гӮӯгғЈгғігғҡгғјгғіжғ…е ұзӯүгӮӮй…ҚдҝЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ”зҷ»йҢІгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮү
гӮӮгӮҢгҒӘгҒҸзөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰпјҲгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜж „йӨҠеӯҰпјүеҶҠеӯҗгҒҢз„Ўж–ҷгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ
зӣ®ж¬Ў
- 1 еӯЈзҜҖжҖ§гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгӮ’и§Јж¶ҲгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
- 2 гӮұгғ«гӮ»гғҒгғі
- 3 гғ“гӮҝгғҹгғіC
- 4 гғ“гӮҝгғҹгғіE
- 5 гғҹгғҚгғ©гғ«
- 6 гӮӘгғЎгӮ¬пј“гҒҜеҠ№жһңгҒӘгҒ—
- 7 гӮўгғјгғҰгғ«гғҙгӮ§гғјгғҖгҒ®гғҸгғјгғ–и–¬
- 8 жқұжҙӢеҢ»еӯҰгҒ®гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғј
- 9 е°Ҹйқ’з«ңж№Ҝ
- 10 жқұжҙӢеҢ»еӯҰгҒ«гӮҲгӮӢи–¬иҶі
- 11 гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒӢгӮүгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№
еӯЈзҜҖжҖ§гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгӮ’и§Јж¶ҲгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹ
еӯЈзҜҖжҖ§гҒ®гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҖҒиҠұзІүз—ҮгҖӮ
гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒиҠұзІүз—ҮгҒ«йҷҗгӮүгҒҡгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјжҖ§гҒ®йј»зӮҺгӮ„зӣ®гҒ®гҒӢгӮҶгҒҝгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁиҫӣгҒ„гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ
з§ҒгҒҜй•·гҒ„й–“гҖҒж§ҳгҖ…гҒӘгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒ«жӮ©гҒҫгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒ2013е№ҙгҒӢгӮүпј‘е№ҙй–“гҖҒIINпјҲзұіеӣҪгғӢгғҘгғјгғЁгғјгӮҜгҒ«гҒӮгӮӢдё–з•ҢжңҖеӨ§гҒ®гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒйӨҠжҲҗеӯҰж ЎпјүгҒ§еӯҰгӮ“гҒ зөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰгҒ®гӮўгғ—гғӯгғјгғҒгӮ’е®ҹи·өгҒ—гҖҒе…¬иӘҚгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹ2014е№ҙ2жңҲгҖҒз§ҒгҒҜгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢйЈҹдәӢгӮ’еӨүгҒҲгҒҰгҒ„гҒҸгҒҶгҒЎгҒ«гҖҒ次第гҒ«гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒҢеҮәгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
2014е№ҙ2жңҲ
иҠұзІүз—ҮгҒҜгҖҒгҒҫгҒ гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ
гҒ§гӮӮгҖҒи–¬гӮ’йЈІгҒҫгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮйҒҺгҒ”гҒӣгӮӢгҒҸгӮүгҒ„гҒҫгҒ§гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖҚ
гҒҫгҒҹгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гӮӮжӣёгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢз§ҒгҒ®гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒҢж”№е–„гҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒи…ёеҶ…гҒ®з’°еўғгӮ’гғӘгӮ»гғғгғҲгҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж №жң¬зҡ„гҒӘгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒ®и§Јж¶ҲгҒ«гҒҜгҖҒ
и…ёгҒЁгҒ®иүҜгҒ„й–ўдҝӮгӮ’зҜүгҒҚгҒӘгҒҠгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒ
й•·жңҹгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒЁгҒ—гҒҰж°—й•·гҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮгҖҚ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гғ–гғӯгӮ°гҒ®еҶ…е®№гӮ’еүҚеӣһжӣҙж–°гҒ—гҒҹ2020е№ҙгҒ«гҒҜгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢ2020е№ҙ2жңҲзҸҫеңЁгҒ®з§ҒгҒ«гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒҜдёҖеҲҮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“пјҲгӮӨгӮЁгғјгӮЈпјҒпјүгҖҚ
гҒ•гҒҰгҖҒи…ёеҶ…з’°еўғгӮ’ж•ҙгҒҲгӮӢд»ҘеӨ–гҒ«з§ҒгҒҢгҒ„гҒЈгҒҹгҒ„дҪ•гӮ’гҒ—гҒҹгҒ®гҒӢпјҹгҒҜгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒ®гғһгӮӨгғігғүгғ»гғңгғҮгӮЈгғ»гғЎгғҮгӮЈгӮ·гғіи¬ӣеә§гӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ®дёӯгҒ§и©ігҒ—гҒҸгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҒиҠұзІүз—ҮгҒӘгҒ©гҒ®еӯЈзҜҖжҖ§гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгӮ’жІ»гҒҷгҒЁгҒ„гҒҶиҰізӮ№гҒӢгӮүгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸпјҲгҒқгӮҢгҒҜи¬ӣеә§гҒ§гҖҒ笑пјүгҖҒ科еӯҰзҡ„гҒӘз ”з©¶гҒ§гҖҒгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гӮ’з·©е’ҢпјҸж”№е–„гҒҷгӮӢгҒЁе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢйЈҹе“ҒгӮ„гғҸгғјгғ–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒзөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰгҒҜгғҹгӮҜгғӯж „йӨҠзҙ гҒ§ж „йӨҠгӮ’ж‘ӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еӢ§гӮҒгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮд»ҠеӣһгҒҜеӯЈзҜҖжҖ§гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒ®ж”№е–„гҒ«еҠ№гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢйЈҹе“ҒжҲҗеҲҶгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгӮөгғ—гғӘгғЎгғігғҲгҒӢгӮүгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгғӣгғјгғ«гғ•гғјгғүгӮ’йЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹжҲҗеҲҶгӮ’иұҠеҜҢгҒ«еҗ«гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢйЈҹе“ҒгӮӮдҪөгҒӣгҒҰгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒиЈҸд»ҳгҒ‘гҒЁгҒӘгӮӢз ”з©¶и«–ж–ҮгҒҜгҖҒжңҖеҫҢгҒ«еҸӮиҖғж–ҮзҢ®гҒЁгҒ—гҒҰдёҖиҰ§гҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮұгғ«гӮ»гғҒгғі
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®йЈҹе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒгӮұгғ«гӮ»гғҒгғігҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгғқгғӘгғ•гӮ§гғҺгғјгғ«гҒҢиұҠеҜҢгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮұгғ«гӮ»гғҒгғігҒҜгҖҒеӨ©з„¶гҒ®жҠ—гғ’гӮ№гӮҝгғҹгғіеүӨгҒ§гҒҷгҖӮ

гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјеҸҚеҝңгҒҜгҖҒгғ’гӮ№гӮҝгғҹгғігҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢзӮҺз—ҮжҖ§зү©иіӘгҒҢдҪ“еҶ…гҒ§ж”ҫеҮәгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иө·гҒ“гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгӮұгғ«гӮ»гғҒгғігҒҢгҖҒгҒқгҒ®гғ’гӮ№гӮҝгғҹгғігӮ’ж”ҫеҮәгҒҷгӮӢгғһгӮ№гғҲзҙ°иғһгӮ’йҺ®йқҷеҢ–гҒ•гҒӣгҖҒгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гӮ’и»ҪгҒҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®з ”究гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгӮұгғ«гӮ»гғҒгғігҒҢгҖҒжҠ—гғ’гӮ№гӮҝгғҹгғіеүӨгҒ®гӮҜгғӯгғўгғӘгғігҒЁеҗҢзЁӢеәҰгҒ«гғ’гӮ№гӮҝгғҹгғіж”ҫеҮәгӮ’жҠ‘еҲ¶гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгӮҜгғӯгғўгғӘгғігҒҜгҖҒгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒҢиө·гҒҚгҒҹеҫҢгҒ§гҒ®гҒҝгғ’гӮ№гӮҝгғҹгғігӮ’жҠ‘еҲ¶гҒ§гҒҚгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒгӮұгғ«гӮ»гғҒгғігҒҜгҖҒгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒҢиө·гҒҚгӮӢеүҚгҒ«дәҲйҳІи–¬гҒЁгҒ—гҒҰеғҚгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгӮұгғ«гӮ»гғҒгғігҒҜгҖҒгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒҢгҒ§гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гӮӮгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒгӮұгғ«гӮ»гғҒгғігҒҜгҖҒдёҖйғЁгҒ®дәәгҒ«й ӯз—ӣгӮ’еј•гҒҚиө·гҒ“гҒҷеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢжҲҗеҲҶгҒ§гҒҷгҖӮеӨҡгҒ‘гӮҢгҒ°еӨҡгҒ„гҒ»гҒ©иүҜгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгӮүгҖҒгӮөгғ—гғӘгғЎгғігғҲгҒӢгӮүгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒйЈҹе“ҒгҒӢгӮүж‘ӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒдёҠгҒ®з”»еғҸгӮ’дҪңжҲҗгҒҷгӮӢгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҖҒеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒ®йЈҹе“ҒжҲҗеҲҶиЎЁгҒ«гӮұгғ«гӮ»гғҒгғігҒ®зҷ»йҢІгҒҢгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒеӣҪз«Ӣз ”з©¶й–Ӣзҷәжі•дәә иҫІжҘӯгғ»йЈҹе“Ғз”ЈжҘӯжҠҖиЎ“з·ҸеҗҲз ”з©¶ж©ҹж§ӢгҒҢ2015е№ҙгҒ«зҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҖҒж—Ҙжң¬дәәгҒҢж—Ҙеёёзҡ„гҒ«еҸЈгҒ«гҒҷгӮӢйЈҹе“ҒгҒ®дёӯгҒ§гӮұгғ«гӮ»гғҒгғігӮ’еӨҡгҒҸеҗ«гӮҖеӨҸгҒЁеҶ¬гҒ®йЈҹе“ҒгғӘгӮ№гғҲгҒЁгҖҒжө·еӨ–гҒ®з ”究иҖ…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиӘҝжҹ»гҒ•гӮҢгҒҹиӨҮж•°гҒ®з ”究論ж–ҮгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮұгғ«гӮ»гғҒгғігҒ®жҠҪеҮәгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҹж–№жі•гҒҢз ”з©¶гҒ”гҒЁгҒ«з•°гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒеҚҳдҪҚгҒҜжҸғгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒж•°еҖӨпјҲгӮұгғ«гӮ»гғҒгғійҮҸпјүгҒ«гҒҜгҖҒгҒӮгӮӢзЁӢеәҰгҒ®иӘӨе·®гӮ„е№…гҒҢгҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒ”жүҝзҹҘгҒҠгҒҚгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮгҒӘгҒҠгҖҒж•°еҖӨгҒҜе…ЁгҒҰгҖҢз”ҹгҖҚгҒ®йЈҹжқҗгҒӢгӮүгҒ®жҠҪеҮәйҮҸгҒ§гҒҷгҖӮ
еӣҪз”ЈгҒ®йЈҹе“ҒгҒ®гӮұгғ«гӮ»гғҒгғійҮҸ
иҫІжҘӯгғ»йЈҹе“Ғз”ЈжҘӯжҠҖиЎ“з·ҸеҗҲз ”з©¶ж©ҹж§ӢгҒҢиӘҝгҒ№гҒҹеӣҪз”ЈгҒ®йЈҹе“ҒгҒ гҒ‘гҒ«йҷҗе®ҡгҒ—гҒҰдёҖиҰ§гҒ«гҒ—гҒҹгҒ®гҒҢдёӢгҒ®иЎЁгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ–гҒЈгҒҸгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹз§ҒгҒ®еҚ°иұЎгҒ§гҒҜгҖҒеӨҸгҒ«еҸҺз©«гҒ•гӮҢгӮӢйЈҹе“ҒгҒ«гӮұгғ«гӮ»гғҒгғігҒҢеӨҡгҒҸеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гғ–гғӯгғғгӮігғӘгғј
гғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒ®ж—¬гҒҜеҶ¬гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгғ“гӮҝгғҹгғігӮ„гғҹгғҚгғ©гғ«гҒҜеҶ¬гҒ®гғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒ«еӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮұгғ«гӮ»гғҒгғігҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒеӨҸгҒ«гғҸгӮҰгӮ№ж Ҫеҹ№гҒ•гӮҢгҒҹгғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒ®ж–№гҒҢеҶ¬гҒ®пј“еҖҚгӮӮеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒЁгҒҰгӮӮй©ҡгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
зҺүгҒӯгҒҺ
еӨҸгҒ«еҸҺз©«гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’еҶ¬гҒҫгҒ§дҝқеӯҳгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгҖҒгӮұгғ«гӮ»гғҒгғійҮҸгҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮҠгӮ“гҒ”
гӮҠгӮ“гҒ”гҒҜгҖҒзҡ®гҒ«еӨҡгҒҸгҒ®гӮұгғ«гӮ»гғҒгғігҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒзҡ®гҒ”гҒЁйЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгӮҠгӮ“гҒ”гҒ®и©ігҒ—гҒ„ж©ҹиғҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺгӮҠгӮ“гҒ”гҖҸгӮ’гҒ”еҸӮз…§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒгӮұгғ«гӮ»гғҒгғігӮ’еӨҡгҒҸеҗ«гӮҖйЈҹе“ҒгҒЁеҗ«гҒҫгҒӘгҒ„йЈҹе“ҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгӮӮгҖҺзӣ®гҒ®гҒӢгӮҶгҒҝгҖҸгҒ«и©ігҒ—гҒҸжҺІијүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгҒЎгӮүгӮ’гҒ”зўәиӘҚгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гғ“гӮҝгғҹгғіC
дҪ“еҶ…гҒ§гғ“гӮҝгғҹгғіCгҒҢдёҚи¶ігҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјзҷәз—ҮгҒ®зўәзҺҮгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғ“гӮҝгғҹгғіCгҒҜгҖҒгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гӮ’зҹӯжңҹеҢ–гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶеғҚгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ


1ж—ҘгҒ«500mgд»ҘдёҠгҒ®гғ“гӮҝгғҹгғіпјЈгҒҢгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒ®ж”№е–„гҒ«иүҜгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶе ұе‘ҠгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғ“гӮҝгғҹгғіCгҒ®и©ігҒ—гҒ„ж©ҹиғҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺгғ“гӮҝгғҹгғіCгҖҸгӮ’гҒ”еҸӮз…§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гғ–гғӯгғғгӮігғӘгғј
гғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒҜгҖҒжҠ—гғ’гӮ№гӮҝгғҹгғідҪңз”ЁгӮ’гӮӮгҒӨпј’зЁ®йЎһгҒ®жҲҗеҲҶгҖҒгӮұгғ«гӮ»гғҒгғігҒЁгғ“гӮҝгғҹгғіCгҒҢиұҠеҜҢгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒгҒЁгҒҰгӮӮгҒҠеӢ§гӮҒгҒ§гҒҷгҖӮ
иӢәгҒҜиҰҒжіЁж„Ҹ
иӢәгҒ«гӮӮгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ®гғ“гӮҝгғҹгғіCгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиӢәгҒҜгғ’гӮ№гӮҝгғҹгғігҒ®ж”ҫеҮәгӮ’дҝғгҒҷгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒ®з·©е’ҢгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҒҠеӢ§гӮҒгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гғ“гӮҝгғҹгғіE
гғ“гӮҝгғҹгғіEгҒҜгҖҒгғһгӮ№гғҲзҙ°иғһгҒ«гӮҲгӮӢгғ’гӮ№гӮҝгғҹгғігҒ®ж”ҫеҮәгӮ’йҳ»е®ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒзҙ°иғһгҒёгҒ®гӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ пјҲCa2+пјүгҒ®еҸ–гӮҠиҫјгҒҝгӮ’еў—еҠ гҒ•гҒӣгҒҰгҖҒиЎҖз®ЎеЈҒгҒ®й…ёеҢ–гӮ’йҳІгҒҗдҪңз”ЁгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮи©ігҒ—гҒ„гғ“гӮҝгғҹгғіEгҒ®ж©ҹиғҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺгғ“гӮҝгғҹгғіEгҖҸгӮ’гҒ”зўәиӘҚгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гғ“гӮҝгғҹгғіEгҒҜгҖҒиұҶгӮ„гғҠгғғгғ„гҖҒгӮ·гғјгӮәпјҲзЁ®пјүгҒ®жІ№гҒ«еӨҡгҒҸеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгғҠгғғгғ„гӮ„гӮ·гғјгӮәгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫйЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гӮӮеҠ№жһңгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘгғҠгғғгғ„гҒ®ж „йӨҠдҫЎгӮ„еҖӢжҖ§гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺгғҠгғғгғ„гҖҸгӮ’гӮ·гғјгӮәгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺгӮ·гғјгӮәгҖҸгӮ’гҒ”еҸӮз…§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гғ•гғ«гғјгғ„
гҒҫгҒҹгҖҒгғ•гғ«гғјгғ„гҒ«гӮӮгғ“гӮҝгғҹгғіEгӮ’еӨҡгҒҸеҗ«гӮҖгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гғ“гӮҝгғҹгғіCгҒЁEгҒ®дёЎж–№гӮ’еҗ«гӮҖгғ•гғ«гғјгғ„
гғ“гӮҝгғҹгғіCгҒЁEгӮ’дёЎж–№гҒЁгӮӮиұҠеҜҢгҒ«еҗ«гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖҒгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒ®ж”№е–„гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰйқһеёёгҒ«еҠ№зҺҮгҒ®иүҜгҒ„гғ•гғ«гғјгғ„гҒ§гҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгӮӮгғҷгғӘгғјйЎһгҒ«гҒҜгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гӮұгғ«гӮ»гғҒгғігӮӮиұҠеҜҢгҒ§гҒҷгҖӮ

гғҹгғҚгғ©гғ«
ж—Ҙжң¬дәәгҒ®з”·жҖ§275еҗҚгҖҒеҘіжҖ§977еҗҚгӮ’еҜҫиұЎгҒ«гҖҒиҠұзІүз—ҮгҒ®дәәгҒЁгҒқгҒҶгҒ§гҒӘгҒ„дәәйҒ”гҒ®й«ӘгҒ®жҜӣгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгғҹгғҚгғ©гғ«гӮ’жҜ”ијғгҒ—гҒҹз ”з©¶гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иҠұзІүз—ҮгҒ§гҒӘгҒ„дәәгҒЁжҜ”ијғгҒ—гҒҰгҖҒж¬ЎгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- иҠұзІүз—ҮгҒ®з”·жҖ§гҒҜйү„еҲҶгҒҢжңүж„ҸгҒ«е°‘гҒӘгҒ„
- иҠұзІүз—ҮгҒ®еҘіжҖ§гҒ§гҒҜгӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ гҒЁгӮҜгғӯгғ гҒҢжңүж„ҸгҒ«е°‘гҒӘгҒҸгҖҒгӮ»гғ¬гғігҒҢеӨҡгҒ„
гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®гғҹгғҚгғ©гғ«гӮ’иұҠеҜҢгҒ«еҗ«гӮҖйЈҹе“ҒгҒ®дёҖиҰ§иЎЁгӮ’дёӢгҒ«жҺІијүгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ



гҒ“гҒҶгҒ—гҒҰгҒҝгӮӢгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®пј“гҒӨгҒ®гғҹгғҚгғ©гғ«гӮ’е…ұйҖҡгҒ—гҒҰиұҠеҜҢгҒ«жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢйЈҹе“ҒгҒҜгҖҒгҒІгҒҳгҒҚгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ
з”·жҖ§гӮӮеҘіжҖ§гӮӮгҖҒеӯЈзҜҖжҖ§гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒҢеҮәгӮӢеӯЈзҜҖгҒ®ж•°гҒӢжңҲеүҚгҒӢгӮүгҖҒгҒІгҒҳгҒҚгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«йЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒз—ҮзҠ¶гҒ®дәҲйҳІгӮ„ж”№е–„гҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҖҒгҒІгҒҳгҒҚгҒ«йҷҗгӮүгҒҡгҖҒиҠұзІүз—ҮгҒ®з”·жҖ§гҒҜйү„еҲҶгҒ®еӨҡгҒ„йЈҹе“ҒгӮ’гҖҒиҠұзІүз—ҮгҒ®еҘіжҖ§гҒҜгӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ гҒЁгӮҜгғӯгғ гҒҢеӨҡгҒ„йЈҹе“ҒгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«йЈҹгҒ№гӮӢгҒЁдәҲйҳІгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜз—ҮзҠ¶гҒ®з·©е’ҢгҒҢжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒҸгӮҢгҒҗгӮҢгӮӮгӮөгғ—гғӘгғЎгғігғҲгҒ§ж‘ӮгӮҚгҒҶгҒӘгӮ“гҒҰиҖғгҒҲгҒӘгҒ„гҒ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҒӯгҖӮпј“гҒӨгҒ®гғҹгғҚгғ©гғ«гҒ®и©ігҒ—гҒ„ж©ҹиғҪгҒЁгӮөгғ—гғӘгғЎгғігғҲгҒ§ж‘ӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®еҚұйҷәжҖ§гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҺйү„еҲҶгҖҸгҖҺгӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ гҖҸгҖҺгӮҜгғӯгғ гҖҸгӮ’гҒ”еҸӮз…§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гӮӘгғЎгӮ¬пј“гҒҜеҠ№жһңгҒӘгҒ—
гӮӘгғЎгӮ¬пј“дёҚйЈҪе’Ңи„ӮиӮӘй…ёгҒҢеӯЈзҜҖжҖ§гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒӘгҒ©гҒ®з—ҮзҠ¶гҒ®з·©е’ҢгҒ«иүҜгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’е ұе‘ҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢз ”з©¶и«–ж–ҮгӮ’Pub Med гҒ§иҰӢгҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
Pub Med гҒ§иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҹи«–ж–ҮгҒ®е…ЁгҒҰгҒҢгҖҒгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒЁгӮӘгғЎгӮ¬пј“гҒЁгҒ®й–“гҒ«гҒҜгҖҒдҪ•гҒ®й–ўдҝӮжҖ§гӮӮзҷәиҰӢгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁе ұе‘ҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮўгғјгғҰгғ«гғҙгӮ§гғјгғҖгҒ®гғҸгғјгғ–и–¬
гӮўгғјгғҰгғ«гғҙгӮ§гғјгғҖпјҲгӮӨгғігғүдјқзөұеҢ»зҷӮпјүгҒ§еӯЈзҜҖжҖ§гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒ®ж”№е–„гҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгғҸгғјгғ–гҒӘгҒ©гҒ®еҠ№жһңгӮ’дәҢйҮҚзӣІжӨңгғ©гғігғҖгғ еҢ–иҮЁеәҠи©ҰйЁ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиЁјжҳҺгҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

иҘҝжҙӢгҒөгҒҚпјҲгғҗгӮҝгғјгғҗгғјпјү
иҘҝжҙӢгҒөгҒҚпјҲгғҗгӮҝгғјгғҗгғјпјүгҒҢеӯЈзҜҖжҖ§гҒ®гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒ®ж”№е–„гҒ«жңҖгӮӮеҠ№жһңгҒҢй«ҳгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒгғҗгӮҝгғјгғҗгғјгҒ«гҒҜгҖҒиӮқжҜ’жҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰ2012е№ҙгҒ«иӢұеӣҪеҢ»и–¬е“ҒеәҒгҒҢиҮӘдё»еӣһеҸҺзӯүгҒ®жҺӘзҪ®гӮ’и¬ӣгҒҳгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒеҢ»и–¬йЈҹе“ҒеұҖйЈҹе“Ғе®үе…ЁйғЁгӮӮгҖҒж‘ӮеҸ–гӮ’жҺ§гҒҲгӮӢгӮҲгҒҶжіЁж„Ҹе–ҡиө·гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒе®үе…ЁжҖ§гҒҢзўәиӘҚгҒ•гӮҢгӮӢгҒҫгҒ§йЈҹгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжҺ§гҒҲгҒҹгҒ»гҒҶгҒҢе®үеҝғгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮўгғ¬гғ« 7
гӮўгғ¬гғ«пј—гҒҜгҖҒгӮўгғјгғҰгғ«гғҙгӮ§гғјгғҖпјҲгӮӨгғігғүдјқзөұеҢ»зҷӮпјүгҒ§гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒ®з·©е’ҢгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢпј—гҒӨгҒ®гғҸгғјгғ–гҒ®ж··еҗҲеүӨгҒ§гҒҷгҖӮ
гғҲгғӘгғ•гӮЎгғ©гғ»гғ»гғ»пј—гҒӨгҒ®гғҸгғјгғ–гҒ®гҒҶгҒЎпј“гҒӨгҒҜгғҲгғӘгғ•гӮЎгғ©гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгӮўгғјгғҰгғ«гғҙгӮ§гғјгғҖгҒ®еҲҘгҒ®гғҸгғјгғ–ж··еҗҲи–¬гҒ§гҒҷгҖӮгғҲгғӘгғ•гӮЎгғ©гҒ®и©ігҒ—гҒ„ж©ҹиғҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺгғҲгғӘгғ•гӮЎгғ©гҖҸгӮ’гҒ”зўәиӘҚгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гғ’гғҸгғ„гғ»гғ»гғ»ж—Ҙжң¬гҒ§гӮӮйҰҷиҫӣж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰиіје…ҘгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ°гғүгӮҘгғғгғҒ
гҒ“гӮҢгӮӮгӮўгғјгғҰгғ«гғҙгӮ§гғјгғҖгҒ®гғҸгғјгғ–гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҲгҒ”гҒҫгҖҒиғЎжӨ’
гҒҲгҒ”гҒҫгҖҒиғЎжӨ’гҖҒз”ҹе§ңгҒҜгҖҒжҜ”ијғзҡ„гҒ©гҒ“гҒ§гӮӮиіје…ҘгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„йЈҹе“ҒгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ
з”ҹе§ң
з”ҹе§ңгҒҜгҖҒгғ’гӮ№гӮҝгғҹгғігӮ’йҳ»е®ігҒ—гҒҰгҖҒгӮөгӮӨгғҲгӮ«гӮӨгғіпјҲзӮҺз—ҮжҖ§зү©иіӘпјүгҒ®йҮҸгӮ’йҒ©еҲҮгҒ«дҝқгҒЎгҖҒе…Қз–«ж©ҹиғҪгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰиүҜгҒ„еғҚгҒҚгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
з”ҹе§ңгҒ®жҠҪеҮәж¶І500mgгӮ’ж‘ӮеҸ–гҒҷгӮӢгӮ°гғ«гғјгғ—гҒЁгғӯгғ©гӮҝгӮёгғі10mgгӮ’ж‘ӮеҸ–гҒҷгӮӢгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ«еҲҶгҒ‘гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢ6йҖұй–“ж‘ӮеҸ–гҒ—гҒҹеҫҢгҒ®з—ҮзҠ¶гҒ®ж”№е–„еәҰгӮ’жҜ”ијғгҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒж”№е–„еәҰеҗҲгҒ„гҒҢеҗҢзЁӢеәҰгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒз”ҹе§ңгҒҢгӮҜгғ©гғӘгғҒгғіпјҲжҠ—гғ’гӮ№гӮҝгғҹгғіеүӨгҖҒдё»жҲҗеҲҶгғӯгғ©гӮҝгӮёгғіпјүгҒЁеҗҢзЁӢеәҰгҒ«гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјжҖ§йј»зӮҺгҒ®з—ҮзҠ¶гӮ’ж”№е–„гҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
жӣҙгҒ«гҖҒз”ҹе§ңгҒ®жҠҪеҮәж¶ІгӮ’ж‘ӮеҸ–гҒ—гҒҹгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ§гҒҜгҖҒжҠ—гғ’гӮ№гӮҝгғҹгғіеүӨзү№жңүгҒ®зң ж°—гӮ„еҖҰжҖ ж„ҹгӮ„дҫҝз§ҳгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеүҜдҪңз”ЁгҒҢиө·гҒ“гӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒз”ҹе§ңгҒҜгҖҒгӮҜгғ©гғӘгғҒгғігӮҲгӮҠгӮӮе„ӘгӮҢгҒҹжҠ—гғ’гӮ№гӮҝгғҹгғійЈҹе“ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁзөҗи«–гҒҘгҒ‘гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
и©ігҒ—гҒ„з”ҹе§ңгҒ®ж©ҹиғҪгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺз”ҹе§ңгҖҸгӮ’гҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҒӯгҖӮ
жқұжҙӢеҢ»еӯҰгҒ®гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғј

дёҠиЁҳгҒ—гҒҹгӮўгғјгғҰгғ«гғҙгӮ§гғјгғҖи–¬гҒ®з ”究гҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҖҒдёӯеҢ»еӯҰпјҲж—Ҙжң¬гҒ®жјўж–№гҒ®жәҗпјүгҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢз”ҹи–¬гҒ«гӮӮеҠ№жһңгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒжқұжҙӢеҢ»еӯҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеӯЈзҜҖжҖ§гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
е…Қз–«ж©ҹиғҪгҒҜгҖҢжӯЈж°—гҖҚ
жқұжҙӢеҢ»еӯҰгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдҪ“гҒ®е…Қз–«ж©ҹиғҪгҒҜгҖҢжӯЈж°—гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгӮўгғ¬гғ«гӮІгғігӮ„гӮҰгӮЈгғ«гӮ№гӮ„иҸҢпјҲгғҗгӮҜгғҶгғӘгӮўпјүгҒӘгҒ©гҖҒеӨ–йғЁгҒӢгӮүдҫөе…ҘгҒ—гҒҰеҒҘеә·гӮ’жҗҚгҒӘгҒҶгӮӮгҒ®гӮ’гҖҢеӨ–йӮӘпјҲгҒҢгҒ„гҒҳгӮғпјүгҖҚгҒЁе‘јгҒігҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢжӯЈж°—гҖҚгҒҜгҖҢеӨ–йӮӘгҖҚгҒЁжҲҰгҒ„гҒӨгҒҘгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢжӯЈж°—гҖҚгҒҢеӢқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶ж…ӢгҒҢгҖҢеҒҘеә·гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгҖҢеӨ–йӮӘгҖҚгҒҢеӢқгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶ж…ӢгҒҢгҖҢз—…ж°—гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢжӯЈж°—гҖҚгҒҢејұгҒ„жҷӮгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒеҒҘеә·гҒҢжҗҚгҒӘгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжҷӮгҒ«гҖҒгҖҢеӨ–йӮӘгҖҚгҒЁгҒӘгӮӢгӮўгғ¬гғ«гӮІгғігҒЁжҺҘгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒҢиө·гҒҚгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
е°Ҹйқ’з«ңж№Ҝ
е°Ҹйқ’з«ңж№ҜпјҲгҒ—гӮҮгҒҶгҒӣгҒ„гӮҠгӮ…гҒҶгҒЁгҒҶпјүгҒҜгҖҒеӯЈзҜҖжҖ§гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶пјҲзү№гҒ«гҖҒйј»зӮҺпјүгҒ®з·©е’ҢгҒ«еҮҰж–№гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҖҒгҒ©гҒ®дҪ“иіӘгҒ«гӮӮиүҜгҒ„гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢжјўж–№и–¬гҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮ
ж¬ЎгҒ®пјҳгҒӨгҒ®з”ҹи–¬гҒҢгғ–гғ¬гғігғүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- йә»й»„пјҲгҒҫгҒҠгҒҶпјү
- иҠҚи–¬пјҲгҒ—гӮғгҒҸгӮ„гҒҸпјү
- д№ҫе§ңпјҲгҒӢгӮ“гҒҚгӮҮгҒҶпјү
- з”ҳиҚүпјҲгҒӢгӮ“гҒһгҒҶпјү
- жЎӮзҡ®пјҲгҒ‘гҒ„гҒІпјү
- зҙ°иҫӣпјҲгҒ•гҒ„гҒ—гӮ“пјү
- дә”е‘іеӯҗпјҲгҒ”гҒҝгҒ—пјү
- еҚҠеӨҸпјҲгҒҜгӮ“гҒ’пјү
гҒ“гҒ®дёӯгҒ§гҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢйЈҹе“ҒгҒЁгҒ—гҒҰе…ҘжүӢеҸҜиғҪгҒӘгҒ®гҒҜгҖҒд№ҫе§ңгҒЁжЎӮзҡ®гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮд№ҫе§ңгҒҜж–Үеӯ—йҖҡгӮҠз”ҹе§ңгӮ’д№ҫзҮҘгҒ•гҒӣгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷпјҲи©ігҒ—гҒ„гӮӯгғғгғҒгғігҒ§гҒ®дҪңгӮҠж–№гҒҜгҖҒгӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§гҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮпјүжЎӮзҡ®гҒҜгӮ·гғҠгғўгғігҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒиҠҚи–¬гӮ„з”ҳиҚүгҒҜгғҸгғјгғ–гҒЁгҒ—гҒҰиіје…ҘгҒ§гҒҚгӮӢгҒ»гҒӢгҖҒж§ҳгҖ…гҒӘеҠ е·ҘйЈҹе“ҒгҒ«йҰҷж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ жјўж–№и–¬гҒ®и–¬еҠ№гҒҜгҖҒз”ҹи–¬еҗҢеЈ«гҒ®гӮ·гғҠгӮёгғјгҒ«гҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҖӢеҲҘгҒ«йЈҹгҒ№гҒҰеҗҢгҒҳеҠ№жһңгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгҒӢгҒҜеҲҶгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒз”ҹе§ңгҒҜгҖҒгӮўгғјгғҰгғ«гғҙгӮ§гғјгғҖгҒ§гӮӮи–¬гҒ®жҲҗеҲҶгҒЁгҒ—гҒҰз”ЁгҒ„гӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒЁгҖҒйЈҹгҒ№гҒҰжӮӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒӯгҖӮ
жқұжҙӢеҢ»еӯҰгҒ«гӮҲгӮӢи–¬иҶі

гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјжҖ§йј»зӮҺ
еӯЈзҜҖжҖ§гҒ®гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒҢдё»гҒ«йј»гҒ«иЎЁгӮҢгӮӢдәәгҒҜгҖҒдҪ“иіӘгҒ«гӮҲгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒз”ҹе§ңгӮ„гғҚгӮ®йЎһгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒгғҹгғігғҲгӮ„жҹ‘ж©ҳйЎһгҒӘгҒ©гҒҢз—ҮзҠ¶гҒ®ж”№е–„гҒ«еҪ№гҒ«з«ӢгҒӨгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
з”ҹе§ңгҒҜгҖҒгӮўгғјгғҰгғ«гғҙгӮ§гғјгғҖгҒ®гғҸгғјгғ–и–¬гҒ®дёӯгҒ«гӮӮй…ҚеҗҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢйЈҹе“ҒгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒзҺүгҒӯгҒҺгҒ«гҒҜгӮұгғ«гӮ»гғҒгғігҒҢиұҠеҜҢгҒ§гҒҷгҒ—гҖҒжҹ‘ж©ҳйЎһгҒ«гҒҜгғ“гӮҝгғҹгғіCгҒҢиұҠеҜҢгҒ§гҒҷгҖӮ科еӯҰзҡ„гҒ«гӮӮиЈҸд»ҳгҒ‘гӮүгӮҢгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ
гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјжҖ§гҒ®зӣ®гҒ®гҒӢгӮҶгҒҝ
еӯЈзҜҖжҖ§гҒ®гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гҒҢдё»гҒ«зӣ®гҒ«иЎЁгӮҢгӮӢдәәгҒ«гҒҜгҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®гғҸгғјгғ–иҢ¶гҒҢиүҜгҒ„гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
- гҒёгҒЎгҒҫиҢ¶
- гӮӘгӮӘгғҗгӮіиҢ¶
- гҒ©гҒҸгҒ гҒҝиҢ¶
- гҒҜгҒ¶иҢ¶
гҒ„гҒҸгҒӨгҒӢи©ҰгҒ—гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгҒҠеҸЈгҒ«еҗҲгҒҶгӮӮгҒ®гҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®гғҗгӮӨгӮӘеҖӢжҖ§гҒ«еҗҲгҒҶгӮӮгҒ®гӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҒӯгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒеӯЈзҜҖжҖ§гҒ®гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒ«гӮҲгӮӢзӣ®гҒ®гҒӢгӮҶгҒҝгҒ®и§Јж¶Ҳжі•гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҺзӣ®гҒ®гҒӢгӮҶгҒҝгҖҸпјҲ2024е№ҙ2жңҲе…¬й–ӢдәҲе®ҡпјүгҒ§и©ігҒ—гҒҸгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒдҪөгҒӣгҒҰгҒ”зўәиӘҚгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
зӣ®гҒЁйј»гҒ®дёЎж–№гҒ«еҠ№гҒҸйЈҹе“Ғ
иҠӢйЎһгҖҒиұҶйЎһгҖҒз”ңиҢ¶гҒӘгҒ©гҒҢгҖҒдҪ“иіӘгҒ«гӮҲгӮүгҒҡгҖҒдёЎж–№гҒ®з—ҮзҠ¶гҒ®ж”№е–„гҒ«еҠ№гҒҸгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒӢгӮүгҒ®гӮўгғүгғҗгӮӨгӮ№

д»ҠеӣһгҒҜгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠгҒҹгҒҸгҒ•гӮ“гҒ®жғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒз§ҒгҒ®еҚ°иұЎгҒ§гҒҜгҖҒж¬ЎгҒ®йЈҹе“ҒгҒҢз·ҸеҗҲзҡ„гҒ«еӯЈзҜҖжҖ§гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒ®ж•‘дё–дё»гҒ«гҒӘгӮҠгҒқгҒҶгҒ гҒЁж„ҹгҒҳгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
- гғ–гғӯгғғгӮігғӘгғј
- зҺүгҒӯгҒҺ
- гғҷгғӘгғјйЎһ
- з”ҹе§ң
- гҒІгҒҳгҒҚ
з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгӮүгҒҜгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§гӮӮйЈҹе“ҒгҒ§гҒҷгҖӮи–¬гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгӮүгҖҒдёҖеҸЈйЈҹгҒ№гҒҹгӮүз—ҮзҠ¶гҒҢжІ»гҒҫгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮжҜҺж—ҘгҖҒйҒ©йҮҸйЈҹгҒ№з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮўгғ¬гғ«гӮІгғігҒ«иІ гҒ‘гҒӘгҒ„дҪ“гӮ’дҪңгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒңгҒІгҖҒд»Ҡе№ҙгҒҜгҖҒи–¬гҒ§дёҖжҷӮзҡ„гҒ«еӯЈзҜҖгӮ’гӮ„гӮҠйҒҺгҒ”гҒҷгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒж №жң¬зҡ„гҒӘдҪ“гҒҘгҒҸгӮҠгҒ«зқҖжүӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гҒҹгӮүе¬үгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒгҖҺйўЁйӮӘгҒЁгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒ®иҰӢеҲҶгҒ‘ж–№гҒЁгӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶гӮ’жҘҪгҒ«гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢйЈҹе“ҒгҖҸгӮӮгҒ”еҸӮз…§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
зү№еҲҘи¬ӣеә§

зү№еҲҘи¬ӣеә§гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеӯЈзҜҖжҖ§гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјз—ҮзҠ¶дәҲйҳІгҒЁз·©е’ҢгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гғ¬гӮҜгғҒгғЈгғјгӮ’й–ӢеӮ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
и©ізҙ°гҒЁгҒҠз”ігҒ—иҫјгҒҝгҒҜдёӢгҒ®гғңгӮҝгғігҒӢгӮүгҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№

гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒгӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲгҒ®гғһгӮӨгғігғүгғ»гғңгғҮгӮЈгғ»гғЎгғҮгӮЈгӮ·гғіи¬ӣеә§гӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§еӯҰгҒігҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹ
гӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјгӮігғјгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢйЈҹгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҒ”иҮӘиә«гҒ®дё»жІ»еҢ»пјҲгӮ»гғ«гғ•гғүгӮҜгӮҝгғјпјүгҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеҝ…иҰҒгҒӘзҹҘиӯҳгҒЁгӮ№гӮӯгғ«гӮ’ж•ҷгҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еӯЈзҜҖжҖ§гӮўгғ¬гғ«гӮ®гғјгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒж №жң¬гҒӢгӮүжІ»гҒӣгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„йЈҹе“ҒгҒ®дҪңгӮҠж–№гӮӮгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠз”ігҒ—иҫјгҒҝгҒҠеҫ…гҒЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮи¬ӣеә§гҒ§гҒҠдјҡгҒ„гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гғ—гғ©гӮӨгғҷгғјгғҲгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°гғ»гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ

гҒ§гӮӮгӮӮгҒ—гҖҒгҒҠгҒІгҒЁгӮҠгҒ§еҸ–гӮҠзө„гӮҖгҒ“гҒЁгҒ«дёҚе®үгӮ„йӣЈгҒ—гҒ•гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гҒҹгӮүгҖҒгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒЁгҖҒдёҖеәҰгҖҒи©ұгӮ’гҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹ
е…¬иӘҚгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгҒҜгҖҒйЈҹдәӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгӮ’еҸ–гӮҠе·»гҒҸж§ҳгҖ…гҒӘгҒ“гҒЁпјҲз’°еўғгҖҒд»•дәӢгҖҒ家ж—ҸгҖҒдәәй–“й–ўдҝӮгҒӘгҒ©пјүгӮ’иҖғж…®гҒ—гҒҰгҖҒгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«еҸҚжҳ гҒ•гҒӣгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒҢгҖҒгҒӘгӮҠгҒҹгҒ„гҒӮгҒӘгҒҹгҒ«гҒӘгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгӮігғјгғҒгғігӮ°гӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ—гғ©гӮӨгғҷгғјгғҲгғ»гғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°гғ»гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
гҒҠж°—и»ҪгҒ«гҒ”зӣёи«ҮгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
еҲқеӣһзӣёи«ҮгӮ’з„Ўж–ҷгҒ§гҒҠеҸ—гҒ‘гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еҝғгҒЁдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒ„гҒ§еҒҘеә·гҒЁе№ёгҒӣгӮ’жүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢ
гғӢгғҘгғјгӮ№гғ¬гӮҝгғјгҒ®гҒ”зҷ»йҢІгҒҜгҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮү
зөұеҗҲйЈҹйӨҠеӯҰпјҲгғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜж „йӨҠеӯҰпјүеҶҠеӯҗгҒҢз„Ўж–ҷгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ
еҸӮиҖғж–ҮзҢ®пјҡ
- вҖңQuercetin is more effective than cromolyn in blocking human mast cell cytokine release and inhibits contact dermatitis and photosensitivity in humansвҖқ, Zuyi Weng, Bodi Zhang, Shahrzad Asadi, Nikolaos Sismanopoulos, Alan Butcher, Xueyan Fu, Alexandra Katsarou-Katsari, Christina Antoniou, Theoharis C Theoharides, PLoS One, 2012;7(3):e33805. doi: 10.1371/journal.pone.0033805. Epub 2012 Mar 28, PMID: 22470478 PMCID: PMC3314669
- вҖңQuercetin with the potential effect on allergic diseasesвҖқ, Morteza Jafarinia, Mahnaz Sadat Hosseini, Neda Kasiri, Niloofar Fazel, Farshid Fathi, Mazdak Ganjalikhani Hakemi, Nahid Eskandari, Review Allergy Asthma Clin Immunol, 2020 May 14;16:36. doi: 10.1186/s13223-020-00434-0. eCollection 2020, PMID: 32467711 PMCID: PMC7227109
- вҖңVitamin C depletion is associated with alterations in blood histamine and plasma free carnitine in adultsвҖқ, C S Johnston, R E Solomon, C Corte, J Am Coll Nutr, 1996 Dec;15(6):586-91. doi: 10.1080/07315724.1996.10718634, PMID: 8951736
- вҖңDifferent signals induce mast cell inflammatory activity: inhibitory effect of Vitamin EвҖқ, L Tettamanti, Al Caraffa, F Mastrangelo, G Ronconi, S Kritas, I Frydas, P Conti, J Biol Regul Homeost Agents, 2018 Jan-Feb;32(1):13-19, PMID: 29504360
- вҖңHerbal medicines for the treatment of allergic rhinitis: a systematic reviewвҖқ, Ruoling Guo, Max H Pittler, Edzard Ernst, Ann Allergy Asthma Immunol, 2007 Dec;99(6):483-95. doi: 10.1016/S1081-1206(10)60375-4, PMID: 18219828
- вҖңAnti-inflammatory activities of Aller-7, a novel polyherbal formulation for allergic rhinitisвҖқ, N Pratibha, V S Saxena, A Amit, P D’Souza, M Bagchi, D Bagchi, Int J Tissue React, 2004;26(1-2):43-51, PMID: 15573692
- вҖңGinger extract versus Loratadine in the treatment of allergic rhinitis: a randomized controlled trialвҖқ, Rodsarin Yamprasert, Waipoj Chanvimalueng, Nichamon Mukkasombut, Arunporn Itharat, Clinical Trial BMC Complement Med Ther, 2020 Apr 20;20(1):119. doi: 10.1186/s12906-020-2875-z, PMID: 32312261 PMCID: PMC7171779
- вҖңRelationship between Hay Fever and Mineral Concentration in the Hair, Lifestyle or AgingвҖқ, Kaito Yamashiro, Fumihiko Ogata, Naohito Kawasaki, Yakugaku Zasshi, 2017;137(8):1035-1040. doi: 10.1248/yakushi.17-00078, PMID: 28768942
- гҖҢиөӨгғҜгӮӨгғігҒ§й ӯз—ӣгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢдәәгҒҢгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҒӘгҒңпјҹгҖҚгҖҒгғЎгғҮгӮЈгӮ«гғ«гғҲгғӘгғ“гғҘгғјгғігҖҒ2023е№ҙ12жңҲ4ж—Ҙ
- гҖҢгғҗгӮҝгғјгғҗгғјпјҲиҘҝжҙӢгғ•гӮӯпјүгӮ’еҗ«гӮҖйЈҹе“ҒгҒ®ж‘ӮеҸ–гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжіЁж„Ҹе–ҡиө·гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®еҜҫеҝңгҖҚгҖҒеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒеҢ»и–¬йЈҹе“ҒеұҖйЈҹе“Ғе®үе…ЁйғЁеҹәжә–еҜ©жҹ»иӘІж–°й–ӢзҷәйЈҹе“ҒдҝқеҒҘеҜҫзӯ–е®ӨгҖҒе№іжҲҗ24е№ҙ2жңҲ8ж—Ҙ
гӮҪгғ•гӮЈгӮўгӮҰгғғгӮәгғ»гӮӨгғігӮ№гғҶгӮЈгғҶгғҘгғјгғҲ – гғӣгғӘгӮ№гғҶгӮЈгғғгӮҜгғҳгғ«гӮ№гӮігғјгғҒгғігӮ°